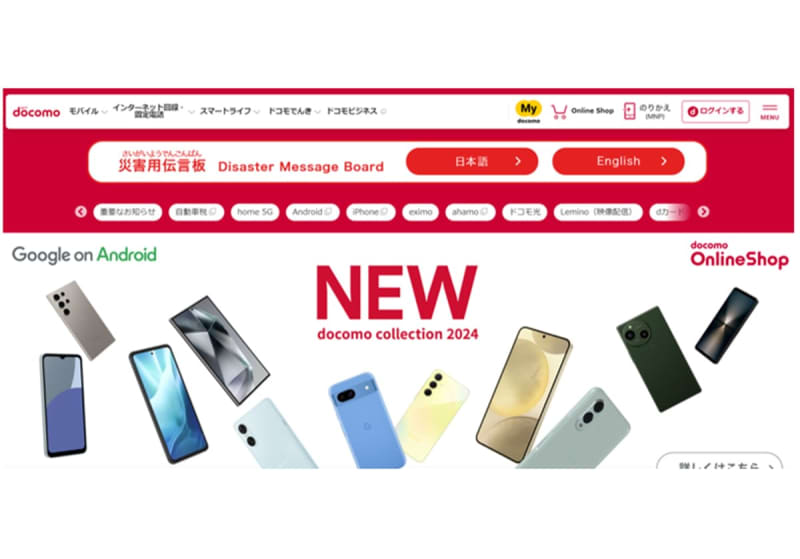
昨年3月、NTTドコモはオンライン申し込み限定の料金プラン「ahamo」などの契約において、楽天グループ(G)の子会社・楽天カードが発行する「楽天カード」を支払い手段として登録することを停止した。報道によれば、両社とも「協議の上で停止している」「メンテナンスのため」と回答しており、再開時期はいまだに不明のまま。
ドコモでの楽天カード利用停止は、携帯電話事業で競合となる楽天モバイルへのけん制という推測も一部では見受けられる。2020年に正式サービスを開始した「楽天モバイル」は、携帯電話事業としては後発組だが、1GB以下0円(2022年7月に廃止)、使用データ量による低料金化、楽天経済圏でのポイント優遇などのメリットを武器に契約者数を増加。契約数は今月13日時点で680万回線となっており、年内に関東の5Gエリアが最大1.6倍に拡大する点や、プラチナバンドと呼ばれる700MHz帯の新バンドが6月に商用化される点なども契約者増加の追い風になると期待される。
加えて、NTTドコモには楽天カードから自社のクレジットカードである「dカード」への移行を進める目論見があるのでは、といった推察も見受けられる。楽天カードは05年からサービス開始し、発行枚数は3000万枚を超えており、国内屈指のクレジットカード。そのためドコモが楽天カードの利用を制限し、自社カードの契約者数を増やす魂胆があるのではないかという見方だ。はたしてドコモの本当の思惑とは。キャリア関係者に聞いた。
原因はシステム上の問題、もしくは政治的な面でのトラブルが濃厚か
「まず、『ドコモが自社利益のために楽天カードを利用停止した』という見方は事実とは異なると思います。楽天カードの利用停止は、ドコモが公式で発表しているとおり、本当にシステム的な障害の可能性が濃厚。もしくは2社間での連携の不十分さが原因だと考えられます。
これは推測ですが、楽天経済圏における楽天ポイント付与の複雑さが背景にあるかもしれません。というのも楽天は、SPU(スーパーポイントアッププログラム)に代表されるように楽天Gのサービスを使えば使うほどお得に楽天ポイントを貯められる仕組みになっていますが、その分ポイント付与のシステムがかなり複雑になっていることが予想されます。たとえば、2社間でポイント付与に関する特殊な取り決めを設定しようとしたものの、技術的な問題によって実現できずそのままになっている可能性もゼロではないでしょう。もしくは政治的な問題によって双方の合意が得られず、やむを得ずに停止しているということもあるかもしれません」(キャリア関係者)
そのほかにも考えられるケースはあるという。
「不正防止への対策というケースも考えられます。楽天カードは業界内でも審査がかなり緩めですので、気軽に申し込みやすい分、不正に利用されるリスクも高い。ドコモの社内規定で『不正利用のうち、○%を超えるとカードの利用を停止する』といった文言があり、これを理由に利用停止した可能性も考えられるワケです」(同)
ではドコモとしては、楽天カードの利用再開を前向きに考えているのだろうか。
「おそらく前向きでしょう。携帯電話事業は公共性が高く、社会インフラの役割を担う事業ですので、一部のクレジットカードの利用のみを制限すると、多くのユーザーから反感を買うことにつながりかねず、発行枚数が格段に多い楽天カードの利用を停止することは避けたいはず。他社の携帯キャリアでも自社以外のクレジットカードの利用を停止する、といったケースは聞いたことがありません。
ただ公式からの発表は、簡素なコメントのみで納得できないというユーザーも少なくないでしょうから、もう少し詳細を明らかにして説明すべきだと感じます。2社の社会的信用を保つためにきちんと説明する必要はあるでしょう」(同)
また、「他社クレジットカードを利用停止し自社の利益を守る」という発想が出てこないほど、携帯電話事業はひとつ上のフェーズに移行しているという。
「現在、携帯電話事業者は金融と強い結びつきを持ったビジネスを展開しています。代表的なところで言えば、KDDIはauじぶん銀行を、ソフトバンクはPayPay銀行を、楽天Gは楽天銀行を持っています。国内の携帯電話サービスはドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルの4社が提供する体制になっており、業界を寡占する形となっていますが、これ以上携帯市場で収入を伸ばしていくことはほぼ不可能。したがって、各社は携帯電話事業で得たマネーでさらに増収が見込める金融事業へと手を伸ばしているワケです。NTTが携帯電話事業を実質的に独占していたときも銀行設立の構想はあったものの、当時は銀行の圧力が強く、設立に至りませんでした。しかし、現在は事業者が増えたことや、スマホユーザー数の増加によりインフラとしての価値が高まったことが要因となり、今後も携帯電話事業者が金融事業に進出していくことは容易に考えられます。
通信インフラ事業は、今や人々の生活に欠かせない存在となっています。そのため、支払い手段が限られてくると、ユーザーの負担は増しますし、クレームも予想される。またクレジット決済を許可しないと、コンビニ支払いなどキャッシュでの決済が増加し、未支払いのリスクも出てきて、回収コストも増える可能性があります。加えて、近年の金融事業への参入を考えると、他社クレジットカードの利用停止を戦略的に行うとは考えにくいというわけです」(同)
(取材・文=文月/A4studio)
