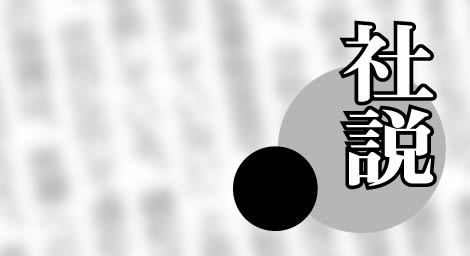
自治体に対する国の「指示権」を拡大する地方自治法改正案がきのう、衆院本会議で可決された。
自治体行政への国の介入は、災害や感染症などの事態に応じて関係する法律ごとに定めてきた。改正案は非常時に、個別法の定めがなくても国が自治体に指示権を行使できる規定を置くものだ。
「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態」を要件とするが、政府は現時点で具体的に想定し得るものはないとする。こんな「白紙委任」のような状態で指示権限が拡大すれば、恣意(しい)的な運用の余地を生む。地方自治をゆがめる恐れが拭えない。
改正案は新型コロナウイルス禍の対応を巡り、国と地方の連携がスムーズに機能しなかったことを踏まえたという。政府関係者は当時の安倍晋三首相が一斉休校を要請して混乱を招いたのを引き合いに、「法的な裏付けがないことを繰り返さないための法整備」と強調する。本気で言っているのだろうか。
法改正は逆に、権力者の思い付きやむちゃな要求にまでお墨付きを与えることになる。自民党などが憲法改正で新設を目指す緊急事態条項を先取りする動きに見えて、危うさを感じざるを得ない。
看過できないのは、どのような場合に指示権を行使できるかが曖昧なことだ。これまでの審議で松本剛明総務相は「個別法では想定されていない事態」と繰り返すばかりで説明になっていない。政府がこの体たらくなら国会は本来、廃案にすべきだ。
まずは個別法をベースに対応するのが筋だ。緊急時に起こりそうな課題を国会で議論し、関係する法律ごとに指示できる規定を設ければ済む話である。そして想定外の事態で重要なのは、国と地方が解決策を見いだすため対等に議論することではないか。
乱用の懸念に対し、自民、公明、日本維新の会の3党は政府提出の改正案を修正。指示権を発動した閣僚に国会への事後報告を義務付けたが、閣議決定だけで指示を出せることには変わりない。衆院総務委員会は全国知事会の要望を踏まえ、関係自治体との事前調整を付帯決議に明記したが、こちらは努力義務で歯止めにはなるまい。
沖縄の米軍基地問題を巡る政府の姿勢を見る限り、国が地方の意向を尊重した運用に努めるとは思えない。地方側は、もっと危機感を持つ必要があるのではないか。
地方自治の重要な機能に「垂直的権力分立」がある。権限が国と地方に分配されることで自治体が国の政策をチェックする役割を果たす。中央集権体制で国全体が戦争にひた走った反省から、憲法は地方自治に1章を割き、地方自治法も同時施行されたことを忘れてはならない。
改正案は衆院を通過したが「再考の府」の参院で問題点を洗い出し、なぜ改正が必要か、政府の本当の狙いは何なのか、徹底的な議論で明らかにする必要がある。少なくとも指示権の乱用を防ぐ手だてが保障されない限り、今国会での成立は見送るべきだ。

