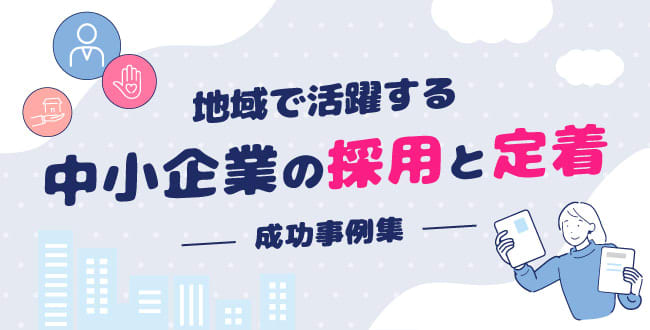
東京商工会議所が中小企業を対象に2023年9月に行った全国調査では、「人手不足」との回答が7割近く(68.0%)となり、2015年の調査開始以降、最大であったことを明らかにしています。
人口減少に伴い、国内の働き手不足が今日の話題となっており、特に地方における中小企業では、人手不足にお困りの方も多いかもしれません。
そんな中、厚生労働省は、新たな人材の採用や定着に成功している中小企業にヒアリングを行った結果を成功事例として取りまとめ、2024年3月に公表しています。
この事例集では、計20社の主な課題とそれに対する取り組みが紹介されています。
そこで今回は、よくある採用と定着の課題に対する成功事例を取り上げ、課題を解決するための具体的な工夫やポイントをお伝えしていきます。
地域を支える中小企業の経営者の方や採用担当の方へのヒントになれば幸いです。
採用人数の増加を目指す
POINT:採用活動の工夫・多様化
多くの企業で行われていたのは、求人ページの掲載内容の見直しと、SNSを活用した発信です。
例えば、ホームページにて「人材に関する考え方」の掲載を行いながら、SNSでは業務内容と従業員の紹介をしている事例(卸小売:アサヤ株式会社)や、応募の心理的ハードルを下げられるように求人表現の見直しを重ねている事例(卸小売:株式会社セラビ)があります。
このように、その会社で働くイメージができるような工夫によって関心を集めることができるほか、SNSの活用により多くの人に会社を知ってもらうきっかけづくりが可能です。
また、多くの企業が職場体験を実施しています。
会社理念を体感してもらう目的で一日研修を実施している事例(保育:株式会社みらい)や、学生が得意なことで業務を体験できる機会を設けている事例(製造:株式会社センショー)などです。
また、中途人材の採用競争が厳しいことから、地元の大学や専門学校の新卒を中心に職場体験を展開するのも一つの手であると考えられます。
実際、地元の新卒を対象としたインターンシップの積極開催と、最終選考における数日間の職場体験を実施する企業(情報通信:株式会社シアンス)があります。
このような職場体験は、会社への理解を深めることができるため採用につながりやすく、入社後のミスマッチも防げるメリットがあると考えられます。
POINT:誰もが活躍できる環境整備
誰もが活躍できる環境は、採用活動をする上で企業のアピールポイントになり、採用できる従業員の幅も広がります。
例えば、作業のマニュアル化は働きやすい印象を与え、作業が効率化するため残業対策としてもアピール可能です。
また、「誰もが活躍できる」という言葉の通り、多様な人材を積極的に採用している企業も多くあります。
短時間勤務でも正社員に登用しプロジェクトの責任者を任せる制度を導入している事例(運輸:大橋運輸株式会社)や、インバウンド需要に伴う外国人材の採用を進めている事例(情報通信:株式会社ペンシル)です。
さまざまな強みを持つ多種多様な人材の存在は、企業にとっても付加価値となり、多角的な視点を持つことは企業の発展にもつながり得るのではないでしょうか。
従業員の離職を防ぐために働きやすい職場づくりを推進したところ、新たな人材の確保につながった例もあります。
地方での離職要因として多い介護離職を防ぐ意図でテレワークを導入したところ、働きやすさが向上し、地方でも全国の優秀な人材を呼び込むことに成功している事例(製造:兵庫ベンダ工業株式会社)です。
時間的・地理的な制約がある人材に就業してもらうための工夫として、現場に出向く必要のない業務は、テレワークを導入してみてもよいかもしれません。
既存の従業員の定着を目指す
POINT:事業戦略の転換
事業戦略を転換することで、人手不足を解消している事例がいくつかあります。
請負事業形態による長時間労働のため退職が相次ぎ、人手不足が課題だった企業(情報通信:株式会社シアンス)では、顧客と直接契約の事業運営に転換しました。
その結果、受注量や仕事内容を選べるようになり、働き方の調整が可能となったため、働きやすい環境づくりや、利益率の向上につなげています。
また、自社製品の知名度の低さから、若者の関心集めや従業員の意欲低下が課題であった事例(製造:兵庫ベンダ工業株式会社)では、主軸事業が他の分野でどのように活用されているかを「見える化」する戦略を立て、魅力の発信に力を入れています。
その結果、従業員のモチベーションが向上し離職率の低下を達成するとともに、関心を持って就職を希望する若者を増やしています。
事業戦略の転換は勇気が必要かもしれませんが、課題解決のためにもこのような新たな戦略を考えてみるのも一つの手ではないでしょうか。
POINT:業務の見直し
業務の見直しは働きやすさに直結し、従業員の定着率アップにつながりやすいと考えられます。
求人広告にお金をかけるよりも、今いる人材が働き続けられるような環境整備を優先する方が効果的な場合も多いのではないでしょうか。
例えば、可能な範囲でジョブローテーションを実施している事例(運輸:株式会社トレンディ茨城)では、従業員の担当できる業務の幅が広がり、業務代替が可能となったことで、休みやすい環境につながっています。
気兼ねなく休める安心感は精神的負荷を軽減するでしょう。
肉体労働をメインとしている仕事内容であれば、身体的負担を軽減する装備品の支給や機械の導入が効果的です。
身体的ストレスの軽減だけでなく、仕事内容へのネガティブなイメージも解消されます。
新たな備品や機械の導入にはコストがかかりますが、従業員を大切にしていることが伝われば人材へのPRにもなり、離職率の低下も相まって結果的に導入コストを回収できると考えられます。
また、顧客との信頼関係の構築に向けた業務の見直しが好循環となり、結果として採用人数の増加や従業員の定着を達成している企業があります。
従業員への資格取得を会社負担で支援し、資格に応じて手当の額が上がる仕組みを採用した企業(警備:株式会社セキュリティ庄内)では、従業員のレベルの高さが評価され、安定的な受注と従業員の賃上げを達成し人材定着につながっています。
業務の進捗の可視化ができるアプリを自社で開発した事例(建設:隂山建設株式会社)では、アプリによって進捗の確認が容易になったため、顧客とのコミュニケーション頻度が増えて、従業員のやりがいを獲得しています。
このように、顧客の満足度が高まるような働きかけは、結果的に従業員の働きがいとなり、定着率の向上に至ると考えられます。
さいごに
どの事例も、まずは経営課題を見つめ直し、従業員の採用と定着において何が問題であるかを考察した上で、その改善に向けて実現可能な範囲で新たな取り組みを行っていると感じられました。
全体を通して、従業員のモチベーションが向上するような取り組みや、働きやすさを追求することが採用と定着のポイントであると考えられます。
ぜひ参考にしてみてください。
地域を支える中小企業で、いきいきと働ける従業員の方が増えることを願っています。
<参考>
・ 厚生労働省「地域で活躍する中小企業の採用と定着 成功事例集」
・ 日本商工会議所「日商ニュース『人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査』 の集計結果について ~中小企業の7割近くが人手不足、8割強が仕事と育児の両立推進が必要と感じていると回答~」
・ 内閣府、金融庁、厚生労働省、経済産業省「中小企業が使える人材確保支援策・働き方改革支援策」
