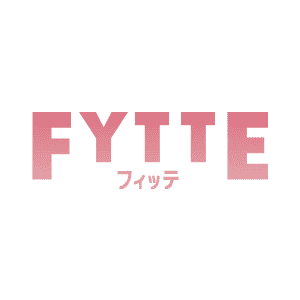By フォーブス 弥生

梅雨入りすると気温や湿度が高く、頭痛や食欲不振、気分が晴れないなどのメンタルの不調を起こす人も多いですよね。この時期、胃腸が弱い人はお腹の痛みや張り、ガス、下痢、便秘の消化器系や不安・うつなどの症状が起こりやすいそうです。今回は、「FODMAP(フォドマップ)」という海外で注目されている食事療法について、一般社団法人グルテンフリーライフ協会 フォーブス弥生さんに教えてもらいました。
長引くお腹の不調が改善するかも!? 自分の腸と相性の悪い食品を探る治療法とは?

まもなく梅雨の時期に入りますね。梅雨に入ると気温や湿度が高く、食欲不振になる人も多いのではないでしょうか。とくに胃腸が弱い人は、食生活に注意が必要です。
FODMAP(フォドマップ)という言葉を聞いたことはありますでしょうか。FODMAP(フォドマップ)とは、小腸で吸収されにくく大腸で発酵しやすい糖類の総称となり、英語の頭文字を合わせた言葉です。FODMAPを多く含む食品を「高FODMAP食」といい、一般的に腸によいと言われている食品の中にも高FODMAP食はあります。
【高FODMAP食】
Fermentable: 発酵性の
Oligosaccharides: オリゴ糖(小麦・玉ねぎ・にんにく・ごぼう・納豆・豆類など)
Disaccharides: 二糖類(牛乳・ヨーグルト・アイスクリーム・クリームチーズなど)
Monosaccharide: 単糖類(はちみつ・スイカ・りんご・アスパラガスなど)
And: アンド
Polyols: ポリオール(人工甘味料・きのこ類・セロリなど)
近年、過敏性腸症候群(群(irritable bowel syndrome:IBS)の食事療法として、「低FODMAP食」が注目されています。過敏性腸症候群(以下、IBSとする)とは、小腸や大腸に炎症や腫瘍など検査でわかる異常がないにも関わらず、数か月以上続くお腹の痛みや張り、ガス、下痢、便秘などの症状をきたす病気です。有病率は世界人口の15%で、7人に1人がかかるとも言われています。また、IBSは消化器症状で外来受診する患者の約3割を占めるそうです。
IBSは、現在の国際的診断基準の Rome IV(ローマIV) では4つの(便秘、下痢、混合、分類不能)型に分類されます。命に関わる病気ではありませんが、症状によっては日常生活に支障をきたすこともあります。
さらに、脳腸相関とも関わりがあるとされています。脳腸相関とは、脳と腸は双方向性の密接な関係のことです。すなわち、ストレスによって生じる消化器症状(脳から腸へ)と、消化器症状によって情動へ影響が生じる(腸から脳へ)現象のことを指します。具体的な症状としてお腹の痛みや張り、ガス、下痢、便秘の消化器系や不安・うつなどの心理的異常などです。この伝達には、セロトニンが重要な役割を果たしていることが明らかになっています。セロトニンとは、幸せホルモンとも呼ばれており、脳内に存在する神経伝達物質の一種です。

「低FODMAP食」の食事療法は、オーストラリア・メルボルンにあるMonash University(モナッシュ大学)により、IBSの下痢型および便秘型のどちらの場合にも、4人中3人が症状が軽減したという研究結果が報告されており、科学的根拠の高い食事法とされています。問題を引き起こしている高FODMAP食を特定して、できるだけその食品を避けることで、お腹の不調が改善するというデータがあります。通常、目安期間としては約2〜6週間です。
【低FODMAP食】
●穀物:白米・玄米・オートミール・米粉麺(ビーフン)など
●野菜:なす・にんじん・きゅうり・レタス・キャベツ・ジャガイモ・ズッキーニなど
●果物:キウイ・バナナ・みかん・パイナップルなど
●たんぱく質:肉類・魚介類・卵など
「低FODMAP食」の食事方法とは「高FODMAP食品」を食べないのではなく、自分の腸と相性の悪い食品を探るための食事方法です。自己判断で進めると栄養バランスが著しく偏ってしまいますので、医師や管理栄養士に相談することをおすすめします。
参照:https://www.monashfodmap.com/