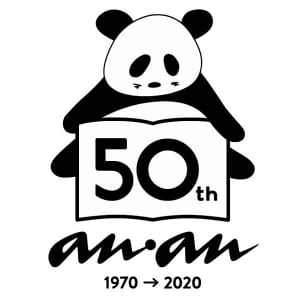口臭対策、できていますか?

【カラダとメンタル整えます 愛先生の今週食べるとよい食材!】vol. 268
人と話している時、吐く息がちょっとニオうなと感じることはないでしょうか。同時に、自分はどうなんだろうと不安に感じることもあると思います。口臭がもっともきつくなる時間帯は朝起きたときであり、その次に昼食前や夕食前などもニオイがきつくなる傾向があるようです。ただ、一番ニオイのきつい朝でも、朝食を食べ、歯磨きをするとほぼニオイは消えていきます。
また、それ以外に、イライラして交感神経が優位になり唾液の分泌が減少したり、ニンニク料理、アルコール、たばこなど明らかな原因あるときにもニオイはきつくなります。むし歯や歯周病、副鼻腔炎、扁桃炎、消化不良、肝臓機能の低下などが原因となることもあります。今週はこういった病気ではなく、セルフケアで軽減できる部分の口臭対策となる食薬習慣を紹介していきます。
今週は、口臭対策となる食薬習慣
漢方医学では、人の体調や体質を判断するときに舌の状態をみる舌診という方法をとることがあります。舌診では、舌につく苔の状態も判断材料としています。舌につく苔が多かったり、黄色い時には、胃腸に負担がかっていたり、偏食や食べ過ぎがあったり、心の状態も落ち込みやすかったり、イライラしやすい状態ではないかと仮説を立てることが多いです。そして、この舌の苔ですが、口臭が発生する原因の6割を占めるともいわれています。
つまり、胃腸へ負担のかかる食事、偏食、食べ過ぎ、ストレスが多い環境などの状況下で、口臭を感じやすくなることがわかります。舌苔には細菌や食べかすが含まれるため、舌の表面で細菌が増殖します。また、食べものをよく噛まなかったり、ストレスが多かったりすることで唾液の分泌が減ってしまうため、口の中を自浄することができず、唾液の抗菌作用も働かず、口臭を悪化させる要因のひとつとなってしまうのです。
漢方医学では、口臭を強く感じるとき、偏食や食べ過ぎによって『湿熱』や『胃熱』が生じているケースや、ストレスにより『肝火』が生じているケースを考えることがあります。そこで、今週は『胃』や『肝』の熱を鎮め、『湿熱』を取り除く食薬がおすすめです。
食べるとよい食材は、【ブロッコリースプラウトとリンゴのレモンサラダ】です。そして逆にNG習慣は、【朝食抜き&カフェラテや牛乳習慣】です。
食薬ごはん【ブロッコリースプラウトとリンゴのレモンサラダ】
『肝火』を取り除くスルフォラファンを含むブロッコリースプラウト、『胃熱』を取り除くレモン、『湿熱』を取り除くリンゴやミックスビーンズを組み合わせたサラダで、お口の中をスッキリさせてみてはいかがでしょうか。また、抗酸化や抗糖化、抗炎症作用もありエイジングケア要素満載のサラダです。
<材料>
ミックスビーンズ 50g
リンゴ 1/2
ブロッコリースプラウト 一掴み
レモン 1個(スライス)
レモン汁・オリーブオイル 各大さじ1
ブロッコリースプラウト 1/2パック
塩 お好みで
<作り方>
材料をポリ袋に入れ、よく材料をなじませたら完成。
NG行動【朝食抜き&カフェラテや牛乳習慣】
私たちが寝ている間は、唾液の分泌が減り、寝起きの口臭はきつくなります。また、空腹時間が続くことも口臭の原因となります。ただ、朝食を摂ることによって、唾液の分泌をしっかり促し、唾液のもつ殺菌効果や自浄効果を期待することができるため、口臭対策ができます。さらに、朝食を抜いた状態で乳製品をとることも口臭を悪化させてしまいます。乳製品は舌に付着し停滞しやすく、硫黄化合物を含むタンパク質が口腔内の細菌により分解され、口臭の原因物質を作り出してしまうためです。口臭で悩む人は、朝食を抜いたり、朝にカフェオレや牛乳を飲む習慣を控えたいものです。
口臭で悩む人の中には、端的に舌磨きやマウスウォッシュ、口臭タブレットなどに頼ること1択というかたもいらっしゃるかもしれません。ですが、日ごろ習慣的に食べているものであったり、噛む回数、ストレス状況、そのほかの病気など様々な原因が隠れていることがあります。日によって、口臭の種類が変わることもあると思いますが、何由来のニオイなのかということを考えて対処していくことが、長期的に口臭が気にならない状態を作り出すために役立つと思います。そのほかにも心と体を強くするレシピは、『不調がどんどん消えてゆく 食薬ごはん便利帖』(世界文化社)や新刊『だる抜け ズボラ腎活(ワニブックス)』でも紹介しています。もっと詳しく知りたい方はぜひご覧ください。
※食薬とは…
『食薬』は、『漢方×腸活×栄養学×遺伝子』という古代と近代の予防医学が融合して出来た古くて新しい理論。経験則から成り立つ漢方医学は、現代の大きく変わる環境や学術レベルの向上など現代の経験も融合し進化し続ける必要があります。
近年急成長する予防医学の分野は漢方医学と非常に親和性が高く、漢方医学の発展に大きく寄与します。漢方医学の良いところは、効果的だけどエビデンスに欠ける部分の可能性も完全否定せずに受け継がれているところです。
ですが、古代とは違い現代ではさまざまな研究が進み明らかになっていることが増えています。『点』としてわかってきていることを『線』とするのが漢方医学だと考えることができます。そうすることで、より具体的な健康管理のためのアドバイスができるようになります。とくに日々選択肢が生じる食事としてアウトプットすることに特化したのが『食薬』です。
Information
<筆者情報>
大久保 愛 先生
漢方薬剤師、国際中医師。アイカ製薬株式会社代表取締役。秋田で薬草を採りながら育ち、漢方や薬膳に興味を持つ。薬剤師になり、北京中医薬大学で漢方・薬膳・美容を学び、日本人初の国際中医美容師を取得。漢方薬局、調剤薬局、エステなどの経営を経て、未病を治す専門家として活躍。年間2000人以上の漢方相談に応えてきた実績をもとにAIを活用したオンライン漢方・食薬相談システム『クラウドサロン®』の開発運営や『食薬アドバイザー』資格養成、食薬を手軽に楽しめる「あいかこまち®」シリーズの展開などを行う。著書『心がバテない食薬習慣(ディスカヴァー・トゥエンティワン)』は発売1か月で7万部突破のベストセラーに。『心と体が強くなる!食薬ごはん(宝島社)』、『食薬事典(KADOKAWA)』、「食薬ごはん便利帖(世界文化社)」、「組み合わせ食薬(WAVE出版)」、「食薬スープ(PHP)」など著書多数。
公式LINEアカウント@aika
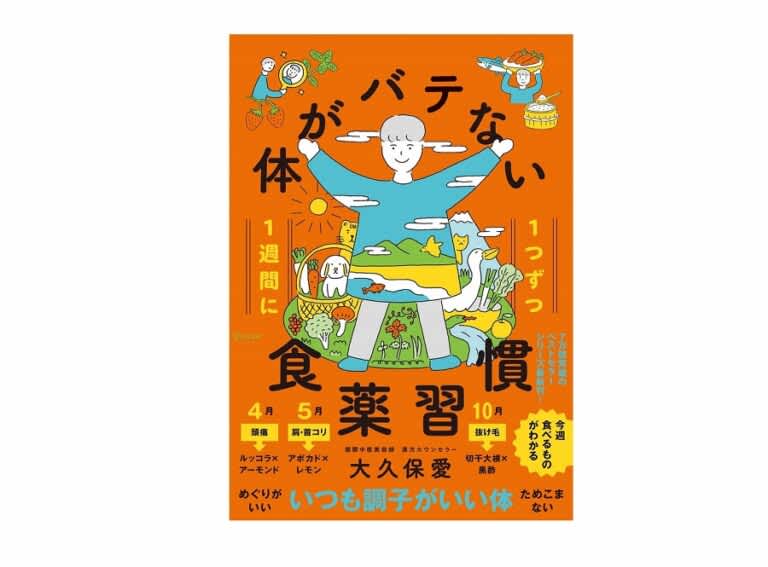
『1週間に一つずつ 心がバテない食薬習慣』(ディスカヴァー)。
『女性の「なんとなく不調」に効く食薬事典』(KADOKAWA)
体質改善したい人、PMS、更年期など女性特有の悩みを抱える人へ。漢方×栄養学×腸活を使った「食薬」を“五感”を刺激しつつ楽しく取り入れられる。自分の不調や基礎体温から自分の悩みを検索して、自分にあった今食べるべき食薬がわかる。55の不調解消メソッドを大公開。