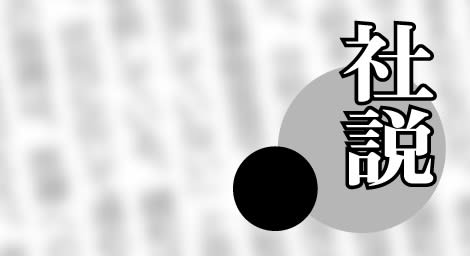学校現場の安全管理に、重い課題を突き付ける司法判断である。
栃木県那須町で2017年3月、部活動で深雪歩行訓練中に雪崩が起き、高校生7人と教諭1人が巻き込まれて死亡した事故で、宇都宮地裁は業務上過失致傷罪に問われていた引率の3教諭に禁錮2年の実刑を言い渡した。
裁判では、雪崩を回避する予見可能性や安全対策の有無が争われた。訓練を主催する立場の3人は「予見できなかった」と無罪を訴えたが、地裁は「相当に重い不注意による人災」と断じた。部活動中の事故で教諭らが実刑判決を受けるのは異例である。
公判では、3人が栃木県高校体育連盟の登山専門部専門委員などを務める経験者なのに、歩行訓練の安全な範囲を明示せず、生徒らにも周知しなかったと指摘された。気象状況の把握のほか、無線での情報共有も怠ったとされた。生徒が勝手に行動したという趣旨の主張もあり、子どもを守る自覚や責任を欠いた態度を、反省がないとみなされた面もあるのではないか。
学校教育活動の一環として行われていた訓練には、とりわけ安全確保が強く求められる。その対策が不十分だったという指摘は、重く受け止めなければならない。
ただ、刑が確定すれば3人は教員免許も失う。これでは部活指導ができなくなると、教育現場に戸惑いが広がることも懸念される。部活動自体が萎縮するような流れに陥らない対応が必要だ。
現場は標高1400メートルを超える高地の急斜面で、雪崩注意報も出ていた。今回の判決は、特段の安全管理が求められていた状況下で危険予測や情報共有を怠っていたことが罪に問われた。通常の部活指導とは、かなり異なる状況だったと認識すべきだろう。
今回の判決に先行した民事訴訟では、司法は県教委などに賠償を命じる一方で、3人の個人賠償は否定した。「公務員の職務上の行為で起きた事故。個人に責任はない」という国家賠償法などに基づく判断である。部活動の事故で教諭の刑事責任を問うことは例外的なものであり、「有罪は故意ではないかと疑われるほど悪質さが際立つ場合だ」とする専門家の意見があるのもうなずける。
教諭は教育のプロであり、危機管理のプロではない。栃木県では雪崩事故後、県立学校で全ての登山活動の安全性をチェックするほか、23年度からは山岳ガイド資格者を各高校に配置した。登山に専門家のガイドを同行させるなど、安全対策を教諭だけに委ねない取り組みを始めたことは前進と言えよう。
危機管理の重要性は登山に限らない。全国の都道府県教委は、全ての部活動に対する危機管理マニュアルを整備すべきだ。現場の教諭に加え、専門家の助言も受けながら、実効的な内容にアップデートしていく必要がある。
それが8人もの犠牲者を出した悲惨な事故のせめてもの教訓だ。今回の判決を、部活動の安全管理を問い直す契機にしなくてはならない。