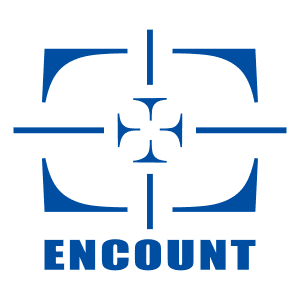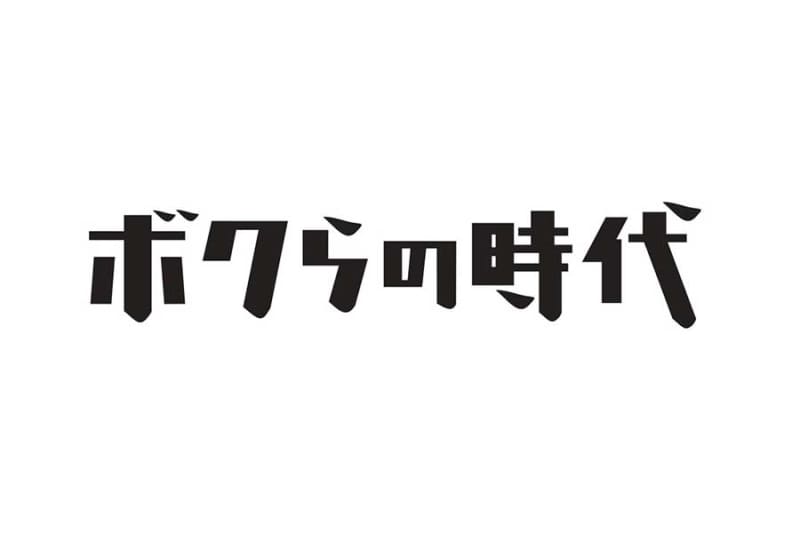
予定調和の無しのフジテレビのトークドキュメンタリー
時代を彩るさまざまな分野の著名人が3人集まってトークを展開するフジテレビ系『ボクらの時代』(日曜午前7時)。出演者の普段とは違う一面が見えたり、意外な事実を聞けるなど本音トークを楽しむことができる。MCがいない上、驚くことに台本も無いというが、本当なのか。本当ならば事前にどんな準備をしているのか。総合演出・高野裕樹氏(イースト・ファクトリー)に舞台裏を聞いた。するとさらなる驚きがあった。(取材・文=中野由喜)
まず、日曜午前7時開始という早い時間の放送枠が気になる。良質な番組なだけに、もう少し遅い時間の方がより多くの人に見てもらえるのではと思うのだが。
高野氏「FODやTVerで配信を見てくれる人もかなり多くて、時間を問わず楽しんでいただいているようです」
番組出演者はどう選んでいるのか。
高野氏「番組開始当初は建築家の安藤忠雄さんやデザイナーの三宅一生さんなど文化人の方が多かったのですが、俳優やアーティスト、アスリートの方など徐々に幅が広がってきました。いろんなジャンルの方に出演していただきたいという意識はもっております。基本的にはどなたか1人にオファーして、その方に誰と話したいかを伺っていくような流れで出演者が決まることが多いです。関係性の高い3人になる形ですが、『会ってみたい人』という希望が実現して初対面のケースもあります」
MC不在の狙い、効果はどこにあるのか。
高野氏「この番組にMCがいないのは、1ショットインタビューでは決して出てこないような、3人の関係性から出てくる話、3人だからこそ話が転がるというところを大事にしているからです。なので、ゲストの方にこういう話をしてくださいといった要求をこちらからはあまりしません。この番組はトークドキュメンタリーとうたっていて、トークが予定調和にならないようにしています」
本当に台本もないのか。
高野氏「せりふが書いてあるような一般的な台本はありません。3人で話せそうなテーマをいくつか書いた資料は参考程度にお渡ししていますが、いつも自由にお話してもらっています。話したくないことは話さなくていいともお伝えしています」
話が思うように展開しない場合もあるのだろうか。
高野氏「そもそも思うようにという概念が無いんです。話が転がっても、転がらなくても、話の展開のあり方に正解はないんです。ご本人が話したいことを話してくれることが大切だと考えています」
台本が無いとなると事前の打ち合わせが重要になると思われる。
高野氏「所属事務所の方も含めて事前の打ち合わせはしないんです。収録直前に数分、座り順などを説明する程度です」
出演者の反応も気になる。
高野氏「はじめてご出演される方は驚かれることも多いです。実は、撮影の時も座っていいただいてから『よーい、スタート』などカウントダウンのような合図も無く収録が始まっているので、『えっ、始まっているんですか?』と驚かれます」
台本もなく事前の打ち合わせもなく、撮影開始の合図さえない番組は珍しい。
高野氏「カメラが回っていない自然体でいる時に面白い話が出ることはよくありますよね。そこで、なるべく収録を意識せず気軽に自由に話してもらえる環境を考えています。この番組は筋書きのないトークドキュメンタリーですから」
「撮りだめだめできない」重大な事情とは
ロケ場所を選ぶ舞台裏も聞いた。
高野氏「番組スタート当初、出演者がよく行くお店を撮影場所として使うことが多かったこともあって、スタジオではなくロケスタイルをそのまま続けています。収録場所は毎回変えていて、都内のカフェや結婚式場などさまざまな場所で撮影しています。実は20年近くやっていると、外光が入ったり、緑があるなど朝の番組の世界観に合う場所は相当使い尽くしている感じです(笑)」
ロケにはもう一つ重大な事情があるようだ。
高野氏「一般的なレギュラー番組は、収録日を固定しているケースがほとんどです。一方、『ボクらの時代』は決まっていません。出演者3人の都合に合わせた日時と場所を選んでいます。忙しい3人の著名人に出演していただくため、3人の都合を考えた場所にこちらから出向いていく形なんです。だから、なかなか撮りだめができません。来週末の放送分をまだ撮れていないということもありました。今も多々あります(笑)」
フジテレビに入社を希望する学生に面接などで一番好きな番組を尋ねると『ボクらの時代』と答える人も少なくないという。07年のスタートから番組のスタイルは変わっていないが出演者のトークは新鮮。朝早い時間の番組だがTVerやFOD、インスタグラムなどを通じ若者にもトークドキュメンタリーの魅力はしっかり伝わっているようだ。中野由喜