
身体的特徴を活かしてモデルとして活動する女性がいます。身長123cmの大学生、星来(@seira_123cm)さんは、現在芸能事務所に所属しながら学生業と両立させています。
大学では医療保育を学ぶ彼女がモデルを目指したきっかけはなんだったのでしょうか。星来さんに話を聞きました。

もっと身近な存在に
2型コラーゲン異常症とは、同遺伝子の変異で発症するX線所見が類似した複数の疾患をまとめた疾患概念です。星来さんの詳しい疾患名は『先天性脊椎骨端異形成症』。
この疾患には低身長の人が多く、なかには目の異常、難聴、口蓋裂など、人によって様々な合併症も発症することがあるのだとか。同じ疾患でも別の診療科に通っている場合もあるなど、生活スタイルが大きく異なっているそうです。

星来さんがモデルを目指したのはSNSがきっかけでした。障がい者専門の芸能事務所『アクセシビューティーマネジメント』の所属モデルの活動の様子を初めて知ったときに、疾患があっても可愛い服を着たり、疾患がない人と同じように演技をしたり、多くの人に向けて自分の考えを発信したりできることに衝撃を受けました。
これは、星来さんがずっとやりたかったことで、無意識のうちにできないと決めつけてしまっていた活動だったそう。
幼いころから人前で活動をすることに憧れていた星来さん。しかし、身長制限のため、モデルのオーディションに応募さえできない、周りと動きが合わせられるとは限らないなどの理由で、ダンスを習うことをも諦めていました。
そんな経緯のなかで、アクセシビューティーマネジメントは星来さんの夢への道を切り開く場所になりました。
「この場所で『たくさんの人に障がいをもっと身近に感じてもらえるような活動がしたい!』と思い、モデルを目指し始めました」
入院中の出会いが医療保育を学ぶきっかけに
小学6年生のとき、入院を経験した星来さん。そこで出会った入院中の子どもと遊び、子どもの家族の精神的なサポートをする医療保育を行う保育士さんに憧れを持ちました。
このことがきっかけで、星来さんは医療保育を学ぶことができる大学に入学。
しかし、大学1年生のときにアクセシビューティーマネジメントに出会い、考え方が変化します。
「事務所に所属したり、SNSを始めたりしたことで、たとえ間接的であるとしても、1人でも多くの方の障がい者に対する価値観をアップデートすることに、強い魅力を感じました。現在大学卒業後の進路については検討中ですが、メディア、マスコミ関連の仕事を視野に入れています。とはいえ、インクルーシブな社会を実現するためには、幼児期からの教育がとても大切だと考えています。大学で保育学や教育学について学び、保育士資格と幼稚園教諭一種免許状を取得する予定です。そこで手に入れた知識を活かして、園や学校などで講演を行い、子どもにも障がいを身近に感じてもらえるような活動がしたいです」と、将来の夢について語ってくれました。
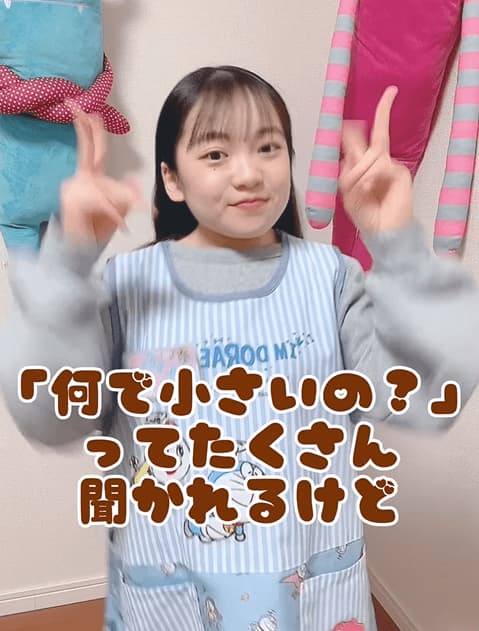
保育実習中、子どもから「なんで小さいの?」と聞かれたという星来さん。このことについては自身のSNSでも発信しています。
「子どもの純粋な好奇心から生まれた質問だと思うので、さほど嫌な気はしなかったです。この質問に対して『病気があって小さいんだよ』と伝え、そのあとに受ける『いつから小さいの?』『何歳なの?』という質問にも丁寧に嘘をつかずに答えると『小さい先生は子ども用の遊具で一緒に遊べる!』と、先生として私の存在を受け入れてくれました」
しかし、他の業務に追われ最後まで子どもへの説明ができないと「小さい先生は嫌だ!」と毛嫌いされたんだとか。このことから、丁寧に疑問に答えることは子どもたちが障がい者を自然に受け入れることにつながると星来さんは感じました。

価値観のアップデート
星来さんが日常で1番大変なことは、洋服選び。大人っぽいデザインの子ども服を探しては試着しての繰り返しなんだそう。着たい服が着られなくて落ち込むこともしばしばあるようです。

しかし、大変なことの多くは、背骨が曲がる側弯症の手術をしたことによる問題。
現在星来さんの背骨には、金属の棒と、それを固定するビスが入っています。転倒してその棒が折れることがないよう、人混みへ行くときは杖を持って出かけています。
また、棒が入っていない部分の骨がこれ以上曲がらないよう、同じ姿勢を長く続けない、荷物をリュックではなくキャリーケースに入れて行動することを星来さんは意識しています。
「飲食店では、座高が低いため頼んだどんぶりの中身が見にくく、食べづらいことがあります。また、行楽地では人混みで対象物が見えなかったり、説明文が読みづらかったりします。遊園地に行くと、身長制限により乗れないアトラクションがあることも悲しいです」と星来さんは語ります。
身長が低いことの強みについて「人に覚えてもらいやすいことだと思います。日常生活のなかでも、大学で関わりの少ない先生が『何かできることはないか』と声をかけてくださったり、10年以上会っていなかった友達が私に気づいて話しかけてくれたりします。一度出会っただけでも覚えやすいこの容姿を、人前で活動をするときに活かしたいと思っています。SNSやメディアで私を見て、低身長症の存在を知っていただき、どこかで低身長症の方を見かけたときに、普通に受け入れて接してもらいたいです」と、身長が低いことにも星来さんはメリットがあると感じているようです。
同じ疾患がある人と交流することがあった星来さん。同じ疾患でも性格や個性は人それぞれだということに、改めて気づかされたといいます。
2型コラーゲン異常症は、国内の患者数が約1000~1500人と推定される希少疾患です。「私は大学生になるころまで、同じ障がいの方との交流がありませんでした。しかし、2型コラーゲン異常症の患者会に積極的に参加し、役員を務めるようになると、同じ障がいがある人と関わる機会が増えました。当事者や保護者の話を聞くうちに、同じ障がいでも、それぞれ考え方は違うということに気づかされました。SNSで自身の障がいを発信する上で、同じ障がいの人は中身も似ていると誤解されないように、注意する必要があると思っています」と、同じ疾患がある人と関わることでそれぞれの個性を確認できたようです。
SNSの発信では、多くの方に自分の姿や考えを伝えられていることにとても驚いている星来さん。初めは同じ疾患がある人や知人による閲覧が多かったそう。しかし、最近は違う疾患がある人やない人にも見てもらう機会が増えたのだとか。
SNSを通し、もっと活動の場を広げ多くの人に疾患や障がいを身近に感じてほしいという思いが強くなっている星来さん。寄せられるコメントは、活動へのモチベーションに大きくつながっています。
今後は、活動を通して疾患がある人も、障がいがある部分以外は健常者と同じだということを伝えていきたいという星来さん。
「社会にはまだ、障がい者に対してどう接したらいいかわからないと感じている人もいると思います。そんな人たちに、障がいがない健常の部分、つまり普通の生活を楽しむ様子を見せることで、障がい者に出会ったときに必要以上に身構えず、自然に受け入れられるようになって欲しいです。目標は、モデルとして、メディアや講演会などを通じて、自分のありのままの姿を伝えることです。また、保育学を学ぶ者として、子どもや保育者に対する発信にも力を入れていきたいです。それは、幼いころから障がい者が生活のなかにいる環境で育つと、自然とインクルーシブな考え方が身につくと考えているからです。そのようにして、子どもたちの価値観をアップデートすることは、数十年後の社会全体の考え方を変えることにつながると信じています」
多方面での星来さんの活躍が期待されます。
【引用】
『「指定難病を目指した2型コラーゲン異常症の疾患概念と診断基準の確立」に関する研究』:https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/download_pdf/2015/201510106A.pdf
『2 型コラーゲン異常症の遺伝子変異と症状に関する研究』:https://mhlw-grants.niph.go.jp/system/files/report_pdf/202011024A-buntan.pdf
ほ・とせなNEWS編集部
