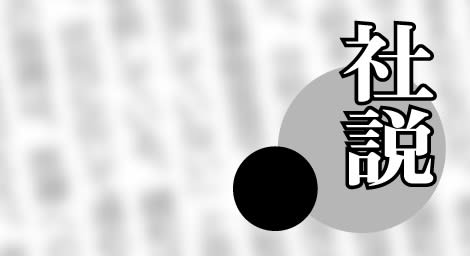
物価高と相まって、とりわけ年金暮らしの高齢者にとって負担は重荷だろう。
65歳以上の人が本年度から支払う介護保険料が、全国平均で月額6225円となり、過去最高を更新した。3年に1度の見直しで、半数近くの自治体が引き上げた。
高齢者の増加でサービスの需要が増しただけではない。深刻な人手不足が続く介護職員の賃上げに充てるため、公定価格の「介護報酬」を増額改定したことも影響した。
介護保険制度の財源は国と自治体の公費が50%、残り50%を40歳以上が支払う保険料で賄う。改定の議論で、サービス利用時の自己負担が2割の人の範囲を拡大するなど給付と負担の見直し案を検討したが、大半は先送りされた。
制度が始まった2000年度と比べ、保険料は2・1倍に膨らんだ。手をこまねくうちに、ただ上昇の一途をたどったように映る。
高齢者の人口はこれからまだ増え、40年にピークを迎える。介護職員の賃上げは、もはや避けられない。制度を根本的に見直さなければならない時に来ている。
増える負担をどう分かち合うか、政府は財源問題から逃げてはならない。利用料の2割負担の人を増やす案は入り口に過ぎない。一定の所得や資産がある人を対象に相応の負担を求める検討が必要だ。保険料の支払い開始年齢の引き下げや、公費を増やす可否も議論せねばならない。
負担の程度は、介護サービスをどの水準で維持するかで変わってくる。高齢者だけでなく、介護を担う家族を支える制度でもある。現役世代の介護離職や、子どもや孫の「ヤングケアラー」の顕在化は喫緊の社会課題となった。負担を抑えたいばかりに、必要以上にサービスを切り下げては本末転倒だ。住民目線での議論が欠かせない。
保険料の地域差が大きい背景にも目を向けたい。介護保険制度は市区町村が保険者であり、地域の特性に合わせた運用が求められる。一概に高いから問題というわけでなく、負担に見合うサービスの質や量なのか、住民に納得感があるかが肝心である。
今回の改定で最高額は大阪市の9249円だった。1人暮らしの高齢者が多く、訪問介護などのサービス利用が増えたという。所得が低い世帯の割合が高いのも要因だ。超高齢社会で格差の拡大も進む中、どの自治体でも起こり得る未来像といえるだろう。
逆に3千円台の自治体は、体操教室など介護予防に力を入れ、高齢者の働く場を充実させた地域が目立つ。健康寿命を延ばす地道な対策が、いかに重要かを物語る。
広島県内23市町でも6718~4828円と差が出た。認知症や、要介護度の上がる後期高齢者の増加に備えたサービス充実のために上げた市町もあれば、見込みより利用が少なく下げた市町もある。
なぜこの額になったのかを自治体は住民に丁寧に説明すべきだ。制度が持続可能なのか見通しの提示も要る。制度の根本議論に向けた土台として、実態をまず共有したい。
