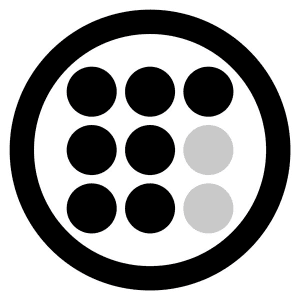遊撃守備の達人・元阪神・久慈照嘉さんが力説「キャッチボールが全て」
内野守備の名手からの“金言”に、小学生たちがじっと耳を傾けた。1日に大阪・堺市で開催された「第5回くら寿司・トーナメント2024 第18回学童軟式野球全国大会ポップアスリートカップ星野仙一旗争奪」の開会式後に、キャッチボールクラシックの全国出場権をかけた予選が行われ、元阪神、中日の久慈照嘉さんが参加者に向けて要点を伝授。中学生以降も試合に出られる選手になるために、「キャッチボールを大事にしてほしい」と力説した。
キャッチボールクラシックとは、1チーム9選手が7メートル間隔でキャッチボールを行い、2分間で何回捕球できたかを競うもの。捕球・送球の正確性やスピードはもちろん、仲間がミスをした時の素早いフォローも要求される。12月に東大阪市で実施される全国大会への切符をかけて、この日は16チームが頂点を競った。
競技に入る前、「くら寿司トーナメントポップアスリートカップ2024」の大会シニアディレクターを務める久慈さんが、小学生たちの前で「大事なポイント」として語ったのが、捕球の際のグラブをつけていない手(右投げなら右手)の位置だ。
「常にグラブの近くにあることが大事。グラブをはめた手だけで捕りにいく子がいるけれど、それだと素早く(投げる方の手に)握り返せない。(極端に言えば)突き指をするくらい、グラブの近くに置くようにしてください」
現役時代にショート守備の達人として鳴らした久慈さんは、こう語りながら子どもたちの前で実演。普段から手の位置、握りかえの素早さを意識して練習をしていれば、「キャッチボールクラシック」のようにスピードを求められても焦ることはなく、野球の試合でも素早くアウトを取れて勝利につながると付け加えた。
この日優勝したのは、2015年に全日本学童大会マクドナルド・トーナメントに出場経験もある奈良・磐城デンジャーズ。吉川佑一監督に聞くと、練習で意識させていた1つが、あいている手の使い方だという。「胸の近くで捕ることと、(右投げならば)右手を添えること。あとは、できる子は(ノーステップで)体重移動を使って投げるように指導してきました」。この日は準決勝で105回、決勝では108回をマーク。「練習でも100回行ったのは1回だけ」と驚いていたが、名手・久慈さんのレクチャー効果もあったのかもしれない。

送球が逸れて来ても…できる限り体を寄せる「そこで頑張らないと」
グラブをはめた手だけで捕りに行かないためにも、「常にボールが来る正面に自分の体を入れる意識が大事」だと久慈さんは語る。「送球が逸れて来ても、できるだけ自分の体を寄せにいく。キャッチボールはそこで頑張らないと、というのが僕の中ではありますね」。それは守備において、どれだけ素早く打球の正面に入れるかという“身のこなし”にもつながる。
全国の逸材小学生が集まる“プロの登竜門”「NPB12球団ジュニアトーナメント」の選考でも、多くのジュニア監督が重視するのがキャッチボールだ。捕球・送球技術はもちろん、“身のこなし”の素早さがそこには表れるという。「キャッチボールが全てなんですよ。ダメな選手は目に残らないし、できている選手は『もう1回見てみよう』となります」と、指導者としても名伯楽の久慈さんは同意する。
キャッチボールの上手・下手は、その後の野球人生にも大きく関わるという。「中学生になってキャッチボールがきちんとできない選手は、絶対に試合に使ってもらえません。それを小学生のうちに指導者が口酸っぱく言えるかどうか。僕らの頃はキャッチボールだけで1時間ということもあったけれど、今の時代は短い時間の中で、目的をもってやらせることが大事です」と久慈氏。1球1球に意識をもって取り組む、今日の練習からでも取り入れられる名手のアドバイスだ。(高橋幸司 / Koji Takahashi)
・プロの“関心集める”逸材小学生への条件 野球上手でも…希少枠に「選びにくい」難点