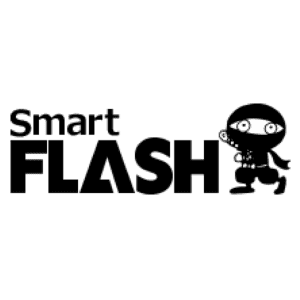画像はイメージです
組織不正についての最近の研究では、「多くの人は無関心なまま不正をする」と言われています。
それ以前の研究では、不正をしようとする人は大変注意深い人物で、不正をしようとする機会をうかがい、積極的に行うものと考えられていました。このような人物は、周囲にはなじまずに、孤立している場合も多いと考えられています。
このような風変わりな人物が不正を行うことから(あるいは、それが組織的に拡大して組織不正に至ると考えられたことから)、組織不正とはまれなものであり(めったに起こらないものであり)、常識とはかけ離れたものであると思われてきたのです。
しかし、私が研究において参考にしている社会学者のドナルド・パルマーは、このような見方では組織不正がここまでなくならない理由を説明できないとしています。そのため、パルマーは、これとは正反対の人物像を仮定し、むしろ不正には消極的な人物が不正を犯すことで、それが組織全体を含む組織不正へと拡大するのだと説明しています。
つまり、多くの人は不正に無関心なことが多く、不正をしようとも考えておらず、そのため積極的に不正をしようとする意思もない、というのです。このような人物は、不正をしようとする様子もないため、孤立しているどころか、むしろ周囲に溶け込んでいるものとされます。
パルマーが伝えたかったのは、私たちの身近なところにこそ不正を犯してしまう人がいるということであり、時には私たち自身もそうなりかねない、という警告になります。
■個人が「正しさ」を追求して起きる「社会的雪崩」
現代では、どのような状況においても「正しさ」が求められます。
しかし、個々人が「正しさ」を求めるがあまり、それが積み重なることによって、個人のみならず、組織や社会などの全体が沈んでいく現象があります。これを社会的雪崩(social avalanche)と呼んでみたいと思います。
私たちの日常生活(仕事生活)においても、周りを見渡した際にわざわざ自分がいざ不正をしようと態度や表情に表す人などいないように思います。
それよりも、結果的に不正行為者であるとされた人々やそれが組織的な不正につながってしまった事案などを見ていくと、「彼・彼女らはむしろ自分たちがやっていることが『正しい』と思って、これらをやったのではないか」と考えられることが多いように思えたのです。
自分がある種の「正しさ」をもっていれば、周囲の人々にもそれが伝わり、仮に根拠がない状態でも組織的に大きな仕事を行うことは簡単です。
多くの人は、そこで根拠があるかどうかを逐一確認することは少なく、その代表である個人が「正しさ」を担保していれば、それに乗っかって自分の仕事をこなそうとするものだと思います。
なぜなら、その根拠を確認する作業は別のコストを伴いますし、根拠を確かめてそれが根拠ありだと分かると徒労に終わることもあるからです。
このような個人の「正しさ」の追求は、いつしか個人、組織、社会というように次第に大きな動きとなっていくことにもつながります。それはまるで、少しずつ雪が降り積もることによって次第に大きな雪崩が起きるのと同じ現象と言えます。
個人の追求が個人を犠牲にするだけではなく、それが組織、社会へと少しずつ大きな雪崩を引き起こすことにつながるという点が、この社会的雪崩の怖さになります。
■いつ起きてもおかしくない「組織的雪崩」
最近の研究において分かってきたことは、「組織的雪崩」の代表例である組織の不祥事や不正は、外部環境との関係において生じることです。
外部環境では業界内における法規制や他社との競争、さらには株主を始めとしたステークホルダーからの要求が存在しています。この外部環境からの多様な要求に応答するために、組織は経営戦略を策定し、その戦略を実現するために組織を設計していきます。
さらに従業員は、組織から与えられた環境において、組織から要求される組織内行動を取ることによって要求に応答しようとするのです。つまり、要求自体は外部環境→組織→従業員へと行われる一方で、その対応は従業員→組織→外部環境へと行われるのです。
ただし、注意が必要なのは、従業員→組織への応答において従業員が暴走してしまうことです。組織→外部環境への応答においては、一見すると組織はきちんと対応しているように見えますが(表の正当化)、実際のところは従業員が自らの「正しさ」を信じ込んで組織を巻き込んでしまうことがありうるのです(裏の正当化)。
例えば、スルガ銀行の不正融資事件をこの枠組みで説明することができます。もともとスルガ銀行は、外部環境であるメガバンクや有力な地方銀行との競争に勝つために個人融資を拡大しており、それでも競争に勝つことができなかったため、最終的にはシェアハウス融資へと乗り出すことになりました。
この時スルガ銀行では、他行との競争に勝つことが絶対的になっているため、行員に対して過大な業績目標が与えられており、その目標達成のために行員がパワハラを行うなどの事案が複数確認されるようになっていったのです。
内部通報制度があったことも行員は認知していたものの、結局もみ消されたり、村八分のような状況になるとして内部通報を行わなかった実態があったとも報告されています。
この時に注意したいのは、行員はあくまで組織から与えられた業績目標を疑っておらず、それを追い求めることを「正しさ」として考えていたことだと思います。スルガ銀行において過度な業績目標が与えられていたことは今であればよく理解できますが、それが組織的に共有されてしまっている場合、なかなかそれを疑うことが難しくなります。
ですから、少なくともスルガ銀行では過度であっても業績目標を達成することが「正しさ」であるとして、それを追い求めることによってパワハラのように暴力的になることもいとわなかったのだと考えられます。
そうした「正しさ」が個人によって追求された結果、他の個人にも伝播していき、組織的雪崩が起きてしまったのです。
※
以上、中原翔氏の新刊『組織不正はいつも正しい ソーシャル・アバランチを防ぐには』(光文社新書)をもとに再構成しました。組織不正を行わない方が得策にもかかわらず、なぜ組織不正に手を染めてしまう企業が出てくるのか、その理由を考察します。
●『組織不正はいつも正しい』詳細はこちら