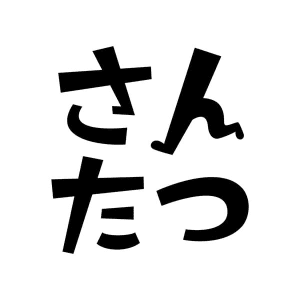広島に行ったんですよ。ちょっと前に数日かけて県内いろいろな場所へ行きました。昼間の取材で行ったのですが、ある夜、少しだけ時間があったので繰り出しましたよ、もちろん。呉の街での「2時間だけのバカンス」。
営業再開したという呉のグランドキャバレーへ
呉は言わずと知れた軍都ですね。海軍工廠のあったころは戦艦大和を建造し、戦後も造船の街としてにぎわってきました。大規模工場のあるところ、盛り場あり。汗を流して働いた男たちを癒やす歓楽地もまた相当の規模だったようです。

まずは、一軒だけ残ると聞いていたグランドキャバレーへ足を向けました。なんでも、一度廃業されたあと、どなたかが引き継いで営業再開しているそう。側まで近づくと、闇に浮かぶ赤いネオン管のギラつきが目の奥を刺してきます。脳内の血流がいっきによくなってきました。さて早速ドアに手をかけますと、
開かない——。
残念ながらふたたびの閉業。吹き抜けの店内や、かつて生バンドが演奏し、ダンスをしたフロアを見てみたかったですが、叶いません。あとから少し調べましたら、最後のころは、フィリピンパブに近い業態だったようです。
キャバレーは大掛かりなんですよね。風営法の上でも他の業態とは一線を画した設備が求められていました。もう東京にも一軒もありませんし、地方都市で存続するのは相当大変だったのだろうと思います。
大風呂敷の歓楽装置を維持できるほど遊客の厚みがなくなってきているわけです。これは大都市の中心市街地以外は、ほとんどどこでも起きている現象です。複数街区にわたって飲み屋の建物が並び、そこが大きな歓楽街だったことは分かるものの、今や空き物件だらけでぐっと小規模になってしまった街をずいぶんと見てきました。寂しいですが、仕方がありません。
旅の酒の醍醐味
無人のまま、音もなく、ネオンだけを輝かせる元キャバレーを後にし、若干しょんぼりしながら歩いていると、ふと目に付いたのが、「スタンド」を掲げた飲み屋さんが呉には多いこと。



雑居ビルに袖看板を出して、上階に小さなコマが並ぶ形態ですし、どの店の看板のデザインテイストをみても、業態はスナックに違いないと踏んで、一軒に入ってみることにしました。
「こんばんは〜」
大ベテランのママの店でした。
「いらっしゃ〜い」
おしぼりを受け取って、中年男性の悪癖・着席後即顔ふきふきをしながらシステムをお聞きすると、時間制でショット(ボトルおろさず一杯ずつ)でも飲めるとのこと。やはり、ふつうにスナックです。

ハウスボトルのリザーブで水割りを作ってもらいました。昭和の酒場で長年飲まれてきたこの銘柄も、最近はめっきり見かけなくなりました。さて燃料をグングン補給し、調子が出てきたところで『男と女のハシゴ酒』だったか『居酒屋』だったかをデュエットしてから、ママとゆっくり話し込みます。
初恋の話。
「ハタチじゃ。遅いじゃろう〜」
子供に厳格ながら夜遊びを好んだお父さんの話。
「昭和の生まれじゃから。父親がこわかったけん。鞭でたたきよる。自分はそのくせに遊ぶけん。男の人が遊びよるのは、病気じゃわいね」
昭和と今の差異、人のサガ、そういったものをどの地であっても思い知りながら酒を飲むのが常ですが、土地の言葉、響きを感じられるのも旅の酒の醍醐味です。

呉に「スタンド」を掲げる店が多い理由とは?
そうそう、疑問をママにぶつけてみました。明らかにスナック業態でも、このあたりではスタンドとかスタンドバーというのですね?
「呉は、食べ物出すのがスナックじゃから。酒はスタンド。バーは女の子がつく」
これはちょっと感動しました。盛り場の歴史的な話をします。
戦後、洋風にしつらえた飲み屋さん(主にホステスを配置している)は、バーとか、スタンドを名乗るところがかなりありました。相当遅い時間まで店を開けるところも多かったといいます。
これが昭和39年の東京五輪のころ、海外から人が大勢来ますから、風紀紊乱をきらう当局から、だいぶ圧迫を受けることになって、夜通しホステスさんを置いて酒を飲ますのはいかん、飯を食う食堂ならまあいいよ、ということになり、苦肉の策として生まれた名が、「スナック」だったと言われています。
アメリカあたりから入ってきた新しい名前で、軽食を食べられる店、というテイで、実際は社交飲食店をやったわけです。手入れ対策のために、誰も手をつけないサンドイッチやおにぎりだったりを申し訳程度に置いていた、という話も聞いたことがあります。
つまり呉の飲み屋さんは、その名称変革の波にのまれず、戦後以来の古形の名称のまま、現在に至っているのが分かりました。実質としては、現在ではママのいうような差異はないらしく、まったくのスナックのようです。
後日、広島出身の人に聞くと、「スタンド」「スタンドバー」を名乗るスナック業態店は、呉に限らず県内では結構見かける、とのことでした。
と、これはわかりやすい例ですが、全国あちこちに古形のまま変化していない盛り場の習俗というものは多々あります。
〈いいかい学生さん、盛り場をな、盛り場を飲んで歩きなよ〉
と私などは言いたくなってしまうくらい、新しい世代の民俗学者や、文化人類学者に追っていただきたい奥行きを持つ場所が、盛り場です。
プライベートとパブリックの狭間でたゆたう
帰り際、ママさんが私を見送りながら、ほほえみました。
「今度来たらゆっくりボトル入れて飲むのもいいよ」
はい、ぜひとも。3人くらいで来ればリザーブ1本くらいは空きますね!
そういえばこのボトルキープの風習、外国にもあるのですかね。私にはわかりませんが、自分で注文したボトルを何回も店へ通って減らしていく――これは考えてみれば面白いシステムです。
私物を、他人のなかに置く、というふうにも捉えられます。
プライベートとパブリックの狭間でたゆたってみる、ゆらゆらゆらぐ自分自身を置くのを楽しむ遊び、と言い換えることもできると思います。そんな場がスナックです。
これには他者に配慮しながら自分の欲望を追う、他人に甘ったれない、ゆらがない理性が必要とされると思います。こうした酒の飲み方そのものの習俗、これも見落とさないほうがいいと思います。
昔、「飲み屋街で大人を磨く」みたいな言辞には、キザったらしいなぁ〜と感じたものですが、案外、正しいように今では思っています。
文=フリート横田
フリート横田
文筆家、路地徘徊家
戦後~高度成長期の古老の昔話を求めて街を徘徊。昭和や盛り場にまつわるエッセイやコラムを雑誌やウェブメディアで連載。近著は『横丁の戦後史』(中央公論新社)。現在、新刊を執筆中。