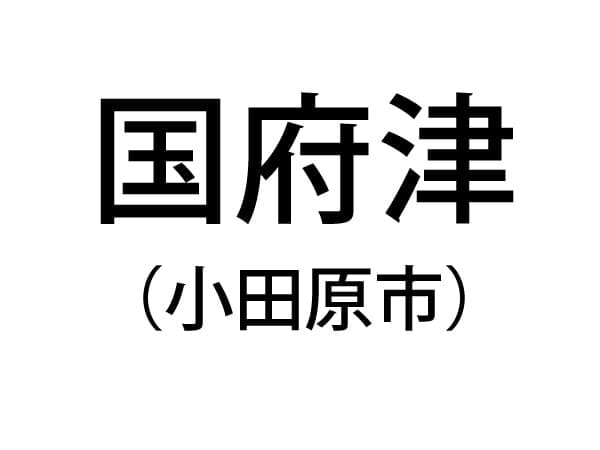
地元ではみんな知っているけど、それ以外の人からは、なんて読むか分からない地名ってありますよね?
そんな地名を探して、クイズにします!
神奈川県小田原市にある地名「国府津」は何と読む?
神奈川県小田原市にあるまちの名前です。同市の東部に位置しています。
地図を見ると、まちの様相は東と西では違うようです。東側には丘陵が連なっていて、かつては別荘地として知られていたとか。一方、西側の低地には市街地が広がっています。
その市街地を、南北に突っ切るようにして神奈川県道が通っています。森戸川に沿って県道を北へ進むと、国道271号線と交差。反対の南へ進むと、西湘バイパス(国道1号線の迂回道路)の国府津インターチェンジに接続します。
西湘バイパスと並行して走るのは、JR東日本の東海道本線です。停車駅のひとつ、国府津駅は、まちの最寄り駅。東海道本線で最初に駅弁が売られた駅として、またJR東海の御殿場線も乗り入れるJRの境界駅として有名です。

そんな国府津駅は、ホームの上から見えるくらい、海の近くにあります。まさに駅の目の前、西湘バイパスの直下に延びる国府津海岸は、釣り人に好まれる釣り場。理由はアクセスの良さと、さまざまな種類の魚が狙えるからだそうです。
国府津海岸からのぞむ相模湾は、いわし類、さば類、かつお類、ぶり類、あじ類などの魚がいる豊かな海。彼らの餌となる小魚を育むのは、海中に漂うプランクトンです。
プランクトンの存在は海の環境変化をとらえるのにも重要ですが、実態を明らかにするには、沖に出て深海まで潜って調べる必要があります。相模湾の国府津沖は、岸から3㎞ほどの地点で水深が約550mという地形のため、調査にうってつけだそうです。
陸の近くにこれほど深い海があるところは、世界的にみても珍しいのだとか。水産技術センター相模湾試験場の調査船「ほうじょう」による国府津沖の調査は、2020(令和2)年7月から続けられています。
リビングネットワーク「さかなをたべよう!」キャンペーン
https://mrs.living.jp/yokohama/osakana
さて、正解は?
そんな「国府津」の読み方ですが、正解は・・・
「こうづ」でした!
その由来は?
地名に詳しい本によると、「国府津」とは、相模国(さがみのくに)の「国府」に通じる「津(=港)」がつくられた場所であることから付けられた名だそうです。
奈良時代から平安時代にかけて、国は律令制度で治められていました。「国府」とは、その政務を執り行う施設が置かれた都市のこと。「こくふ」のほか、「こう/こふ」とも読むそうです。
参考:神奈川県ホームページ、村石利夫著「おもしろ地名・駅名歩き事典」(みやび出版)
皆さんは、正しく読めましたか? 機会があれば、ぜひ散策に訪れてみてください。
