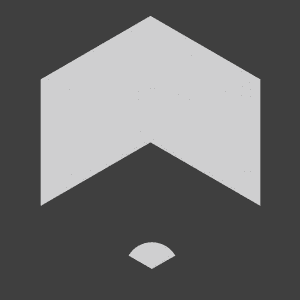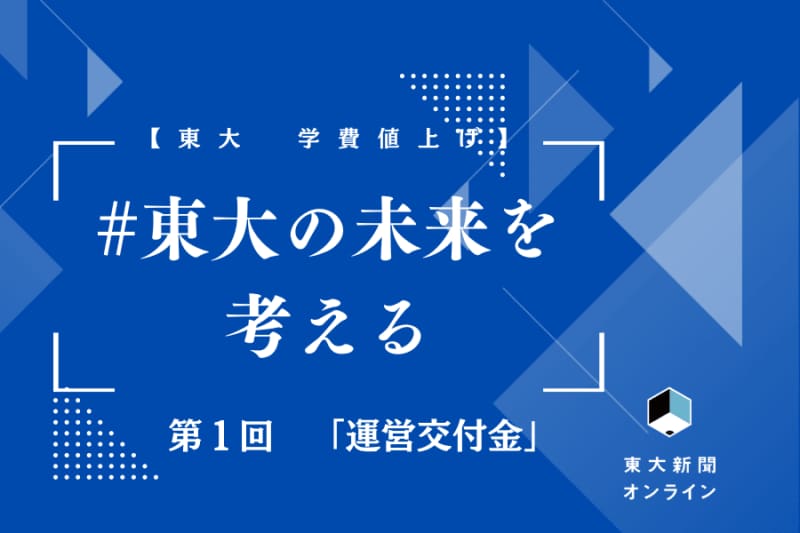
東大は5月16日、授業料改定を検討していることを発表した。素案では、年間の授業料を現行の約53万円から約64万円に引き上げるとされている。議論が拙速で不十分だという一部構成員からの批判に加え、他の国立大学の構成員からは、授業料値上げの動きの全国的な波及を不安視する声も聞かれる。本連載では、東大の経営や国の文教政策に関するキーワードを通して学費問題を深掘りする。今回は「運営費交付金」について考える。
運営費交付金は、文部科学省の予算から各国立大学法人に経費として財政措置され、人件費をはじめ教育・研究の基盤をなす業務に用いられる。総交付額は2004年の国立大学法人化以来減少を続け、現在は約1兆円前後で底を打つ。一方で各大学の支出は、事業拡大や光熱費・物価の高騰により増加傾向が続く。経費不足を補うため、各大学は寄付の呼び掛けや大学債発行などによる独自予算の獲得を求められてきた。
東大は昨年9月、22年度の経常損失が約50億円となったと公表。要因として、光熱費や物価の高騰で経常費用が上昇した一方、経常収益が大きく上昇しなかったことを挙げた。経常費用は約100億円増と大幅に上昇した一方、収益は前年比約20億円増の上昇に終わった。
東大の収益は、運営費交付金の他に国からの補助金、寄付金や共同研究などの外部資金、学費や入学料などの学生納付金などからなる。22年度は、国費と外部資金がそれぞれ収益の約35パーセント、学生納付金が約6パーセントだった。ある関係者によると教授会では、授業料値上げの理由の一つとして運営費交付金が増えないことが挙げられたという。しかし、授業料の2割引き上げによる増収は単純計算で全体の約1.2パーセントで、運営費交付金の下げ止まり分の補填とはなり難い。
実際に2010年に東大が開いた説明会で、前田正史理事(当時)は財政の悪化を授業料引き上げだけで賄うことはできないと述べている。同説明会で濱田純一総長(当時)は、授業料の問題と高等教育の在り方の関係に言及し、単なる財政不振を理由とする値上げではなく「授業料免除、奨学金とセットにして、大きな枠組みの中で考えたい」と答えた。
総長対話の1週間前をめどに、申請者には資料が共有される。値上げが全学構成員に受け入れられるには、総長対話を含め、財政状況の解説に留まらない十分な説明と議論が必要だろう。
東京大学新聞社は多様なステークホルダーの声を発信し、日本の大学の未来を考える助けになることを願っています。東大内外問わず皆様の意見をお聞かせください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRlELQPbDDk9PbncP2DXEalxCBxnGv4cC4OqQTqU-1CZv0Iw/viewform
GoogleフォームのQRコードはこちら
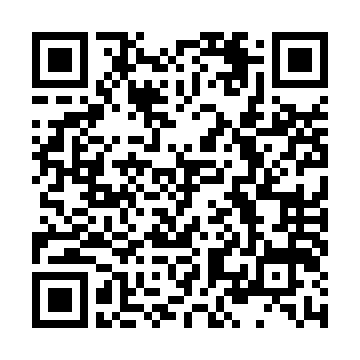
【学費問題】東大新聞オンライン掲載記事のまとめページはこちら(随時更新)
The post 【連載 東大の未来を考える】増額されない「運営費交付金」強いられる自主財源の拡大 first appeared on 東大新聞オンライン.
【記事修正】2024年6月8日午前12時3分 最終段落の「総長交渉」を「総長対話」に修正しました。