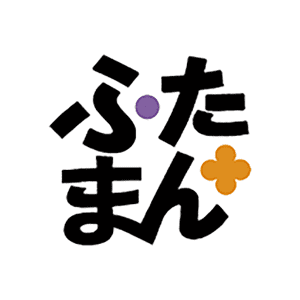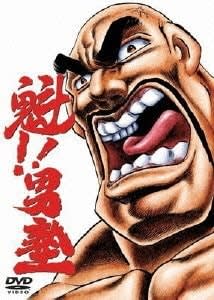
宮下あきら氏による人気漫画『魁!!男塾』は、1985年から1991年まで『週刊少年ジャンプ』(集英社)にて連載された作品だ。本作は過激なスパルタ教育をおこなう「男塾」を舞台にしたバトル漫画で、過激で有名なシーンもたくさんある。そして、そのような男塾の名物シーンは、本作に登場する民明書房をはじめとした出版社が刊行する“謎の書籍”によって、由来が紹介されていることが多いのだ。
昭和の時代、これら“架空の書籍”に書かれていたことを鵜呑みにし、これらの事柄が本当にあるものだと信じた読者も多かっただろう。今回はそんな男塾に登場する謎の書籍で紹介された、あまりにもインパクトのある伝説やイベントを紹介したい。
■男塾といえばこれ…!!「万人橋」
『魁!!男塾』を読んだことのない人でも、人と人がつながってできたこの「万人橋」ならご存じの人も多いのではないだろうか。
万人橋はコミックス7巻に掲載されている「男と男の掛橋の巻」で登場する。
大威𢸍八連制覇という男塾の格闘行事で、主人公・剣桃太郎たち一行は第二闘門へと向かう。しかし長城が崩落しており、先に進むことができない。そこに現れたのが、戦いを見守る田沢慎一郎や松尾鯛雄たち一号生メンバーだ。
彼らは数十人にも渡って高い肩車を組み上げ、そのまま向こう側の谷へダイブ。見事、“人の橋”を完成させ、桃太郎たちはその橋のおかげで長城を渡ることができたのである。
この万人橋は、“中津川大観著・時源出版刊『戦場にかける橋』”より、ざっと次のように紹介されていた。
“戦国時代、武田信玄と松山勝善の合戦の折、窮地の松山勝善を助けるべく楠木清久は援軍をひきいてむかった。しかし、途中にある雛谷の橋は落とされていたため、中国の兵法書にヒントを得て人橋をかけ、谷を渡った。このとき人橋となった者は味方の兵を渡しきったあと、ことごとく力つきて谷に落ちたという”。
武田信玄など歴史上の人物が出てきたら、本当に万人橋はあったと信じてしまいそうだ。しかし松山や楠木なんていう人物は、歴史上そもそも存在しない。リアルさとウソを織り交ぜて作られた『戦場にかける橋』。本作に登場する万人橋は、まさに史実よりインパクトの残る漫画界の事実として残っている。
■仲間のために自らの胸に入れ墨を…「血闘援」
『魁!!男塾』では、ちょくちょく刺青を入れるシーンが登場する。なかでもインパクトがあるのが、仲間のために自らの胸に刀で刺青を入れた「血闘援」だ。
大威𢸍八連制覇の第二戦でタッグを組んだのは、富樫源治&飛燕のコンビ。相手は当時悪役だった独眼鉄&センクウだ。最初に飛燕が独眼鉄と戦い、首を絞められピンチに陥る。そこで富樫は自らの胸に「闘」の刺青を彫り、飛燕を応援して復活させるのだ。
この血闘援は、かの有名な民明書房刊行の『武士魂』にて次のように紹介されている。
“江戸時代、御前試合などで仲間を応援する際、胸に「闘」の字を刻み必勝を祈願する応援の至極である。その胸の傷字は一生残る”。
飛燕がピンチのとき、胸に闘の字を刻んだ富樫。18画にも及ぶ複雑な漢字を、鏡も見ずに自分の胸に一瞬で彫るのはスゴい。しかも飛燕は独眼鉄に首を絞められた状態で、鉄棒の大車輪のようにグルグルと回されている状態だ。そんな時に富樫の血闘援を見て「頑張らなきゃ!」と奮起し、復活するのはちょっと面白い。
ちなみに『武士魂』では生涯傷跡が残るとされているが、その後手当をされたのか復活した富樫の胸に「闘」の字はなかった……。
■仲間のために20km遠方からエール「大鐘音」
『魁!!男塾』には数々の“男塾名物”という伝統がある。そのうちの1つが遠く離れた仲間にエールを送る「大鐘音」だ。
驚邏大四凶殺で、富樫が飛燕との戦いで苦戦していることを知った一号生の仲間たち。富士五合目で戦う富樫に向け、20km離れた場所から「フレーフレー富樫ーっ!!」と大声援を送ったところ、意識を失っていた富樫はその声を聞いて復活するのである。
この大鐘音も民明書房の『戦国武将考察』で紹介されており、次のように解説されている。
“武田信玄が上杉謙信と戦いで遠方にいる味方が苦戦に陥った際、味方の兵を励ますために一千騎の兵を並べ大声を出させ檄を送った。その距離はおよそ100キロ離れていたというから驚嘆だ”、と。
さらに余談まで掲載されており、“昭和15年野球のW大応援団のエールは神宮球場から池袋まで聞こえたという”とまで、紹介されている。
念のため、今回これを調べてみたのだが、残念ながらそうした事実はないようだ……。男塾に出てくる書籍には本当かウソか微妙な内容が描かれているため、読者は半信半疑のまま好奇心をもって物語を読み進めてしまうのである。
男塾には民明書房をはじめとした出版社が刊行する“謎の書籍”によって、数々の伝統がたくさん登場する。いずれも真実か否か絶妙な内容が紹介されているため、スマホのない時代にそれらの伝統を信じてしまう読者が多かったのは当然だろう。
あらためて見直すとツッコミどころ満載の書籍とも言えるが、そのような魅力も含めて男塾は多くのファンを惹きつけているのだ。