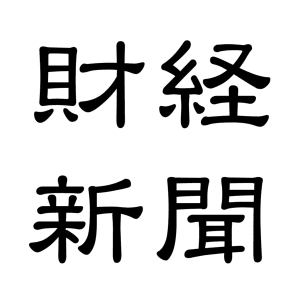国際宇宙ステーション(ISS)では、運搬コストや限られた在庫スペースの関係上、補給パーツを保管できる種類や数は限られる。万が一、機器故障でパーツ交換の必要が生じた場合、パーツ在庫がなければ、それを地球から取り寄せるとなるとかなり時間がかかることは容易に想像がつく。
このようなリスクの回避策として、ISSでは自前で必要な補給パーツを、3Dプリンターを用いて製作することが検討されている。
3Dプリンターが最初に発明されたのは1983年で、その5年後には市販が始まった。現在では家庭用3Dプリンターが、通販サイトで簡単に購入できる。安価なものならば、数万円程度で購入ができ、個人での活用も広がっている。
ISSでも2014年からプラスチックを原材料とした3Dプリンターが設置され、プラスチック製補給パーツ製作が始まっているという。
欧州宇宙機関(ESA)によれば、金属を原材料とする3DプリンターのISSへの搬入が、2024年1月に完了したという。既に様々なテストが開始され、動画もESAのサイト(https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2024/06/First_metal_3D_printing_on_Space_Station)で公開されている。
ISSでは、地球からの引力とISSが地球を周回する際に生ずる遠心力がつり合い、無重力あるいは非常に微小な重力環境下にある。またプラスチックと比べて金属は比重が重く、微小重力環境下では地球での3Dプリンターによるパーツ制作とは違った挙動が生じる可能性もあり、そのような影響について現在詳細な調査を実施している状況だ。
3Dプリンターの宇宙での活用はISSだけでなく、近い将来展開されるであろう月面基地建設においても積極的に行われる予定だ。既に月面での住宅建設を可能とする建設用3Dプリンターの開発や、月の資源を活用した基地建設技術の開発も始まっている。
日本でも3Dプリンターによる住宅建設を行う会社が出現し、工期2日、予算数百万円で家が建つという。宇宙でも短納期かつ低コストで必要なものを自前で確保する最強の武器として、3Dプリンターが活躍する日が間近に迫ってきている。