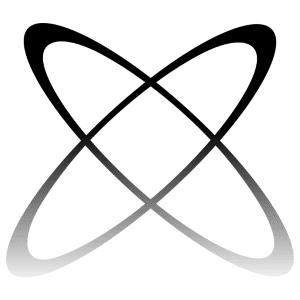2024年6月1日(土)、NPO法人国際教育eスポーツ連盟ネットワーク日本本部が主催する「第5回NASEF JAPAN eスポーツ国際教育サミット」が住友不動産秋葉原ビルにて開催されました。
今回は「ゲームで深める探究的な学習と学びに向かう力」と題して「PBL(Project Based Learning)」にフォーカスが当てられました。
eスポーツが子どもたちの成長に与える影響について、NASEF関係者や現役の教員などが実践例や経験談を通じて議論したようすをレポートします。
登壇者紹介&各人の主張
本サミットのオープニングセッション&パネルディスカッションには、NASEF USやNASEF JAPANの関係者、教育関係者が登壇しました。
今回の登壇者を、各人の発言内容とともに紹介します。
松原 昭博(NASEF JAPAN 理事長)

松原昭博氏による開会の辞では、本サミットの目的として「eスポーツを広めるのではなく、eスポーツを入り口に教育にいざなう」というポイントに焦点が当てられました。
eスポーツを活用して「子どもたちの可能性や興味の幅を広げる」「次世代人材を育成する」という趣旨の発言がありました。
坪山 義明(NASEF コミュニティ・リーダー )

坪山義明氏は、NASEF JAPANにおけるPBLの概要について説明がありました。
坪山氏によると、PBLとは「課題解決型学習」を意味し、従来の受動的な教育手法とは異なるものです。
PBLでは、生徒たちが自分の好きなことや興味をきっかけに能動的に学習できるメソッドを採用。生徒たちが自ら課題を見つけ、その課題に対する解決策を探求し、実践する過程で学びを深める学習であり、生徒たちは単に知識を受け取るだけでなく、実際に自分の手で問題を解決する経験を積むことができるとのことです。
またPBLは、興味と学びを結びつけることで、従来の学習方法では得られにくい実践的なスキルの習得を目指していると説明がありました。
Kevin T Brown(NASEF最高教育責任者)
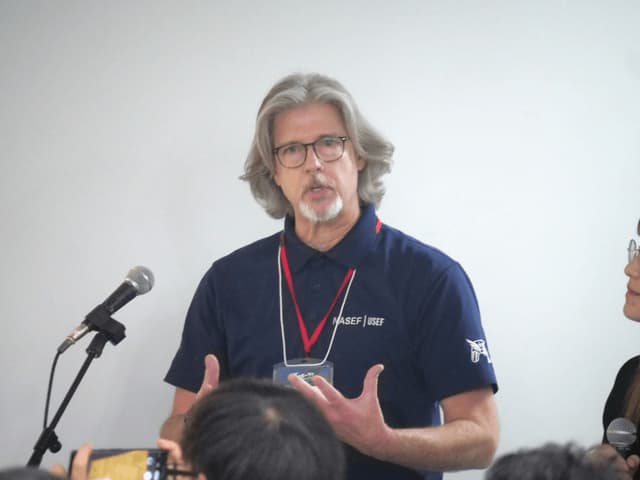
Kevin T Brown氏は、PBLの重要性について強調しました。
PBLにおいては、また教員は一歩引いて生徒を導き、生徒が自ら学び、失敗を通じて成長する機会を提供することが重要であると、Brown氏は話しました。
また、教科書の内容をただ学ぶのではなく、学んだことを生徒自身がどのように示すかに焦点を当てます。その過程を通して実践的なスキルを身につけ、最終的な学習成果を達成することを目指すようです。
PK Graff(NASEF コミュニティ・リーダー )

PK Graff氏は、教育を遊び場のように身近で楽しいものにすることを提案。5C(Connect, Commit, Create, Climb, Cookie)の理念に基づいて、eスポーツを通じた教育の重要性を強調しました。
Graff氏は、ゲームに対するネガティブなイメージに対抗するため、健康的かつ安全なゲームプレイを推進するためのリサーチを行っているとのこと。彼の「マインドフルゲーム」のアプローチでは、ゲームに入る前、プレイ中、そして終了後に自分の感情をコントロールする方法を指導しているようです。
この方法により、生徒たちはポジティブなマインドセットでゲームを楽しみ、達成感を得られたといいます。
義本 博司(元文部科学省事務次官)

義本博司氏は、教育におけるeスポーツの役割とその可能性について語りました。義本氏は、「教育は楽しいものでなければならない」と強調し、eスポーツが子供たちの学びの入り口として重要であると述べています。
eスポーツを通じて、生徒は自分の興味を発見し、チームで協力することで多様な視点を学びます。また、失敗を通じて成長する経験が重要であり、これがキャリア形成にもつながるとしています。
昨今、国内外で教育改革が進んでおり、日本でも課題解決型学習を取り入れ、生徒が主体的に学ぶことが求められています。eスポーツはこの新しい学習方法を支える有力なツールであり、学校や地域社会と連携して広めていくことが必要であると説明しました。
藏下 一成(修道中学校教頭)

藏下一成氏からは、eスポーツを教育に取り入れる意義とその可能性について説明がありました。修道中学校では部活動としてeスポーツチームを作り、大会に参加する予定があるとのこと。
授業では教育版『マインクラフト』を導入し、生徒の興味を引き出すことを意識。eスポーツが生徒のモチベーションを高め、学びを促進する有効な手段であると強調されました。また、eスポーツはゲームプレイだけでなく、様々な役割を通じて生徒が実践的なスキルを習得し、将来のキャリアに繋がると述べています。
加えて、eスポーツを通じた海外交流や、プログラミング教育の効果についても共有がありました。藏下氏は、社会的な理解を深めるための啓蒙活動と、行政のバックアップが必要であるとし、生徒の成長を見逃さないようにPBLを推進していく意欲を示しました。
板垣 聡美(立修館高等専修学校 情報教育担当)
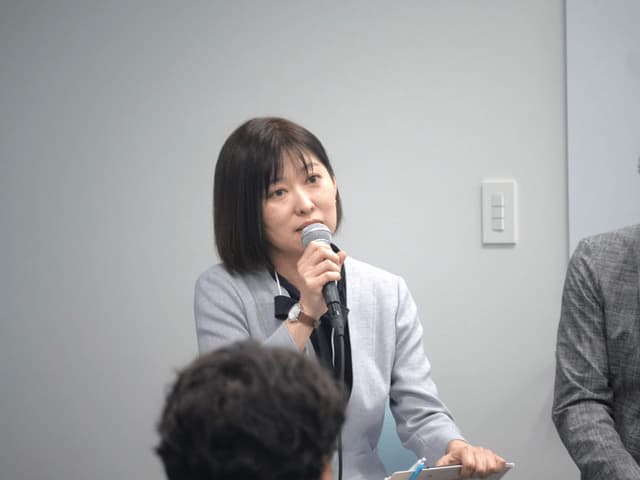
板垣聡美氏からは、eスポーツを教育に取り入れる意義と効果について説明がありました。4年前に立修館高等専修学校に設立されたeスポーツ部では、活動を通じてコミュニケーション能力が向上し、不登校の生徒たちが学校に行く動機付けにもなっていると述べました。
さらに、国際的な交流や英語力の向上にも寄与しているとのこと。板垣氏は、eスポーツを教育に取り入れることで、生徒たちが主体的に学び、社会とのつながりを深めることができると考えており、保護者の理解を得るための啓蒙活動の重要性についても触れていました。
注目の議題を3つピックアップ

筆者が特に注目した議題を3つピックアップします。
eスポーツは教育の第1段階「興味をもつ」をクリアしている
教育における最初のステップは、生徒たちに興味をもってもらい、学習意欲を引き出すことです。
Brown氏は「PBLが生徒たちの興味を引き出すための有効な手法である」と述べました。PBLでは、従来の受動的な学習方法とは異なり、生徒自身が興味をもつテーマを探求し、能動的に学ぶことが奨励されます。
NASEFでは、PBLをeスポーツや『マインクラフト』などの具体的なプロジェクトに落とし込み、生徒たちが自分の興味を起点に学びを深められるよう活動を行っています。
また、藏下氏は、修道中学校のeスポーツ部の事例を挙げ、生徒たちが自分の得意分野を発揮しながら学ぶことの重要性を説きました。eスポーツ部では、プレイヤーだけでなく、プレゼンテーションやイベント運営に興味をもつ生徒も活躍しています。このように、生徒たちは自分の興味を追求することで学びの幅を広げています。
板垣氏は「立修館高等専修学校でのeスポーツ部活動が、生徒たちのコミュニケーション能力や実践的なスキルを向上させる一助となっている」と述べました。生徒たちは興味を持つ活動に取り組むことで、学習意欲が高まり、成長を遂げているとのことです。
eスポーツとPBL(課題解決型学習)の親和性の高さ
昨今、eスポーツは単なる娯楽ではなく、強力な教育ツールとして活用できるということが多くの教育者によって示唆されています。PBLは、問題解決能力を養うために生徒が主体的に学ぶことを促し、eスポーツはこの手法を実践するための選択肢の1つとなり得ます。
また、eスポーツを通じて、生徒たちはチームワークや戦略的思考を学び、自分の役割を果たす中で問題解決力を身につけます。これはPBLの核心である「学びながら課題を解決する」プロセスを体現しているといえるでしょう。
eスポーツは、PBLの枠組みの中で生徒たちの学びを支える理想的な手段であり、生徒たちは興味を持つ活動を通じて、主体的に課題を解決し、実践的なスキルを身につけます。このアプローチにより、eスポーツは教育の中で重要な役割を果たし、生徒たちの学びをより深く、より充実したものにすることができます。
教育現場の現状「教職員の90%は『教育的効果があるとは思えない』と回答」
eスポーツが教育に与える影響について、板垣氏が立修館高等専修学校の教職員に対して実施した調査では、90%が「eスポーツに教育的効果があるとは思えない」と回答。消極的な回答が大多数になった一方、今後eスポーツに期待をするかという質問には、 80%の教師が「はい」と回答したとのことです。
この結果は「eスポーツが教育にどのように役立つか」を立証するための情報や実例が不十分であることに加え、「現状を変えたくない」という硬直化した教育現場の実態を明らかにしたように思えます。
板垣氏は「eスポーツが生徒たちのコミュニケーション能力や自己肯定感を向上させる一助となっている」と述べています。実際、eスポーツ部に参加することで、不登校経験のある生徒たちが学校に行く動機付けとなり、さらには大学進学にもつながる具体的な成果が出ているようです。このような実例が増えると、eスポーツが教育に与えるポジティブな影響が少しずつ認知されていくのかもしれません。
筆者の感想「課題解決型から課題発見型へ」

PBLは「課題解決型学習」と訳されることが多いですが、実態は生徒自身が課題を発見し、探求していく「課題発見型学習」であるといえます。
教師から与えられた課題をこなすのではなく、自らの興味や関心に基づいて主体的に学びを深めていく点が、PBLの本質であり、eスポーツと高い親和性があります。
ここでネックになるのが、現状の日本の教育者たちが「PBLを受けてきた世代」ではないということ。自分たちが受けてきていない教育を、子どもたちを相手に実践できるのか疑問符がつきます。日本のPBLがいっそう本領を発揮するのは、いまPBLを施された子どもたちが教育者の立場になったときなのかもしれません。
いずれにしても長期的な目線で取り組んでいくことになるのが、eスポーツによるPBLでしょう。本サミットのような教職員向けの勉強会が定期的に開催されることは、長期戦を視野に入れた「eスポーツ×PBL」において重要といえるでしょう。