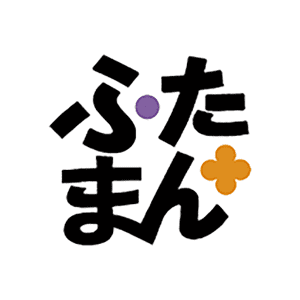連射機能を搭載したことでシューティングゲームやアクションゲームの攻略を助けてくれたハドソンによるコントローラー『ジョイカードmkII』をはじめ、ファミリーコンピュータの時代にはメジャー・マイナー問わず数多くの“周辺機器”が生まれた。
たとえば、1986年にバンダイ(現・バンダイナムコエンターテインメント)から発売された『ファミリートレーナー』は、足踏みやジャンプによって操作するマット型のコントローラーで、体感型ゲームの先駆けと言ってもよい周辺機器だ。ただ、騒音や床への衝撃は大きく、室内で使うことにためらったユーザーが多かったためか、対応ソフトは国内では10本と多くない。
とはいえ、この子どもたちの好奇心を強く刺激したであろう『ファミリートレーナー』は後に改良。2008年にWii用として発売され、全世界での販売本数は100万本を突破した。その好調ぶりを考えると、ファミコン当時としては未来を先取りしすぎていただけなのかもしれない。
テレビでゲームをするというだけではなく、本体につなげることで新たな可能性を提案してくれたレトロゲーム時代の周辺機器。今回は『ファミリートレーナー』を生んだ「バンダイ」が手掛けた、野心的すぎた周辺機器を見ていこう。
■おうちカラオケをファミコン時代に『カラオケスタジオ』
今となっては家でもカラオケ練習するのは簡単だが、ファミコン時代に「自宅でカラオケ」という夢を広げてくれたのが、1987年にバンダイから発売された『カラオケスタジオ』なる周辺機器だ。
これはファミコン本体にマイク付きの『カラオケスタジオ』を差し込むことで、画面に流れる曲にあわせて歌うことができるというもの。歌声判定システムがあり、「レッスン」「のどじまん」「スターたんじょう」「イントロあてゲーム」のモードを選べ、テレビでカラオケができるだけではなく、ファミコンならではのゲーム的な要素もある。
収録曲は、『一年生になったら』や『ジングルベル』といった低年齢層向けの童謡から、『光戦隊マスクマン』『ゲゲゲの鬼太郎』といったアニソン系の歌、また吉幾三さんの『雪國』、松田聖子さんの『赤いスイートピー』などのヒット曲まで、全15曲を収録。そして『カラオケスタジオ』背部のカセットを入れ替えることで曲を追加できる機能もあり、サザンオールスターズ『いとしのエリー』やヒロシ&キーボーの『3年目の浮気』などなど全40曲が追加された。
通常、ゲームのカセットを差し込むだけだったスロットに、マイクがついた本体を載せるというアイデア。今では家庭用ゲーム機でカラオケをすることは当たり前になっており、これもまさに“早すぎた”というべきバンダイの周辺機器のひとつだろう。
■バーコードで遊ぶことができる『データック』
ファミコン末期となる1992年12月29日にバンダイから発売された『データック』は、本体上部についたバーコードリーダーにバーコードを読み取らせて遊ぶことができる周辺機器。
ファミコンのカセット差し込み口にデータックを差し、このデータックに、データック対応ソフトを差して使うことになるので、かなり巨大な見た目になる。データックは灰色のため、どこかスーパーファミコンをイメージさせるのも、時代を先どっている感があっていい。
本体と同梱発売された『ドラゴンボールZ 激闘天下一武道会』をはじめ、『SDガンダム GUNDAM WARS』、『クレヨンしんちゃん “オラとポイポイ”』、『幽☆遊☆白書 爆闘暗黒武術会』などのデータック専用ソフトが発売された。一部タイトルを除いて、カードなどに印字されたバーコードを読み取らせれば、キャラやアイテムを入手することができる。
当時、子どもたちの間では、同じくバーコードを読み取らせて遊ぶ『バーコードバトラー』(1991年、エポック社)が大流行していたが、それを『ドラゴンボールZ』や『SDガンダム』のキャラクターでプレイできると考えれば、夢の膨らむ周辺機器だった。
また、雑誌『Vジャンプ』の特典としてデータック用のカードが付属するなど、ファミコンの枠組みを超える拡張性もあった。現在でいえば「追加コンテンツ」を先取りした感じだろうか。
ネットが発達して、コピーも作りやすい今では、バーコードによる特典配布は難しいところだが、当時としてはかなり野心的な周辺機器だったと言える。
■開発者とユーザーの味方になった 『スーファミターボ』
スーパーファミコン本体の発売以降、ソフトの価格は年々高騰していき、1万円を超えることも珍しくなくなっていった。その原因は、ソフトの大容量化とそれに伴う開発費の増加だと言われている。
そういった問題を受けて開発費を削減し、安価でスーファミソフトが発売できるようにした周辺機器が、1996年にバンダイから発売された『スーファミターボ』。
これは、スーファミのスロットに『スーファミターボ』本体を差し、さらにこの『スーファミターボ』に小型の専用カートリッジを差して遊ぶというもの。『スーファミターボ』本体に基本となるプログラムや文字フォントが入っており、ゲーム開発者はそれを利用することで、プログラミングの工数や容量を節約できるようになっている。そのため、開発費が安価となり、ソフトの定価も抑えられ、いずれの専用ソフトも3980円という値段で発売された。
また、『スーファミターボ』にスロットは2箇所用意されており、片方にゲームソフトを差し、もう片方に拡張ソフトを差して、追加のシナリオを遊んだり、友だちのカセットとのデータのやり取りができたりという拡張性もあった。
残念ながら売り上げが振るわなかったため、対応ソフトは少ない。とはいえ、現代でも問題となっている、ハードのスペックアップによるソフトの開発コスト増加に、いち早く着目し、実際に改善を計った『スーファミターボ』は、レトロゲーム時代の画期的な周辺機器と言えるだろう。
以上、バンダイの野心的な周辺機器を3つピックアップして紹介した。どれも知名度やセールスの面で苦戦したものばかりだが、そのアイデアと存在感は今の時代でも光っている。