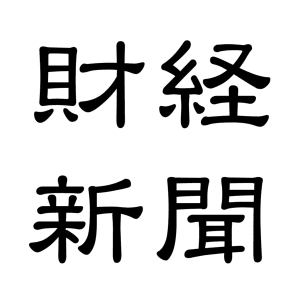葬儀・仏壇・墓のポータルサイトを運営、相続・介護と領域を拡げている鎌倉新書(東証プライム)から、『第6回お葬式に関する全国調査―アフターコロナで葬儀の規模は拡大、関東地方の冬季に火葬待ちの傾向あり』と題するリリースが届いた。2歳下の弟の急逝を体験したばかりの身としては、いささか複雑な心境ではあったが目を通した。
3月1日~4日に、22年3月~24年3月までに喪主(準ずる立場)を経験したことのある40歳以上の男女(有効回答数/以下、省く。2000件)を対象にしたネット調査の結果だという。こんな内容が記されていた。
(I)半数が家族葬を実施。コロナ渦を経て主流に台頭(50%で前回調査に続き最多)。一方、前回調査の結果との比較では家族葬は-5.7%、一般葬は+4.2%。新型コロナ感染症が第5類に移行し行動規制が緩和されたことにより、参列者が多い一般葬の割合が戻りつつあることが分かる結果となった。
ちなみにコロナ禍の2022年調査では家族葬55.7%/一般葬25.9%が、今回の調査ではそれぞれ50%/30.1%。また葬儀の平均価格費用は22年が110.7万円に対し、今回は118.5万円(基本料金75.7万円+飲食費20.7万円+返礼品費22.0万円)。
リリースでは「葬儀費用は葬儀の規模が大きいほど高額に、小さいほど安価となる。従い、一般葬が最も高額になり次いで家族葬・1日葬・直葬となる」と説明している。我が舎弟の葬儀は「通夜は行わず、告別式/火葬」の1日葬だった。
(II)葬儀までの日数は関東全体では「死去から3日以内:36.2%/4日以上7日以内:58.1%/8日以上:5.7%」に対し、関東地域でも冬場は「27.8%、54.2%、18.1%」。いずれにしても過半数の故人が火葬までに4日以上かかっている。
明確な論拠こそないが、いささか「資金」面での比較はどうかと思うが日数が経つほど遺族側の負担は重くなる。「遺体が腐敗するのを防ぐための安置室の冷房費用」が、その要因だ。また大方の火葬場では年末年始、そしていわゆる六曜の友引が休業となる。友引=休業は「友を引くから」というのが理由とか。弟の火葬も逝去から4日目に行われた。
リリースを読み最も興味をひかれたのは、コロナ感染症が第5類に移行したことで一般葬の割合が増える傾向にあることだった。義母は文字通り簡素な家族葬でおくった。父親は104歳、どうおくろうか・・・