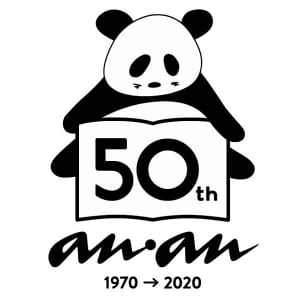子供の利益になっているのか? 熟考が必要。

離婚後も父母の双方が子供の親権を持つ「共同親権」の導入を含んだ、民法改正案が成立しました。1898年の明治民法施行以来の大きな変更になります。これまでは離婚後は単独親権が前提でした。最終的に母親が親権を得ることが圧倒的に多く、父親が子供に会わせてもらえないなどの問題が起きており、改正が求められていました。今後は、単独親権、共同親権のどちらかを選べ、合意できない場合や裁判離婚は家庭裁判所が判断します。
親権とは、子供の利益のために監護や教育、財産管理などをする権利であり、義務です。共同親権を選択すると、引っ越しや進学、手術を受けさせるかどうかなどを別れた夫婦で話し合わなければいけません。しかし、離婚理由が家庭内暴力の場合もあります。暴力から逃げるために住む場所も隠しているのに、暴力を振るう相手と連絡を取らなくてはならなくなるリスクもあり、法案に反対する声も上がっていました。
その家庭にとって共同親権が妥当なのかを裁定するのは家庭裁判所ですが、家裁の調停員も、家庭の実態に踏み込んで審査できる体制にありません。児童相談所や子ども家庭支援センターの職員の方に伺うと、虐待の相談件数は増え続けているが、児相の体制はあまり変わらず、どこまで踏み込んでいいかわからないと話していました。最終的には警察に届けることになりますが、子供と親を引き離して終わり。虐待の背景には貧困や働き方、孤立の問題が引き金になっていることが多いですが、根本的な解決にはならず、対症療法にしかならないのが現状です。
共同親権の論議も親の権利の話ばかりで、子供の権利がなおざりになってはいないでしょうか。どちらが親権を取るかも、子供が選べる環境を整備するべきでは? やはり、理想は「社会で子供を育てる」。どこに住んでいようとごはんを食べられて、教育を受けられ、安心して子供が暮らせる体制作りが必要だと思います。子ども食堂やフードバンクはその一例ですが、民間事業ベースで寄付によって運営されている脆弱なシステムです。“子供ど真ん中”の社会の実現には皆で取り組むことが大事なのではないかと思います。

ほり・じゅん ジャーナリスト。元NHKアナウンサー。市民ニュースサイト「8bitNews」代表。「GARDEN」CEO。報道・情報番組『堀潤モーニングFLAG』(TOKYO MX月~金曜7:00~8:30)が放送中。
※『anan』2024年6月12日号より。写真・小笠原真紀 イラスト・五月女ケイ子 文・黒瀬朋子
(by anan編集部)