
倉敷美観地区のシンボルのひとつである大原美術館で、新たな取り組みが始まりました。
加齢によって心身が老い衰え、社会とのつながりが減少した状態である「フレイル」を予防するためのプログラムです。
美術館と健康、どのようなつながりがあるのでしょうか。
大原美術館が主催するフレイルプログラムに参加して感じたことをレポートします。
大原美術館とは
大原美術館は1930年(昭和5年)に設立された、日本で最初の西洋美術中心の私立美術館です。
本館、分館、工芸・東洋館に分かれており、収蔵点数は約3,000件。
多くの場合、美術館では静かに鑑賞するのがマナーですが、大原美術館では「みんなのマイミュージアム」をスローガンに、作品を見て感じたことを共有する対話型鑑賞や院内学級の子どもたちを対象に出前講座など、多様な鑑賞に取り組んでいます。
フレイルとは
公益社団法人地域医療振興協会によると、フレイルとは以下のような状態を指すそうです。
加齢に伴って、筋力や認知機能が低下したり、閉じこもりがちになったりなど、
「体力や心身の活力が低下したり、社会との関わりが希薄化した状態」のことです。
フレイルは健康な状態と要支援・要介護状態の狭間の状態ですが、早めに気づいて日々の生活を見直すことで、何歳からでもフレイルを予防・改善できるそうです。
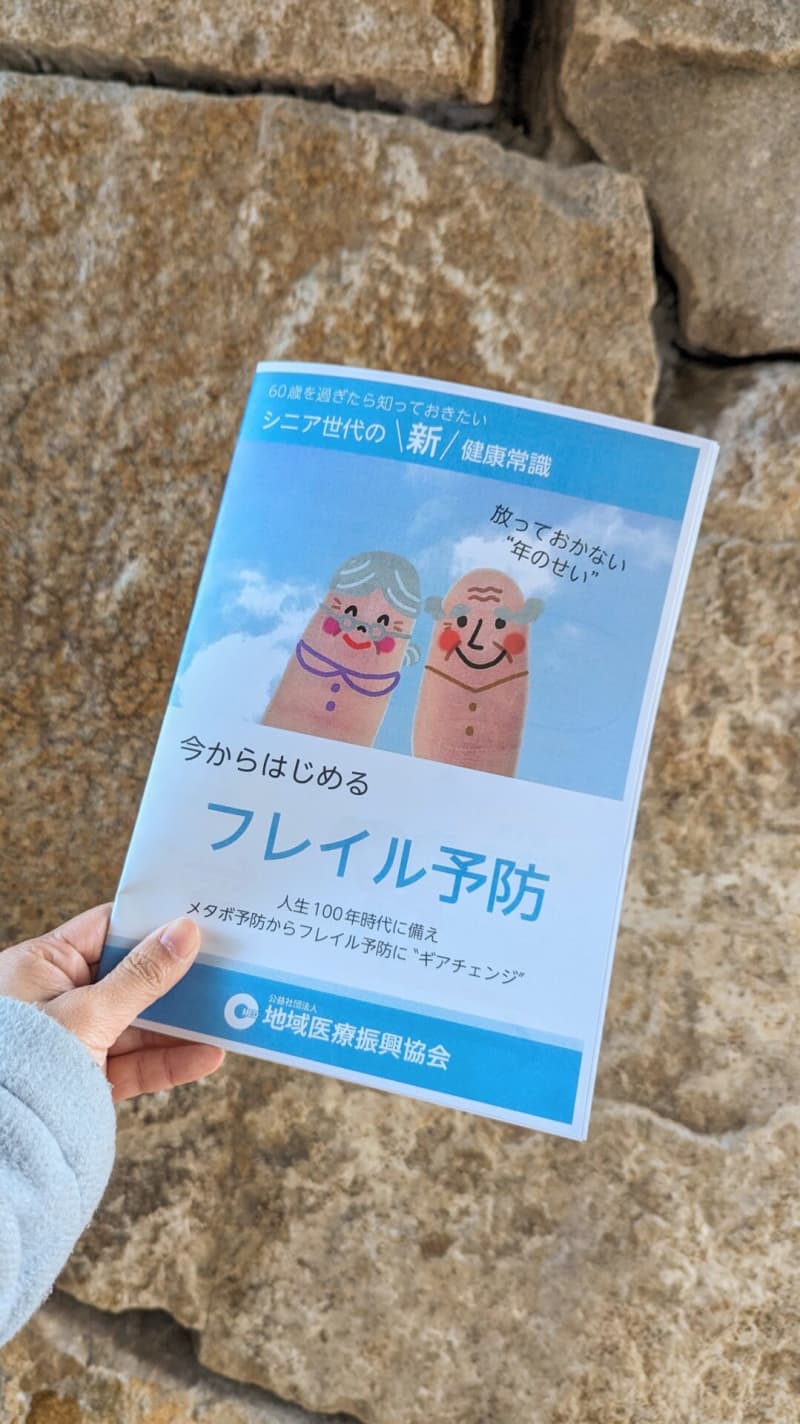
フレイル予防の三本柱は、以下のとおりです。
- 運動:身体を動かして筋力や歩行力を保つ
- 社会:地域社会との交流を保つ
- 栄養:しっかり食べて栄養状態を良好に保つ
大原美術館が取り組むフレイル予防プログラムとは
大原美術館は、大原美術館本館と工芸・東洋間を歩くだけで1,000歩程度歩ける施設。作品を鑑賞し、館内の階段を昇降することで運動になります。
また、作品鑑賞のポイントを決めて鑑賞したり対話型鑑賞に参加することで他の人と会話ができ社会参加につながります。
以上の背景から、公益社団法人地域医療振興協会の指導による研修を受けた大原美術館職員によるフレイルプログラムが、2024年2月24日(土)に実施されました。内容は以下のとおりです。
- 近隣散策(フレイル予防要素《運動》の実践)
※研修を終えた美術館職員による大原美術館の歴史・近隣の建築・おすすめの飲食店などを交えた案内 - レクチャー(フレイル予防要素《運動》《社会参加》《食》の説明)
- 本館展示室内にて対話型作品鑑賞(フレイル予防要素《社会参加》の実践)
「美術館で健康増進!」体験レポート
冬の晴れ間の昼下がり、週末ということも相まって集合場所の大原美術館前には多くの観光客が行き交っていました。
この日のプログラム参加者は15名。参加者以外にも報道関係者も集まっていて、本プログラムへの注目度が伺えます。

聴覚障がいのある私は事前に手話通訳の派遣をお願いしていたので、美術館職員の解説を手話で通訳してもらいながら参加しました。
美観地区散策の提案
大原美術館の前でフレイル予防プログラムの簡単な説明を受けると、さっそく大原美術館周辺の散策が始まります。
今回の散策ルート
大原美術館本館前→大原美術館分館前→倉敷国際ホテル前→若竹の園前→大原美術館本館
「新渓園は、入場無料の施設なので美観地区散策のついでにふらりと立ち寄れますね」

「倉敷国際ホテルと大原美術館分館は、浦辺鎮太郎(うらべ しずたろう)という同じ建築家によるデザインですよ。美観地区周辺には他にも浦辺による建築があるので探してみてくださいね」


「上を見上げてみてください。児島虎次郎記念館は狭い道に面していますが、鏡張りを取り入れることによって軽やかさを表現しているんですよ」

など、どのスポットも一つの場所をじっくり見るというよりは、散策のポイントを教えてもらう感覚で進行されました。
フレイル予防の提案
約1時間の散策を終えて、大原美術館本館に戻ってきました。
ここからは休憩を兼ねて、美術館職員からフレイル予防についての説明や、「美術館で健康増進!」の企画意図の紹介を受けます。

フレイル予防は、一度きりではなく継続することが大切なのだとか。
つまり「美術館で健康増進!」はあくまでもフレイル予防の提案。美観地区の歩きかたや美術館職員おすすめの食情報、対話型鑑賞を体験することで、フレイル予防のポイントを掴み、参加者それぞれが日々の生活でフレイル予防を実践することが大切なのだそうです。
近隣の散策も気持ち早めのテンポでしたが、そのおかげで気になったところはもう一度じっくりと、自分の足で回れそうな気がしてきます。

対話型鑑賞の提案
休憩を含めて30分ほどのレクチャーを終えると、最後は対話型鑑賞の体験です。
本館一階で対話型鑑賞についてレクチャーを受け、4~5人ほどの小グループに分かれます。

今回は参加者同士初めて会う人ばかりだったので、小グループで対話してもらうことにより安心して対話を楽しめます。まさに参加型の対話鑑賞でした。
私も手話通訳を介しながらのやり取りだったので、参加者がより近く通訳してもらいやすい環境で「その作品を自宅に持ち帰りたい?」といった質問にもじっくりと考えて答えられました。

私はイブニングツアーに続いて二度目の対話型鑑賞でしたが、大原美術館は常設展示が季節ごとに変化するほか、ともに対話する参加者や美術館職員によって見方が異なるので、何度体験しても新しい発見があります。
大原美術館は、大原美術館は、大原美術館本館と工芸・東洋間を歩くだけで1,000歩程度歩ける施設と説明を受けましたが、近隣の散策と大原美術館本館を歩いて、この時点で気づけば10,000歩近くも歩いていました。
おわりに
倉敷美観地区の中心にそびえ立ち、近隣に関連施設やゆかりのある施設が多くある大原美術館ならではの近隣散策に、対話型鑑賞。まさに、美観地区にある大原美術館ならではの取り組みだと感じました。
ボリューミーな内容で2時間では消化しきれないところもありましたが、レクチャーで「今回の、美術館で健康増進!はフレイル予防の体験。自分でフレイル予防をする際のヒントだと思ってください」と説明を受けて、美観地区や大原美術館を再訪する楽しみができました。
大原美術館周辺を散策して《運動》し、参加者同士・美術館職員と対話をしながら《社会参加》できる大原美術館のフレイル予防プログラム。
今回のフレイル予防プログラムを担当した美術館職員によると、今後は《食》のアプローチも視野に入れて周辺の飲食店と協力したいとのこと。
更なる発展が楽しみなプログラムです。
