昨今、「服の生地がペラペラになってきた」という声をよく聞く。多くの人は、アパレル側のコスト削減の結果とみる向きが多いが、実はそれほど単純な話ではない。社会、経済、業界慣習、そしてトレンドが複雑に絡み合った結果なのである。どういうことか?

女性の社会進出と服の「軽量化」の関係性
1kg=1000円の糸があったとする。ここでニットの目付(めつけ:重さのこと)が300グラム(肉厚で重いニット)だったものが200グラムになると、素材のコストは300円程度から200円程度に落とすことができる。原価で34%のコストダウンの実現である。このことから「昨今の原料高を吸収するために目付を軽くしているのだ」と言う向きがあり、それは正しいことではあるが、実はそれはいくつもある要素の1つに過ぎない。
ファッション衣料の原料が軽くなったのは、「トレンド」だからである。コストダウンは確かにそうなのだが、あくまでも、トレンドの結果として起きているだけだ。ニットであればスケスケの、布帛やジャージであればヘソ出し、肩だしルックなどが流行りだした。これにはいろいろな理由があると思われるが、まず第1に「女性の社会進出による開放感の醸成」、次に「地球温暖化による気温の上昇」に伴い軽くて薄い生地が好まれるといった要因がある。
第1の社会進出については説明が必要だ。ヘソ出しや肩出しルックが流行った時、某男性評論家は「セクシーカジュアル」と名付け、女性が男性の目を引くためにセクシーな着こなしをしていると説いていたが、これは完全に間違った理屈である。
実際、私は、その「セクシーカジュアル」ブランドを生み出したクリエイターに話を聞いたことがあるが、彼は「アメリカンカジュアル」と言っていた。つまり、クリエイターからしてみれば、原料の使用量が少なく肌の露出が増えている服は実は「アメカジ」なのである。私もはじめは理解が追い付かず、驚いたのだが、話を聞いていくうちに理解が深まってきた。
どういうことかわかるだろうか?
河合拓氏の新刊、大好評発売中!

「知らなきゃいけないアパレルの話 ユニクロ、ZARA、シーイン新3極時代がくる!」
話題騒然のシーインの強さの秘密を解き明かす!!なぜ多くのアパレルは青色吐息でユニクロだけが盤石の世界一であり続けるのか!?誰も書かなかった不都合な真実と逆転戦略を明かす、新時代の羅針盤!
自分らしさを全開にする=肌の露出が多いアメリカンなカジュアル
セクシーカジュアルもといアメリカンカジュアルが流行る前の女性の服は、「相手目線のもの」だったようだ。例えば、「お付き合いしている彼氏のお母さんから褒められるような服」という意味である。だから、フリフリのかわいらしい服が百貨店に並んだわけだが、彼が米国留学中に見たものは、女性が社会にでて男性と対等に張り合っている姿だった。
「このトレンドは必ず日本にもくる」
そう直感した彼は、彼がみた「アメリカンカジュアル」を日本のアパレル市場に取り入れた。これが、いわゆるマルキューブランドの始まりなのである。それを、単にスカートが短いからといって、「セクシーカジュアル」としてしまう評論家の表層的な分析も苦笑ものだが、そんなことよりもっと驚いたのは、「自分を自分らしく見せるファッション=セクシーカジュアル=アメリカンカジュアル」だということなのである。
つまり自分らしく自分らしさを表に出すという意味でアメリカンなわけだ。
「価格を上げられない」業界の思い込みが作ったペラペラの混紡

その後、マルキューブランドは一世を風靡し日本中で流行したのだが、失われた30年の間に日本経済は停滞し、本来ならファッションを楽しむ若者から遊ぶ金を奪ってしまい、マルキューブランドはすっかり陰を潜んでしまった。例えば、ユニクロのカシミヤは1万円を切る衝撃プライスだが、目付はおそらく250グラムあるかないかだろう。百貨店で売っているカシミヤは300グラムぐらいの目付なので、カシミヤのように素材が高価な服は目付によって大きく原価も値段が変わる。
生地がペラペラになった理由は、使用量の他にもう一つある。それは、質の悪い素材を使うことが増えているためだ。例えば、ウールにアクリルを混ぜたり、綿にポリエステルを混ぜたり、合成繊維を混ぜることで質を落とし、結果的に生地がペラペラになるのだ。とくに昨今のポリエステルまみれの服をみると、我々素材のプロは、「こんなもので大丈夫なのか」「これでよいのか」と驚いてしまう。
また、小売の世界では、「一度値段を下げたら二度と上げられない」という都市伝説のような話がある。(誰も検証したことはないし、昨年は、アパレルがこぞって値段をあげても売上は落ちなかったから眉唾ものだ。)だから、高価な100%天然繊維から合成繊維混へ移行して価格を下げているのだ。その結果、素材に弾力性がなくなりペラペラになる。これは、一度、低価格で販売してしまったために、売価を元に戻せないから起きたことだと思われる。
インフレ下で、デフレのものづくりをしているアパレル業界

服の世界は、他のさまざまな工業製品と同様にコストプッシュ型インフレと言われているが、もの作りをしている側からしてみると、実は「完全なデフレ」である。
使う原料の量、縫製や編み時間を短くするためのものつくりの簡素化…… これらの結果、服はペラペラになってきて、また、ペラペラの服に消費者が慣れてしまったため、もとに戻すこともしないでいるからだ。まさにデフレなのである。私はこうしたトレンドの結果、「服文化」が日本から消えてゆくのではないかということを懸念している。
今ユニクロ一強なのは、日本の経済が停滞し国民が貧しくなってきたことも関係あるが、それ以上に、消費者が「服などペラペラのもので安く買えば良い」という具合に、買い方、使い方が「ペラペラな服」に慣れてしまったことにも大きな問題がある。
そうなると、過去は「ユニクロは安いが生地は悪い」というポジショニングだったが、いまや「ユニクロがもっともよい生地をつかっている」という具合に、反転してしまっているのだ。
特に、一般アパレルのポリエステルの使用量は年ごとに増えているように見え、また、消費者はそのことに気付かず、気付いてもなにも感じない。これは、ユニクロやシーインなどがつくったファッション文化の負の部分といえる。今、セレクトショップにいくと、Made in Italyの男性用パンツは3万円〜5万円。ニットになると10万円もするほどだ。もちろん、使用する素材の目付、縫製技術、デザインなどは一級品であるが、こんな価格で服をホイホイ買える人は少ない。服にも二次流通市場が整備され新品で買ってもブランドが高値で買い戻してくれればよいのだが、ファッション商品というのは、早いと年ごとに流行が変わるので現実的には難しい。
例えば、男性用パンツなどは、5年前は非常に細いパンツばかりだったのだが、今は、わたりの太いパンツばかりになってしまった。このように、一年で流行が変わるので、なかなか二次流通を幅広く扱うことに前向きになれないでいるようだ。
ここまでみてきたように、服がペラペラになってきたのには、いろいろな意味がある。
経済の停滞と上がらない所得、素材価格のインフレと完成品としての服のデフレ、そしてそれが定着したことによる流行・トレンドなどである。
しかし、今のペラペラは不可逆的なもので、次にトレンドが変わったからもとに戻そうというわけにはいかない。偶然いまは、トレンドとコストダウンがマッチしているだけだからだ。そうなると今後は、本来コストを切り詰めることが得意な中国、韓国ブランドが中価格ブランドに入り込んでくるだろう。今の消費者は、それぐらい価格に対して敏感なのである。
コロナ前に散々叩かれた百貨店の服売場だったが、ここまで世間一般の服がペラペラになると、その反動で常時高価格で非ペラペラの服を売っている百貨店が復活する時代が来る可能性もあるだろう。
河合拓氏の新刊、大好評発売中!

「知らなきゃいけないアパレルの話 ユニクロ、ZARA、シーイン新3極時代がくる!」
話題騒然のシーインの強さの秘密を解き明かす!!なぜ多くのアパレルは青色吐息でユニクロだけが盤石の世界一であり続けるのか!?誰も書かなかった不都合な真実と逆転戦略を明かす、新時代の羅針盤!
プロフィール
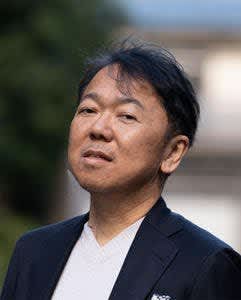
株式会社FRI & Company ltd..代表 Arthur D Little Japan, Kurt Salmon US inc, Accenture stratgy, 日本IBMのパートナー等、世界企業のマネジメントを歴任。大手通販 (株)スクロール(東証一部上場)の社外取締役 (2016年5月まで)。The longreachgroup(投資ファンド)のマネジメントアドバイザを経て、最近はスタートアップ企業のIPO支援、DX戦略などアパレル産業以外に業務は拡大。会社のヴィジョンは小さな総合病院
著作:アパレル三部作「ブランドで競争する技術」「生き残るアパレル死ぬアパレル」「知らなきゃいけないアパレルの話」。メディア出演:「クローズアップ現代」「ABEMA TV」「海外向け衛星放送Bizbuzz Japan」「テレビ広島」「NHKニュース」。経済産業省有識者会議に出席し産業政策を提言。デジタルSPA、Tokyo city showroom 戦略など斬新な戦略コンセプトを産業界へ提言
筆者へのコンタクト
https://takukawai.com/contact/index.html
