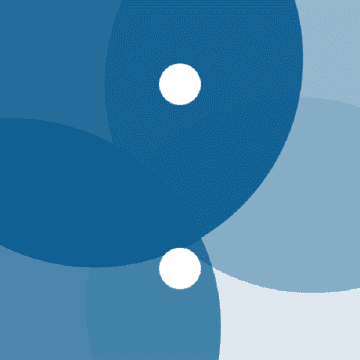2025年の発売が予定されている『モンスターハンターワイルズ(以下、ワイルズ)』。先日6月8日には最新の「プロモーション映像2」も公開され、大きな注目を集めています。
インサイド/Game*Spark編集部は、カプコンが開く合同メディアインタビューに参加。限られた時間ではありますが、最新作『ワイルズ』について、現時点で分かっていることを聞いてきました。

◆『モンハンワイルズ』開発者インタビュー!
―『ワイルズ』からPlayStation5、 Xbox Series X|S、Steamでのクロスプレイに対応していると明かされています。導入の経緯を教えてください。
まず、ユーザーからの要望が非常に大きかったというのがあります。クロスプレイはゲーム開発の初期段階から設計しておかないと実現が難しいという事情があり、『ワイルズ』の開発が始まったときから、クロスプレイを実現するという形で進めていました。
またカプコンタイトルでいうと、先に『ストリートファイター6』『エグゾプライマル』でクロスプレイを実現しています。そこでノウハウや技術を蓄積したうえで、今回の『ワイルズ』にも導入したいと思い、入れさせてもらいました。
今出せる情報として公式HPにも書いていますが、クロスセーブやクロスコマースには対応していません。そのほかオンラインの機能も気になることは色々あるかと思いますが、断片的にお伝えしても分かりにくくなるため、今度ある程度まとめた形で公開します。

―武器を2つ持てることで可能性は広がりましたが、現状の防具スロットではスキルが完璧に揃えられないと思います。その対策などはありますか?
従来シリーズ同様、ハンターが装備する防具は一つという要素は継続します。詳細はまだお伝えできませんがスキルシステムも見直しており、ゲームを進めていく過程で機能が拡張されるなど、最終的に2つの武器種がしっかり遊べる状態を目指しています。
―フィールドは大きく広がっていくのですか?それとも「森林」「砂漠」のようなエリア形式になるのですか?
今回のデモ版では、「隔ての砂原」での生態系を描くという形でプレゼンさせてもらいました。ストーリーが進行するごとにエリアが増えていき、基本的にはシームレスに繋がったマップでエリアが広がっていくようなイメージでいます。
―「集中モード」についてお聞きします。このモードを使うことで操作がどのように変化するのでしょうか?
『ワイルズ』においても、武器種それぞれの個性を活かしつつ新規のアクションを取り入れており、「集中モード」や「集中弱点攻撃」も全ての武器種に実装されてます。
集中モードはトリガーを押すとカーソル(照準)が出現し、そこに対して攻撃やガードが瞬時に出せるというものです。距離だけじゃなく角度も合わせてくれるため、アクションが苦手な方でも攻撃を当てやすくなるなどのメリットがあります。
また『ワイルズ』には、ハンターの攻撃によってモンスターの身体に「傷」ができる仕組みがあります。その傷に向かって攻撃するとダメージが増えたりモンスターが転倒したりするのですが、「集中モード」で狙うと赤いハイライトが付いてわかりやすくなります。集中モード中に傷に向かって集中弱点攻撃すると、今までにない気持ちよさを味わえたり、効果的に破壊できたりします。
―角度調整となると、従来のシリーズではユーザーから“位置取り”と呼ばれるテクニックが重要でした。例えば頭を狙うなら頭のほうに回り込むといった行動を取っていましたが、「集中モード」には移動に関するアシストも加わるのでしょうか?
いえ、あくまで角度のみであり、移動はアシストしません。移動については、各武器種で色々な行動をしながら動けるようアクションを追加しているため、足を止めて何かするというのは少なくなっています。
『ストリートファイター6』のモダン操作のような、操作を簡略化したり、初心者に強力な補助を与えるものではありません。

―オトモアイルーがついに、「がんばろう!」などと人語ボイスを喋ったことに驚きました。さらに主人公も、従来シリーズの「ああ」「うむ」といった相槌ちだけじゃなく、明確に喋っているようです。その狙いを教えてください。また過去シリーズはキャラクリで多くのボイスが選べましたが、このセリフ量だと本作はどうなるのでしょうか。
「モンスターハンター」のストーリーや世界観を感じてもらおうという取り組みを『ワールド』から取り組んでいて、新作『ワイルズ』でも継続しています。その中で、どうしてもハンター(主人公)だけ喋らないというのが描き方として不自然であり、遊んでいるプレイヤーもハンター像を描きにくいのではというところから、自分からどんどん喋るというわけではありませんが、ストーリーへの没入感を優先して最低限のことは喋るようにしました。
なお従来通り、キャラクタークリエイションで自分好みの声を選んだり、アレンジしたりが可能です。詳細はまた後ほどお伝えします。

オトモアイルーについても、没入感という同じ理由で喋るようになりましたが、もう一つ理由があります。本作は編纂者の「アルマ」とオトモアイルーがずっと狩猟に同行してアドバイスしてくれるのですが、色々と状況が変化していくなかでボイスがないとアクション中のプレイヤーに届かないという事情があり、ボイスを入れていこうとなりました。
もちろん、オトモアイルーが喋ることについて従来のファンが気にしているということも伝わっていますし、開発側からも意見はありました。そのためオプションで、従来通り「ニャアニャア」と鳴くような声にも切り替えられるようにしています。
ただ開発側としては、物語のパートナー的な立ち位置として、深みや愛着が出るようにしているので、ぜひボイスも試してほしいと思っています。
―武器種についてお聞きします。太刀や双剣、チャージアックスなど特殊ゲージを持つ武器種は、切り替えるとそのゲージ量はどうなるのでしょうか?
時間減衰はありますが、ゲージは維持されます!どんどんスイッチして遊んでください。ただし、ベースキャンプで武器を変更したらリセットされます。
―クエストのあり方が従来作から変わっている印象があります。『ワールド』では1クエスト50分という基準がありましたが、『ワイルズ』はどうなるのでしょうか。
プレイヤーの腕などで大きく変化しますが、方針は『ワールド』準拠で、同じくらいです。

―これまでのPVでは過去作『モンスターハンター4』を連想させる要素がチラチラと覗きますが、繋がりはあるのでしょうか?ガッツリとストーリーに関わってくるのか、『モンスターハンターライズ』の「カムラの里」と『モンスターハンターポータブル 3rd』の「ユクモ村」のようなものなのか教えてください。
まず『ワイルズ』は何かの続編等ではなく、シナリオも新作として描いています。「禁足地」という舞台が『モンスターハンター4』と同じなので気にされている方も多いかとは思いますが、あくまで「人の立ち入りが禁止されている場所」という一般的な呼称です。
―『ワールド』では「筆頭ルーキー」が“陽気な推薦組”と名前を変えて登場していましたが、そのような繋がりは?
ご想像にお任せします(笑)。
―セクレトは、ガルクと違って自由に攻撃できそうな印象を受けます。乗りながら狩猟笛の演奏したり、操虫棍でエキス回収はできますか?
武器種の詳細はまた追って公開させてください。セクレトへの騎乗で様々な攻撃はできますが、あくまでダメージは地上で取ってもらいたいというコンセプトを持っています。セクレトは騎乗でモンスターを引っ張ってくるとか、そういった特別なアクセントにしています。騎乗だけで狩猟が成り立つような設計にはしていません。
―セクレトに個体差や育成、装備といった要素はありますか?
ゲーム進行によって色々解放されるのですが、毛の色といったカスタマイズがあります。マルチプレイでも自分のセクレトの見分けがつくような設計を検討しています。

―ディレクターの徳田氏、アートディレクター/エグゼクティブディレクターの藤岡氏がいることからも、『ワイルズ』は『ワールド』系譜の作品かと思います。企画はいつ頃から始まったのでしょうか。また、『ワイルズ』という方向性でいこうと思った背景を教えてください。
2018年1月に『ワールド』、その翌年4月に超大型拡張コンテンツ『アイスボーン』が発売されました。『ワイルズ』の構想を練ったり企画実現を検証したりが始まったのは、『アイスボーン』より前になります。
自然の荒々しさを表現する「エコシステム」やビジュアルなどのコンセプトを検証しつつ、次のスペックの機種を決めて、その基準でできる最高峰を目指そうと動いていました。
企画当初から、フィールドの行き来やストーリーをシームレス化しようという構想がありました。そこに大型モンスターをどれくらい出せるのか、群れといったアイデアが加わり、これが実現できるならどれくらい出せて制御できるか、ちゃんとゲームデザインしていこうと煮詰めていった形です。企画書自体は早かったと思います。
PlayStation5/Xbox Series X|S/Steam向けハンティングアクション『モンスターハンターワイルズ』は、2025年発売予定です。
©CAPCOM ※画面は開発中のものです。