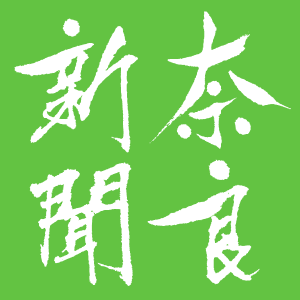河合楽器製作所(静岡県浜松市)が1970年の大阪万博のために作った「万博ピアノ」が残る、奈良県宇陀市榛原下井足の県立宇陀高校榛原学舎で12日、同社のピアノ調律師らが鍵盤の動きを滑らかにする調整などを行った。来年の大阪・関西万博内の県イベントで同ピアノの演奏が検討されており、県万博推進室の職員も作業を見守った。調整後の調律など、あす14日まで作業が続けられる。
万博推進室からの連絡で今年2月、同社ピアノ研究所が同校を訪問。ピアノが良好な状態で維持されていることを確認し、これからも長く親しまれるよう、今回の調整に協力。同研究所の三浦広彦ピアノコーディネーター(60)は「河合小市・初代社長が設計したモデルで、大切に使われてきたことに感謝したい。二つの万博の架け橋となれば」と期待した。
同社は3台の万博ピアノを製造している。うち1台は1970年の万博終了後に榛原町(現宇陀市)の企業が入手し、翌71年に同校に寄贈されていたことが10年前に判明。残る2台は東南アジアのボルネオ島の子どもたちに贈られたり、千葉県内の企業体育館にあることが分かっている。
同校のピアノは幅約1.6メートル、奥行き約2.8メートル、高さ約1メートル。フルコンサートタイプのグランドピアノで、大阪万博のイメージカラーのエメラルドグリーンに塗装されている。
この日は、同社ピアノ研究所の調律師、佐藤祥史さん(36)がピアノから取り外した鍵盤の摩耗部分などを調整。「丈夫な良い木を材料に使っている」と印象を述べた。この後は鍵盤のタッチ感の調整や音色を作る作業を進めるという。
県万博推進室では今後、重量約500キロのピアノを会場に運び使用できるかなどを検討していくといい、和田隼人室長補佐(44)は「県内で守り続けてきたピアノを大阪・関西万博で輝かせることができれば」と来年の演奏実現を見据える。