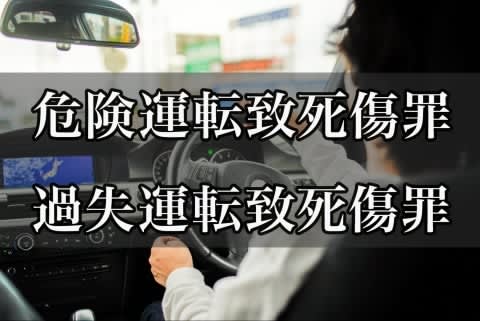
2022年6月に広島県福山市内の一般道でスポーツカーのフェラーリを時速120キロメートルで運転し、小学生を死亡させたなどとして、過失運転致死傷の罪に問われた30代の男性医師に対し、広島地裁福山支部は6月4日、禁錮3年・執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。
報道などによると、医師は法定制限速度を70キロ上回る時速120キロで交差点に進入。衝突した軽乗用車に乗っていた9歳の女児を死亡させたほか、歩道にいた男性にけがをさせたとして、過失運転致死傷の罪に問われていた。
医師は過去3度の速度違反歴があり、「指定最高速度の2倍以上の速度で走行させ、過失の程度は大きい」とされたが、右折する被害者側の車が医師の車を十分に確認しなかったことの影響も考慮し、「直ちに実刑に処することは躊躇される」として執行猶予付きの判決となったようだ。
この判決に対して、ネットでは「時速120キロで走ってくることを確認しろっていうの?」「量刑軽すぎる」「なぜ危険運転致死罪が適用されないのか」など厳しい声が多く上がった。
一般道を時速120キロで走行すること自体がかなり危険な行為といえそうだが、問われた罪名が「危険運転致死傷罪」ではなく「過失運転致死傷罪」だったのはなぜなのだろうか。また、「量刑が軽すぎる」という評価は妥当なのだろうか。元検察官の荒木樹弁護士に解説してもらった。
●「時速何キロ以上だから処罰できる」ものではない
危険運転致死傷罪は、2001年に制定された犯罪です。それまで、交通事故はすべて業務上過失致死傷罪で処罰されていました。
当時の業務上過失致死傷罪の量刑は「懲役5年」が上限で、悪質な運転事故に対する処罰としては軽すぎるとの被害者等の声を受けて、新たに制定された犯罪類型です。
当初は刑法に規定された犯罪でしたが、2013年に制定された自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)に移されています。
危険運転致死傷罪(同法2条)で処罰されるのは、以下の8類型です。
(1)酩酊運転
(2)制御困難高速運転
(3)未熟運転
(4)妨害運転(走行中の自動車の直前に進入等)
(5)妨害運転(走行中の車の前方で停止等)
(6)高速道路等妨害運転
(7)信号無視運転
(8)通行禁止道路運転
同罪成立には各規定の要件を満たすことが必要で、いくら危険な運転であっても、これらの規定のいずれかに該当し、検察官が確実に証明しない限り、危険運転致死傷罪で処罰することはできません。
今回問題となっているのは、(2)制御困難高速運転です。法律上、「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」が処罰の対象です。具体的な速度は規定されておらず、「時速何キロ以上だから処罰できる」というものではありません。
走行していた道路の交通量や状況などから「制御することが困難な高速度」であることを立証する必要があります。
●直線走行中の制御困難な高速度「立証の客観的な基準がない」
立証の方法として、検察実務で一般に使われているのは、「カーブの限界速度を超えているかどうかを鑑定で算出する方法」です。
カーブの限界速度は、カーブの曲線半径、タイヤの摩擦係数、雨が降っていたか否かで、算出できます。
たとえば、曲線半径40メートルのカーブであれば、時速60キロメートル程度が限界速度です。時速80キロメートルで、曲線半径40メートルのカーブを走行した結果、曲がりきれずに路外に逸脱した場合には「制御することが困難な高速度」に該当します。
私も検察官だった時、町中の交差点(曲線半径20メートル未満)を、時速50キロメートルで走行し、対向車線側にはみ出した事故を、危険運転致傷罪で起訴したことがあります。
このように、高速度のためカーブを曲がりきれなかった事故については、「制御することが困難な高速度」の立証方法が確立しています。一方、直線走行中の事故については、「走行を制御することが困難な高速度」を立証する客観的な基準がありません。
法律は、時速何キロから危険運転に該当すると規定していないため、いくら高速度でも、直進道路である限り、「制御することが困難」と認定されない可能性があります。無罪のおそれがあるため、検察は危険運転致死傷罪で起訴しません。
また、今回のケースのように、右折車と直進車の事故の場合、法律上は直進車側が優先です。直進車が制限速度30キロメートルオーバー程度であれば、右折車側の刑事責任も問われるのが通常です。こういった事情も量刑に執行猶予が付いた事情とは思われます。
もっとも、私が検察官として起訴し、被害者側に落ち度がある交通事故でも高速運転であったことを理由に実刑判決になった経験もありますので、執行猶予付き判決に疑問がないわけではありません。
●「無罪の可能性ある罪名で起訴しない」運用はどうなのか
わずかでも無罪の可能性がある罪名では一切起訴しないという検察の運用が、危険運転致死傷罪の成立を難しくしていますと思います。
危険運転致死傷罪で無罪の可能性があっても、過失運転致死傷罪は成立し得ます。過去には、危険運転致死傷罪で起訴した事件について、予備的に過失運転致死傷罪の訴因を追加したという取り扱いをした例も存在します。
一般道路で時速100キロメートルを超えるような事故は、危険運転致死傷罪で起訴し、予備的に過失運転致死傷罪の訴因を追加するなどして、危険運転致死傷罪の成否を裁判所の判断に委ねるという運用もありうると思います。
【取材協力弁護士】
荒木 樹(あらき・たつる)弁護士
釧路弁護士会所属。1999年検事任官、東京地検、札幌地検等の勤務を経て、2010年退官。出身地である北海道帯広市で荒木法律事務所を開設し、民事・刑事を問わず、地元の事件を中心に取り扱っている。
事務所名:荒木法律事務所
事務所URL:http://obihiro-law.jimdo.com
