
客による迷惑な行為や悪質なクレーム、いわゆる「カスハラ」。今や社会問題化していますが、その対策をどうすればいいのか。現場の声は切実です。
「夜に酔っぱらっているお客様が乗車して『今の道をまっすぐ』と、まっすぐしか言わない人。全くの初対面の客だが『俺の家わかるだろ』みたいなお客様はいた」(若葉自動車 ドライバー 木村宗之さん) 乗客から、時に理不尽なことを要求されるタクシーの現場。 名古屋のタクシー会社「若葉自動車」では、様々なカスハラ対策をしています。 まずは防御板。 「羽交い締めされないように防犯対策を取っている。運転しているとどうしても、後ろの動きがあまり注視できないので。後ろから掴まれたりすると、ちょっとどうしようもなくなっちゃう」(木村宗之さん)
第一声をハキハキ明るく・愛嬌良くしたら…
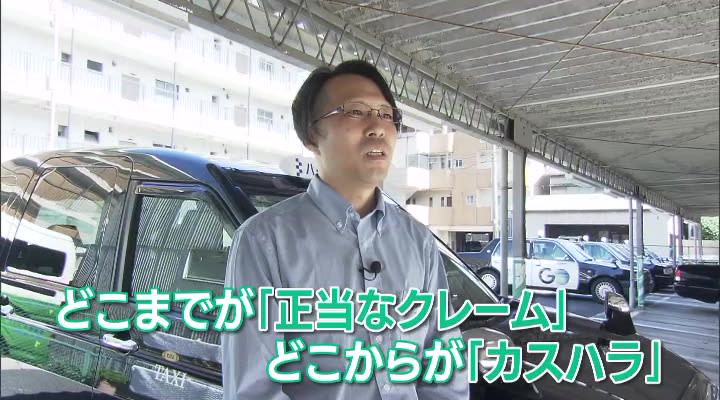
また、顔写真と名前が載った乗務員証から、登録番号のみの乗務員証に変更しました。 「個人情報・名前などがわからないように対策している。動画とか写真で撮られて、インターネットで広まるというのもあり、乗務員の個人情報を守ろうということで、この登録番号を問い合わせたら会社で(ドライバーが)誰か分かるようになっている」(木村宗之さん) 会社とすぐにやり取りができる無線機も、緊急時に役立てられるといいます。さらに、客への「話し方」にも気を付けているそうです。 「お客様に対してどもったり、もごもごしたりしたことでお客さまへの対応があまり出来てなかったが、第一声をハキハキ明るく・愛嬌良くしてたら、そういったのがだいぶ減ったというか、ほとんど無くなったような気がして」(木村宗之さん) ここでも課題になるのは、カスハラかどうかの”線引き”です。どこまでが「正当なクレーム」で、どこからが「カスハラ」なのか? その現場に遭遇した時、瞬時に判断しにくいのが現状だといいます。 「こちらに非があるのか無いのかでも話が変わってきますし。それこそ『蹴られた・殴られた』というのがあれば一番の大きな判断材料になるが、どれが最善策なのかがまだちょっと答えが出てないもんですから、まだ手探りで同僚と話しながらやっている」(木村宗之さん)
市役所のカスハラ対策は──

市民サービスを提供する市役所でもカスハラは起きているといいます。対策はどれぐらい進んでいるのでしょうか? 13日朝の愛知県による協議会にも出席した、大府市。市役所の窓口で、大声を出されたり、不当な要求を執拗に受けたりすることがあるといいます。 「私たち行政職員は、地元の住民の方々と非常に近いところにいると思っている。関係も一時的なものではなく、その人との関係が続くということから、対応に苦慮する場合もある」(大府市 企画政策部 長江敏文 部長) 悪質な電話に対応するため、録音機能付きの電話を導入したり、窓口に防犯カメラを設置したりするなどして、カスハラを防ぐ対策を進めています。 「どこからがカスハラになるのかは難しいというような話も本日の協議会で伺ったので、各団体の意見を聞きながら協議会の中で、より良い対策ができればというふうに思っている」(長江敏文 部長) 名指しのカスハラを防ぐため、フルネームの名札を廃止し、名字だけの名札で対応する自治体も増えてきています。 カスハラを巡っては東京都が、全国初の「カスハラ」防止条例の制定を目指すなど、各地で対応が加速しています。
カスハラ問題に専門家は──
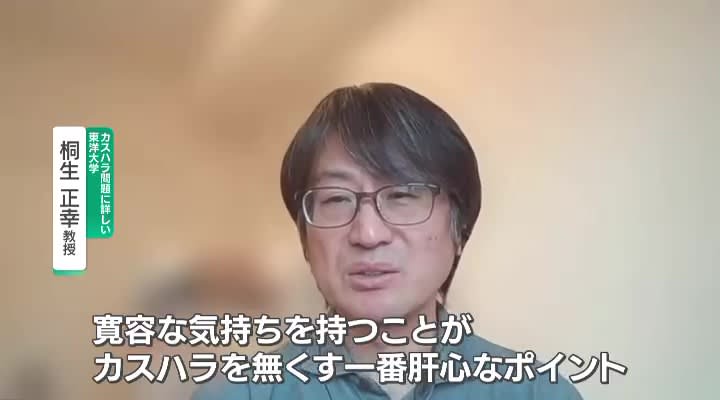
ただ、カスハラ問題に詳しい専門家は、カスハラの基準を一律で線引きするのは難しいと話します。 「業種業態でカスタマーハラスメントの状態状況は違うので、店の状況で自分たちで決めていくということがこれから求められる。お客さんと企業の力関係を作ってしまった。『お客さんが偉い』としてしまったのでカスハラが起きた。お客さんと企業・店は対等。だからといって企業がお客さんをぞんざいな扱いはしてはいけない。対等なんだから互いに許し合う、助け合う関係性が必要。寛容な気持ちを持つことがカスハラを無くす一番肝心なポイント」(カスハラ問題に詳しい東洋大学 桐生正幸 教授)
