「デベロッパーの仕事は今日のお客様を呼ぶことではない。地域に根付き、お客様のニーズに合った個性ある商業施設を運営し、リピーターになっていただくことだ」と横浜岡田屋の岡田伸浩社長はこう言い切る。神奈川県で「MORE‘S(以下:モアーズ)」を運営する岡田伸浩社長に、モノが売れない時代の商業施設のサバイバル戦略、来年135周年を迎える同社の変革への挑戦を聞いた。
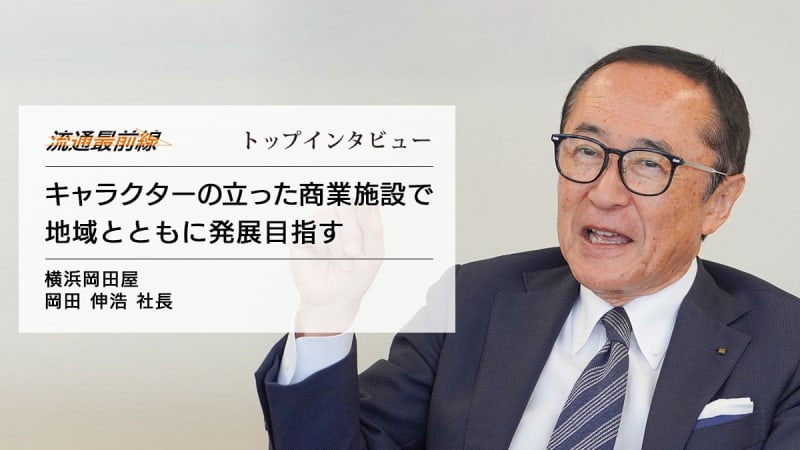
百貨店からキャラの立ったSC運営に転換
――百貨店からSCに業態転換した理由を教えてください
岡田 当社は、1890年に質屋として創業し、1910年に岡田屋呉服屋店、1955年に百貨店となりました。
私は大学卒業後、伊勢丹新宿店の婦人服売り場に就職したのですが、その時、当社が百貨店を運営するのは厳しいと思い知りました。百貨店事業には規模が必要です。それに、大手百貨店は同じ取引先でも商品が違いますし、人脈、教育などレベルが高く、とてもかないません。
当社の店舗は駅に近く、場所はいいけど、規模が小さい。そういう会社がどう生きるべきかというのをずっと考えてきました。
生きる道を模索しているときに、ショッピングセンター化すれば、規模が必ずしも大きくなくても、そこにある専門店の魅力で戦っていけるのではないかと、モアーズに大きくシフトしました。モアーズという商業施設を自分自身の体を通してつくってきた感じです。
<横浜モアーズ>

脱百貨店、ショッピングセンター化し、1980年川崎モアーズ、1982年横浜モアーズが誕生しました。横須賀、相模大野とモアーズを多店舗化し、2019年にはPM事業・地域開発案件である横浜ハンマーヘッドの運営にも乗り出しています。
また、「超高級」は、当社が世の中に与えられた役割ではなく、手の届かないというものではなくて、日常のレベルを上げていくような商業施設の運営が当社の役割だと思っています。
ですから、目指すのは小さくても強い会社です。会社の大きさよりも、その街や分野での存在感の大きさを求め、地域に密着し、キャラクターの立った商業施設を運営することで、時代の変化に対応してきました。モアーズの強みといいますか、基本戦略は、「ロケーション主義」「テナント第一主義」「エバーリフレッシュ」です。
<目指すのは小さくても強い会社と岡田社長>

――横浜、川崎、横須賀どこも個性的なSCですね
岡田 一般的に多店舗展開している商業施設ですと、統一のポイントカード・クレジットカートがあり、施設のコンセプト・販促なども全館一緒です。しかし、当社の各施設は立地によってコンセプトも、ロゴも、カードといった販促施策も違います。
横浜モアーズは「大人のカップルがおしゃれなコトを見つける心地よいところ」を目指して、1階にメンズセレクトショップ、上層階にハンズや飲食店を誘致しています。
横浜モアーズ9階「素敵な普通」をテーマに刷新
――今春15年ぶりに横浜モアーズのレストランフロアを改装しました
<9階レストランフロアを刷新>

岡田 4月に9階レストランフロアが、11店舗のうち2店舗が新業態、7店舗が神奈川初出店となる飲食店を導入し、大きく生まれ変わりました。手が届く、ちょっとしたぜいたくを提供するレストランがそろっていて、おかげさまで順調にスタートしています。
それから意外だったのは、9階のリニューアルが、8階のレストランフロアに全く影響がない。8階は8階で、ハングリータイガーやスターバックスに今までのファンが来てくださって、むしろ伸び気味になり、9階には今までとは違うお客様が来ているような実感があります。
モアーズは「より、より、より」という「モア、モア、モア」なので、「すごく」じゃないのです。どっちかというと、「ちょっと」なんですよ。「ちょっともっと」。そこが今回の横浜モアーズ9階のプロジェクトでも重要で、「素敵な普通」「ちょっとおしゃれ」「ちょっとご褒美」ニーズをターゲットにしています。
――同じ企業が運営しているとは思えないくらい各施設のキャラが立っています
<川崎モアーズ>

岡田 川崎は「駅前立体商店街」がテーマで、「かわさき市場」という食品売り場、ダイソー、サイゼリヤなどに出店してもらっています。
横須賀モアーズシティでは地元ファミリー包み込み戦略として、徹底的に顧客のリピート率をあげる戦略をとっています。会員向けポイントカードを開店前に市内全戸に配布したのですが、現在、横須賀市人口38万人のうち、15万人が会員です。
売上の77%がカードホルダーと、まるで会員制のSCのようです。会員のうち7割が20~30代女性です。10月1日の創業祭は、ポイントアップやプレゼントが当たる抽選会などを実施していまして、横須賀市民の皆様で大変にぎわいます。
<横須賀モアーズシティ>

また、横浜などで定着した「モアーズ」の名前を使わず、2019年から「横浜ハンマーヘッド」の基本計画・テナントリーシング・PM業務を手掛けています。事業公募で選ばれた官民共同プロジェクトで、地域開発への参画と連携という新しいチャレンジになります。
クルミっ子など工場でハンマーヘッドのにぎわい創出
――ハンマーヘッドでの取り組みを教えてください
<横浜ハンマーヘッド>

岡田 当社が今まで運営してきた商業施設は駅前立地ですが、ハンマーヘッド周辺は、ふ頭の上で、駅前のようにふらりとお客様が来てくださるわけではない。ここに来ていただく目的を作らなければ、お客様に来ていただけないと思い、テナント誘致のテーマは「ファクトリー」とし、鎌倉紅谷の「クルミっ子」、クラフトビールやジンの工場を作りました。
そのほかも、クラフトビールの品ぞろえが素晴らしくて人気の「クレイジーセブン」とまで呼ばれるセブンイレブンですとか、個性的なテナントばかりで、おかげさまで順調に推移しています。
観光客というのは流動的で、観光で儲けるのはそう簡単なことではありません。だからこそ、地域の方に来ていただきたいのです。
横浜というのは、マンションも増えていますし、お勤めの方も多くいらっしゃいます。そういう方たちに来ていただくような、時間を過ごす場所を作りたいと思っています。今秋にも新しいレストランがオープンしたり、テナントを入れ替えたりと、商業施設はできて終わりではなく、できてからが始まりなので、リフレッシュしていきます。
さらに、ハンマーヘッドでは、赤レンガ倉庫やワールドポーターズ、マリン&ウォークといった周辺の施設とともに販促企画を展開しています。もちろん、季節のご挨拶を施設内に掲示しますが、あえて季節限定セールを全面に押し出すような販促はしないですね。
――あえて季節にこだわらない販促とは
岡田 ファッションビルですと、夏のバーゲンセールですとか、定番の販促があります。しかし、安いものでしたら、ネットでいつでも買える時代です。セールの安さだけでお客様にリアル店舗に来ていただくのは、なかなか難しい。
それよりも、エリア全体を回遊する企画や、横須賀のモアーズシティのように、創業祭が地域のお祭りになるような、地元と密着した販促で、リアル店舗に行く楽しさを感じてもらうほうが大事ではないでしょうか。
<エバーリフレッシュと岡田社長>

――施設のリニューアルにも注力しています
岡田 モアーズ各店の「エバーリフレッシュ」を継続しています。横浜モアーズは今春の9階レストラン街に続き、今年度中に1~3階のリニューアルも計画しています。
横浜駅周辺は、高島屋、そごう、ジョイナス、ルミネ、ニュウマン、CeeU Yokohama、ポルタと駅チカ商業施設の激戦区です。歴史的にみて、横浜駅にいらっしゃるお客様が行く商業施設は平均2カ所弱と言われています。(選挙に例えると)有権者の票は一人2票ですね。この2票のうちに選んでいただくには、キャラクターの立った商業施設にならないといけません。
アイテム、顧客ターゲットをある程度特化して、キャラクターを立てる。そのため、2008年に横浜モアーズ1階へBEAMSとSHIPSのメンズセレクトショップを誘致しました。
横浜駅西口における商業施設の定石である食品でも婦人服飾、化粧品ではありませんでしたから相当心配されました。しかし、スタイリッシュなメンズセレクトショップは女性客を拒絶するわけではありません。結果的に好評ですし、この秋に1~3階をリニューアル予定です。
トイレも気を抜かずエバーリフレッシュ
――共用部の改修もポイントですね
岡田 格好よくいいますと、デベロッパーの仕事は今日のお客様を呼ぶことではなく、リピーターを増やすこと。明日のお客様を増やすことだと思っています。当社は運営方針として「プリーズ・カム・アゲイン、またどうぞお越しくださいませ」を重視しています。
リピーターになっていただくためには、品切れがないことも大事ですが、接客サービスとか、働いている人たちの姿ですとか、単にモノや箱じゃない。商業施設を人に例えると、総合的な人柄、また会いたいと思われる、つまりまた来たいと思っていただくことです。
そう考えたとき、きれいなトイレというのは大きな要素になると思いました。その象徴が、眺めがよくて広いパウダールームを導入した、横浜モアーズの8階のトイレです。2008年の全館耐震補強と大幅リニューアルの際に、力を入れて改装しました。
<8階のパウダールーム>

それまで横浜駅西口の広場を眺められるレストランだったところを1区画、トイレにしてしまったのです。これは普通の施設運営で行くと、そこでの売り上げが見込めなくなるわけですから、常識的には考えられないことでしょう。しかし、当社が考える商業施設のリフレッシュというのは、それを言い出すと成り立ちません。
入社したての女子社員も巻き込み、トイレプロジェクトを立ち上げ、コンセントを置くべきか、フィッテングルームがあると女子学生のたまり場になってしまうのではないかなど徹底的に議論しました。トイレが空いているかどうか、一目でわかるようなドアの開き具合ですとか、細かいところまで研究しました。
――あえて売り場面積を減らしたと
岡田 モアーズの建物は古いので、どうしても天井が低く、窮屈に感じてしまうのですね。以前は、もっと売り場がぎっちり詰め込まれていたのですが、2008年の改修の際、売り場面積を5%以上減らし、通路やエスカレーターの周りの空間をゆったりとりました。
売り場面積が減っても、残った部分の収益性を上げればいいのです。狭くて窮屈なところでは、お客様が買い物をしたい雰囲気になりません。腹をくくって、トイレや共用部をリフレッシュしました。
「モアーズ」は「より」の「モア」なので、「素敵な普通」「ちょっとおしゃれ」「普通にできるちょっと豊かな場所」というものをそれぞれのエリアで作っていく。そんな思いで各施設をリフレッシュしています。
――社員教育について教えてください
岡田 社内外での研修といった一般的な制度に加え、休日に他社の商業施設を見て、写真を撮って、A41枚レポートを出すと特別手当を出すこともしています。もちろん、休日に社員はプライベートで遊びに行くわけですが、モアーズという商業施設を運営するチームにとって、「お出かけ」が自分を磨く最大のことでしょう。自分で出かけて、目で見て、感動する。リアルな喜びをどれだけ体験しているか。この数だけ、お客様に魅力的なリアル店舗を提供できる、そう思っています。
例えば、婦人服ですとか、担当が決まってしまうと、ついついその業務の視点でしか、仕事を見なくなってしまう。一歩引いて、広い視点で、さまざまな商業施設を見るということは大事ですね。難しく考えすぎず、いろいろなものを幅広く見て、いいなと思える感性をどう鍛えていくか。社員教育では、そういったことも重視しています。
<リアルな体験を重視と岡田社長>

――座右の銘を教えてください
岡田 「ネバーギブアップ」です。普通の人はもうギブアップということになってからが、私の出番だと思っています。
今の時代は、「目指せ!○○!!」といった大きな目標は立てにくい。生き方も多様になってきました。大変な反面、当社のような中小企業でも生き残る選択肢が増えてきました。規模を目指すことが、必ずしも正解はない。規模は規模に負けるし、社員の求める豊かな仕事とは、必ずしも大企業の発展と共にあるわけではないと思います。
当社のある拠点で営業チーフを勤める女性は、学生時代モアーズのビアガーデンでずっとアルバイトをしていました。それで、モアーズで働きたいと就職してくれて、モチベーション高く頑張ってくれています。
会社説明会の冒頭でいつも応募者に話すのですが、商業施設の運営は必ずしも規模を求めない事業です。ロケーションなどの条件、施設コンセプト・方向性がしっかりしていれば、テナント企業は出店してくださる。
コンセプトや方向性をしっかり持って、社員とともに「こういう店を作っていこう」と言える環境にあるという点ではいい時代ではないでしょうか。当社は「ロケーション主義」「テナント第一主義」「エバーリフレッシュ」で、地域愛のある人たちとともに、これからも各エリアで頑張っていきたいと思います。
■岡田伸浩社長略歴
1953年横浜市出身。慶應義塾大学商学部卒業。
伊勢丹を経て1977年横浜岡田屋に入社、1993年に同社社長に就任。1989年横浜青年会議所理事長、1993年日本青年会議所会頭などを歴任。横浜ハンマーヘッドを運営する新港ふ頭客船ターミナルの社長、横浜商工会議所 副会頭、神奈川県スポーツ協会 会長、横浜市観光協会 理事長も務める。
取材・執筆 鹿野島智子
■横浜モアーズの関連記事
横浜モアーズ/9階にレストラン11店舗オープン「おいしいカウンター」も登場

