by 編集部:谷川 潔

2020年に米国ラスベガスで開催されたCESにおいて、トヨタ自動車 豊田章男社長(当時)が発表したのが実証都市「ウーブン・シティ」。実際に記者もプレスカンファレンスに参加、CESでは自動運転関連の技術が発表されることが多く、トヨタのプレスカンファレンスは当初自動運転関連の技術発表と見られていた。ところが豊田社長は、クルマではなく未来都市を発表した。この発表は、CESに参加した世界中の報道関係者だけでなく、多くの人に驚きをもって迎えられた。CESにおいては通常はあまり設けられない、発表内容に関する詳細なQ&Aセッションも用意されていたほどだった。
現在、ウーブン・シティはトヨタ自動車東日本株式会社 東富士工場(静岡県裾野市)の跡地に建設が進められている。当初、コネクティッドシティやスマートシティといった形で語られていたウーブン・シティだが、建設が進む中で目指すところが少し見えてきた。
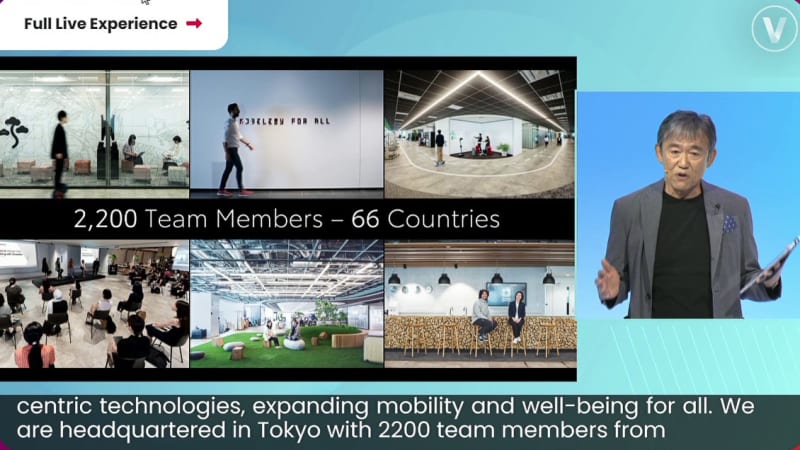
5月下旬にはオリンピックを夏に控えるパリのテックイベント「Viva Technology: 2024」に出展。ウーブン・バイ・トヨタの代表取締役兼CEOを務める隈部肇氏がプレゼンテーションを行なったほか、同社 SVP 豊田大輔氏、R&D Director 大石耕太氏らが展示を実施。現地での説明にあたった。
ウーブン・シティの全貌はまだ分からないが、パリに出展するなど積極的な発信を開始しつつあるように見える。今回、パリでの反響などについて隈部氏、豊田氏、大石氏にうかがうことができたので、ウーブン・シティの構想を含めてお届けする。
ウーブン・シティはスマートシティではなく、テストコースの街

豊田氏は、ウーブン・シティに込められた思いについて語ってくれた。トヨタ自動車は、豊田佐吉が母のために発明した自動織機がルーツとなっているのはよく知られているところだが、ウーブン・シティもその思いをともにしている。
トヨタのコアフィロソフィーとして「誰かのために」というのがあり、ウーブン(Woven、織り込まれた)という名称は、さまざまな思いが織り込まれていることを意味している。この織り込まれたという意味は、もちろん織機から来ているもの。ちなみに、レクサスのスピンドルデザインも、織機に使われているシャトルに由来しており、トヨタの源流をたどると多くのものが豊田佐吉が母のために発明した自動織機にたどりつく。
豊田氏は、この「誰かのために」という思いを絶対に守りたいといい、自動車会社からモビリティカンパニーになっていくなかでも「誰かのために」という思いは変わらないという。
ウーブン・シティ誕生もこの「誰かのために」がきっかけとなっている。前述のようにウーブン・シティは、東富士工場が東北に移転した跡地に建設が進められている。東富士工場が東北に移転したのは、2011年に東日本大震災があり、トヨタとしてはその復興のために寄付だけではなく、仕事を作ることを決断した。トヨタ自動車はトヨタ自動車東日本として生産設備を東北に集約、東北を自動車生産の一大拠点とした。
利府町長 熊谷大氏は、「荒野のような被災地に、お金の寄付や食べ物や服や下着や家電ではなくて、生産すること、真面目に仕事と向き合うこと、技術を学ぶこと、そして製品を作り、みんなが喜んでくれる『ものづくり』という日本の伝統で、その手を、支援の手を差し伸べてくださいました」と、ラリーチャレンジ利府の際に感謝の言葉を述べている。
一方、移転することとなった東富士工場においては1人の従業員のエピソードがあったと豊田氏はいう。その従業員の方は東北に異動したのだが、当時の豊田社長が工場を閉めるとアナウンスをしたときに、その方が「東北の工場に移ってクルマを作り続けたい気持ちはあるが、さまざまな事情があって(東北に)行けない、辞めざるを得ない仲間もいて、やはりよろこんでは行けない。今後、トヨタとして東富士がどうなっていくのか、教えてほしい」と聞いたという。豊田社長は「東富士の地を今後50年にわたる未来の自動車づくりに貢献できる聖地として、自動運転などの実証を行なう『コネクテッドシティ』に変革させていく」と返答。それがウーブン・シティの始まりだと教えてくれた。
このウーブン・シティには、さまざまなものが織り込まれているが、モビリティとして、人、モノ、情報、エネルギーの4つが織り込まれており、幸せの量産とともに「モビリティの拡張」を目指していくと豊田氏は語る。
モビリティの拡張というのは、何かつかみどころがない部分でもあるが、豊田氏はインターネットの登場と、インターネットの拡張に例えてくれた。よく知られているようにインターネットは、分散ネットワークであるARPANETをルーツとしており、コンピュータ同士をつなぐ技術だ。日本では1995年のWindows 95発売を機に一般に広がり始め、今では誰もが意識せずに使っている。当初は電子メールやファイル交換、掲示板などで利用されていたが、多くの人の努力によってさまざまな技術や利用方法が発明され、基本的な社会インフラとなっている。多くの人は意識せずに使用しており、今やインターネットなしの生活など考えられないだろう。
豊田氏はモビリティも同様だという。現在は、単に移動と捉えられているモビリティにおいて、発明や技術革新が行なわれることでモビリティの用途が拡大していくだろうという。そのために必要なのが、モビリティの実証実験を行なっていく場所で、それがウーブン・シティだという。
例えば自動車はテストコースで、さまざまなテストをすることでよりよいものになってきた。ウーブン・シティも同様で、「テストコースの街」だという。
ウーブン・シティに暮らす人は発明家のマインドを持ち、思いついたことを形にして生活に組み込める。そのために、実際にものを作り上げる施設も準備され、発明をサポートする体制が用意される。
もちろんその前に、デジタルツインとして作り上げられた街があり、バーチャル空間で実証実験を行なえる。このメリットを豊田氏は、「前さばきみたいなのをやっておけば、リアルでの手戻りを減らす開発ができるというのもあります」と表現する。普通ITの世界で語る人は、「前さばき」であるとか「手戻り」とかはあまり使わないことが多いのだが、自動車屋としての暮らしがベースにある豊田氏の言葉は製造メーカーならでは。バーチャルがあってリアルがあるのではなく、リアルがあってバーチャルがあるという意識を感じる。
豊田氏は、このデジタルツインとしてのウーブン・シティがあることで改善を速く回すことができ、実際の「ものづくり」も手戻りなく行なうことができ、街へ組み込めるという。このウーブン・シティには多くの人や企業が開発を行ない、そして居住することになる。
豊田氏は「トヨタのアセット(ものづくりの力、改善文化)などを使って、未来をともに作っていく人たち」が住む街になるといい、リアルなものづくり企業であり、トヨタの元々の強みとウーブン・バイ・トヨタのソフトウェアツールの両方を活用してほしいという。ウーブン・シティは「モビリティを拡張し、未来の当たり前を発明するためのしくみ」だと語ってくれた。
パリでの反響は、リアルを持っていること

では、そのようなウーブン・シティをパリのテックイベント「Viva Technology: 2024」で公開した反響はどうだったのだろう? その点について豊田氏は、「実際に街を作っていることに驚く人が多かった」という。IT系のイベントを多く見ている人なら、バーチャル空間での設計や暮らしなどのデモを多く見ていることだろう。とくにテックイベントに訪れる人なら、そこへの驚きは、例えば「見た目だけでなく物理法則が働くか?」「バーチャル空間を作り上げる工数はどのくらいか」といった部分になるかもしれない。
日本にいるとウーブン・シティの発表から見てしまっているためか、街を作っているのを当たり前と捉えてしまい、デジタルツインの街作りがある部分に興味を持ってしまう。

ところが、パリの人は初めてウーブン・シティ構想を知ったときに、一様に本物の街を建設中であることに驚いてくれるという。「実際に街があることに驚いてくれた人が多かった」(豊田氏)と第一印象を語り、その上で「リアルを持っているのはやはり強いところだと思います。大きなテックジャイアントもリアルを持ってなかったりするので」と、これまでのアセットを活かせるのが改めてトヨタの強みであることを認識したという。「我々はリアルを持っているけれど、ソフトは苦手だったから。苦手かもしれないのだけれど、今模索しています。がんばって鍛えようとしています。それができてくると、ハード出身のハードウェアアセットを持っている人たちがソフトを分かるようになるのと、ソフトウェアを分かっている人たちがハードを分かるようになるのはどっちが先かな」と語り、日本でこの街を作っていくことが、世界との競争に大切だと位置付けているようだ。
このリアルな部分に関してだが、パリでプレゼンテーションを行なった隈部氏は、バーチャルデータに実際の位置情報があることもウーブン・シティの特徴だという。隈部氏は、長くデンソーでADASなどの開発に携わってきた人で、電動化を進めるJ-QuAD DYNAMICSの社長も務めていた。コロナ禍前は、海外ショーのデンソーブースで会うことが多く、当時からAIに着目。AIデータの格納における4bit INTや8bit floatなどについて意見交換させていただいた覚えがある。要するに、トップマネジメントでありながら、バリバリのハードウェア、ソフトウェア技術者な人なのだ。
その隈部氏が楽しそうに語るのは、ウーブン・シティのデジタルツインのデータには位置情報があること。つまり、その建物の立つ位置が実際にあり、バーチャルがあってリアルがあるのではなく、実際にリアルが存在する前提でデジタルツインの街が作られているということになる。自動車部品などで座標データがあるのは当たり前かもしれないが、位置情報となるジオデータ(地理空間データ)があるのは極めて珍しい。データアトリビュート的にも、そのような設計がされていることになる。小さな座標データかもしれないが、そこに重みがあると隈部氏は教えてくれた。
また、そのほかパリに出展した狙いとしてデータの取り扱いに対する人々の気持ちを知りたかったと豊田氏はいう。現在、AIなどで利用する収集データに関しては、さまざまな意見がある。ウーブン・シティでは、実際に人が住むことから、人がどう行動しているのかデータを収集することを想定している。テストコースでもあり、実証実験の場でもあるので当たり前だが、世界の人を呼び込む上で個人データ収集に厳しい欧州の人の感触を肌で知りたかったという。
その結果はというと、「取り組み対して前向きな方々が多い」とのことで、基本的にはポジティブ。「現状にしっかりとフォーカスをして進めた方がいいな、というのはすごく自信を持って感じたところです」と、有益な手応えを得たようだ。
ウーブン・シティはリアルに根ざした上で、モビリティの拡張を行なうテストコースとして作られている。豊田氏は、「スマートシティはテックファーストのイメージが大きい。ウーブン・シティはそうではありません。ヒト中心とモビリティのプロダクトを開発するテストコースですということをご理解いただければありがたいなと思います」と、建築が進みつつあるウーブン・シティの現在地を教えてくれた。
