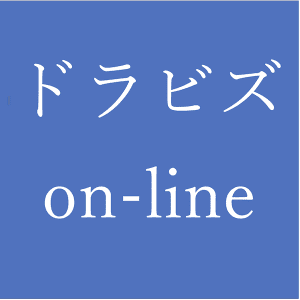【2024.06.14配信】日本医学会連合は6月12日、厚労省に「医薬品安定供給に関する提言を提出した。我が国の健康に関する安全保障上、国民の生命を守るため、切れ目のない医療供給のために必要で、安定確保について特に配慮が必要とされる医薬品である「安定確保医薬品」については、リストの定期的な見直しとその周知、政策への反映を求めている。
ウロキナーゼ(カテゴリーB)などの重要薬剤の供給不安が現場に影響を与えていることが判明
「医薬品安定供給に関する提言」は、厚生労働省の浅沼一成医政局長、内山博之医薬産業振興・医療情報審議官に提出された。
提言は学会が加盟学会に対して行った、医薬品の安定供給に関するアンケートの結果を踏まえてまとめたもの。アンケートは2024年1月から2月にかけて行われた。
アンケートでは、医薬品の供給不安定が日常診療で多く使われる鎮咳薬、解熱鎮痛薬などから、代替の効かない注射薬まで、幅広く生じていたと指摘。また、アンケートの中で必要に応じて備蓄、ないしは国産化を組み合わせた対策を一層講じることが望ましいなどの意見があったという。
提言では供給不安に対する政策を検討する際には、水際で対応を迫られる医療者や、不安や戸惑いを抱く患者の意見を聴取し、ニーズを汲み取ることが重要であると指摘している。
また、アンケート調査の結果では、他の調査でも課題として挙げられている抗生物質に加え、メトトレキサート(カテゴリーA)やウロキナーゼ(カテゴリーB)などの重要薬剤の供給不安が現場に影響を与えていることが判明した。安定確保するべき医薬品の種類は年を追うごとに変化することが考えられるものの、3年前から変更が行われておらず、多くの医療系学会の幹部が「このリストを知らない」という結果も出ている。
提言では、「安定確保医薬品」について、厚生労働省と日本医学会連合が協働して、定期的なリストの見直しの仕組みを導入した上で、関係者に向けて周知し、薬価を含めた政策に反映するべきだとしている。
日本医学会連合としては、医薬品安定供給に関する議論への参加を求めている。