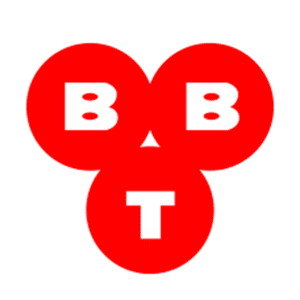人口が100万人を割り込んだ富山県。
「人口減少の現場」取材は、10年前に続き「消滅の可能性」を指摘された氷見市です。
能登半島地震の被害も富山県内で最も大きく、人口の流出に拍車がかかるとの懸念もあります。
*リポート
「氷見市の新道地区です。こちらの80世帯のうち、半分の40世帯が二次避難先で暮らしているということです。夕方の時間帯ですが、住民の姿は見られません」
氷見市栄町にある新道地区。
元日の地震から5カ月余り。
いまも、ブルーシートに覆われた住宅や傾いたままの住宅が多く見られます。
地区の鮮魚店や醤油店は店を閉めました。
*氷見市新道町内会 山崎勇人会長
「ここは住んでいたが、市外に行った。高岡市に行った。家を買ったそう」
新道地区の山崎勇人会長です。
町内およそ80世帯のうち、40世帯ほどは別の町内にある市営住宅や賃貸住宅などに二次避難していますが、2世帯は市外へ移り住んだといいます。
*氷見市新道町内会 山崎勇人会長
「2件の家族が転居されたが、ほとんどの家族が地元で住みたいという思いがある。震災の影響で町内からは相当いなくなったが、いずれは戻ってきたいという気持ちがある」
山崎さんの自宅は「大規模半壊」と判定されました。
自宅は解体せざるを得ませんが、ここで住み続けることを決めています。
*氷見市新道町内会 山崎勇人会長
「ここの家に生まれた以上、ここにずっと住み続けたい。おじいちゃん、おばあちゃんもずっとここにいたので。どこかへ行きたいということは、一度も思わなかった」
一方で、地元での生活再建に複雑な思いを抱えている住民がいます。
自宅が全壊となった沖崎明さんです。
*自宅が全壊 沖崎明さん
「浮いている状態。畳が波打っている」
液状化により床が浮き上がっているだけでなく、地面にもヒビが入りました。
*自宅が全壊 沖崎明さん
「公費解体の申請をした。解体した後、地盤改良をやってもらうが、家をここで建てるかと言われると難しい。個人所有と稲積振興会の土地と、29世帯の共有地が並んでいる」
この地域は、細長い1軒の宅地に隣近所の住民との共有地が交じっており、再建は一筋縄ではいきません。
沖崎さんは現在、町外にある二次避難先の賃貸住宅で暮らしていますが、契約が終わる2年後、どこに住むかは決められずにいます。
*自宅が全壊 沖崎明さん
「公費解体にどのくらいかかるのか、地盤改良するのに何年かかるのかが問題。もう70代だから」
氷見市の人口は現在、4万2652人。
この40年で4分の3に減りました。
県内のほかの市町村と比べても早いスピードで減少し続けています。
さらに2050年にかけての若年女性の減少率は63%と朝日町に次ぐ数字で、消滅の可能性を指摘されました。
(富山県内の「消滅可能性自治体」5市町 朝日町64% 氷見市63% 上市町59% 入善町56% 南砺市55%)
こうした現状に、地震が拍車をかけました。
地震発生後、今年1月から5月までに氷見市からほかの市町村へ転出した人は合わせて566人で、去年の同じ月に比べて増えています。
この状況に、氷見市の林市長は…。
*氷見市 林正之市長
「(市外に)一時的に住んでいても、近いうちに戻ってくる予定で住んでいるのではないか。同じ町内会の災害公営住宅に入る。なるべく早く液状化対策を提案し、住宅を再建しようとなってもらえるよう、スピード感を持って進めていきたい」
地震の被害が特に大きかった新道地区。
この男性は、地震の後、市内の別の町内で中古住宅を購入し引っ越しました。
*自宅が全壊し町外へ転居 鎌和紀さん
「正直、自分の生活を安定させないと何をやるにしても前に進めない。ここに死ぬまで住むつもりだったから、さみしい」
山崎会長は「復興の形が見えなければ、避難住民のふるさとへの気持ちは徐々に離れていってしまう」と危惧しています。
*氷見市新道町内会 山崎勇人会長
「公営住宅など早く建設にとりかかってもらえれば、避難している人も先が見える。それが全くないので、高岡に2次避難している人もここでいいとなる可能性が高くなる。早めに戻ってくるような、目に見えるようなスピード感がほしい」
人口減少に苦悩する氷見市を襲った地震。
復興の形を住民にどれだけ早く示せるかが問われています。
【以下、取材した記者報告】
震災から5カ月経っても、街並みに変化がない様子がわかりました。
今月から氷見市内では公費解体が進む予定で、これが始まれば街の様子は様変わりしますが、今は手つかずのままの住宅が多くあります。
氷見市の住宅被害は全壊221件、半壊482件を含む6000件以上に上り、県内で最も大きな被害となりました。
市は、公費解体を来年度末までに終える予定ですが、その先については見通すのが難しい状況です。
市内の宅地には個人所有と共有地の土地が混在している場合があり、液状化対策や地盤改良をどの程度やり、何年かかるかも見通せません。
この苦境で住民が離れていく状況、人口流出を防ぐためには、震災からの復興の姿を早期に見せることが重要です。