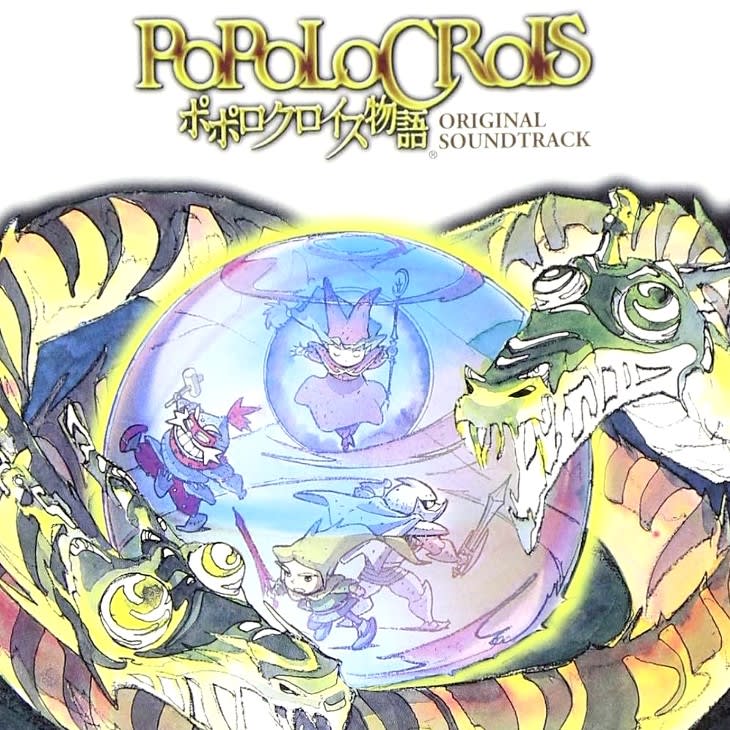
連載【佐橋佳幸の40曲】vol.28 瞳の扉 / marhy 作詞:西尾佐栄子 作曲:佐橋佳幸 編曲:佐橋佳幸
佐橋佳幸が音楽を手がけたプレステ版「ポポロクロイス物語」
1980年代、朝日小学生新聞で連載が始まった田森庸介の漫画『ポポロクロイス物語』。その後、テレビアニメ化されたり、PlayStationやニンテンドー3DS、スマホアプリなどさまざまなプラットフォームでゲーム化されたり。今では親子二世代ファンも多い人気シリーズだ。
そのゲーム第1弾としてプレステ版RPG『ポポロクロイス物語』が発売されたのが1996年7月。その音楽を手がけていたのも佐橋佳幸だった。佐橋、そして盟友であるマニピュレーターの石川鉄男とエンジニアの飯尾芳史のゴールデントリオは、以降『ポポローグ』(1998年)、『ポポロクロイス物語Ⅱ』(2000年)、『ポポロクロイス はじまりの冒険』(2002年)、『ポポロクロイス 月の掟の冒険』(2004年)『ポポロクロイス物語 ピエトロ王子の冒険』(再編集作、2004年)と続いたこのシリーズ全作の音楽制作に関わってきた。
「1作目が出た1996年は、僕が佐野元春さんとホーボーキング・バンドとして活動していた時期。こういうこともやっていたんです。僕、どんな仕事でもやってきたイメージがあるけど、さすがにゲーム音楽までやっていたのは、ちょっと意外でしょ。でも、実はこれもEPIC・ソニーでUGUISSとしてデビューしたことと深く繋がっている仕事なんです。プレステを開発したソニー・コンピュータエンタテインメント(現:ソニー・インタラクティブエンタテインメント)を立ち上げたひとりが、EPIC・ソニーの創設者である丸山茂雄さんなわけですよ」
「で、丸さんいわく、これからはゲームの時代が本格的にやってくる、と。僕はもともとゲームとかあまりしたことがない人間だったので、“音楽よりもゲームの時代になる” と言われてもピンとはこなかったんだけど。なったもんね。さすが、丸さんの慧眼だね」
ソニーならではの音楽業界ネットワークがフル稼働
家庭用ゲーム機として初の本格的3Dグラフィックを実現し、たちまちセンセーションを巻き起こしたPlayStation。グラフィックのみならず、24チャンネルを同時に鳴らすことができるPCM音源によって、かつてのゲーム機の “ピコピコ” サウンドとは比べものにならないCDクオリティの音を再生できることも大きな魅力だった。
となると、ソニーならではの音楽業界ネットワークがフル稼働。当時、丸山茂雄の肝煎りでソニー・ミュージック内に設立された新たな音楽出版部門 “ソイツァー・ミュージック” から、佐橋は『ポポロクロイス物語』の音楽制作を依頼されたのだった。担当は、長 俊広。かつてEPIC・ソニーで “詩人の血” などのディレクターを務め、佐橋とは顔見知りの仲だった。
「仕事ではそれほど付き合いはなかったけど、以前から飲み仲間ではあってね。というのも、UGUISSがデビュー前に出たとあるコンテストで優勝したのが長さんのやってた九州のバンドだったの。だからその後、初めて会った時の会話が “あれ?UGUISSだよね?” “そうだよ、UGUISSだけど?” みたいな(笑)。そこから仲良くなった。長さんも丸さんと同じように、これからはゲーム業界がすごいことになるから、そこで面白い音楽を作っていきたい… って考えている人で」
「この『ポポロクロイス物語』で今までにない新しいゲーム音楽を作りたいから手伝ってくれないか、と。それを僕に頼んできたのも理由があってね。このゲーム、中世のヨーロッパみたいな雰囲気の王国が舞台。主人公の王子様が深い森の中を冒険して、いろんな敵と戦って… みたいなお話なんですよ。だから、ちょっとトラッドふうの音楽にしたかったらしく、ルーツ音楽にも詳しい僕に声をかけてくれたわけ。なんだっけな? 要するにポール・サイモンがお手本にしたような、ヨーロッパの古い伝承歌とかフォークソングみたいな雰囲気の曲が欲しいんだ、と最初に言われた記憶がある。あと、彼は長崎出身だから飯尾さんとも仲が良かったの。そして、石やん(石川鉄男)ともよく仕事をしていた。だったら飯尾さんと石やんと僕という3人でやらない? というところから、このプロジェクトが始まるわけです」

最初のコンセプトは、アコースティックギターを使ったようなゲームのサントラ
1990年代半ば。ハードディスク・レコーディングが急速に普及しつつあった時代。それまでレコーディングスタジオでなければ作れなかったサウンドを、自宅スタジオでひとりで仕上げることも可能になった。プレステが自宅をゲームセンターばりの娯楽場へと変えてしまったのと呼応するかのように、音楽シーンにも宅録時代の波がやってきた。そんな中、この時期を境に、日々ギターを抱えてあちこちのスタジオを駆け回っていた佐橋の仕事スタイルも少しずつ変わっていく。“ポポロクロイス・シリーズ” との出会いは、そんな時代の変わり目を象徴する仕事のひとつだった。
「まずは曲作りを含めてプリプロをしようということになったんだけど。RPGの音楽はキャラクター全員それぞれに音楽がついていたり、とにかく曲数も多くて。けっこう細かい作業がえんえん続くんです。こんなのレコーディングスタジオでやってたら、何日もスタジオを押さえっぱなしでやらないといけない。大変だし、面倒だし、お金もかかる。ただ、打ち込みが進化していたといっても、まだ機材関係とかネットでのやり取りっていうのは発展途上だったからね。家でひとりでカタカタやって完成させるには、まだちょっと早い時代。そもそもアコースティックギターを使ったような音楽をゲームのサントラでやりたい… というのが最初のコンセプトだったわけだから、打ち込みだけのスタジオでやるというわけにもいかない。みんなでいろいろ考えたあげく、結局、レコーディングスタジオで録音をする前段階として、ホテルでプリプロ作業をすることにしました」
レコーディングの拠点は、ヒルトン東京のスイートルーム
都心のシティホテルでのプリプロ。今となってはちょっと不思議なシチュエーションに思えるかもしれない。が、当時、ホテルのスイートルームでの作業というのはある意味で最先端のレコーディングスタイルのひとつだった。コンピュータと最小限の楽器、そしてレコーディングスタジオほど本格的ではないものの一般家屋よりはワンランク上の防音仕様。時間を気にせずひと晩じゅうでも作業ができて、仮眠をとりたければ心地よく整えられたベッドがある。ポポロクロイス・チームは、東京・西新宿にあるヒルトン東京のスイートルームに曲作り作業の拠点を構えた。
「みんなそれぞれ部屋のキーを持っていれば、忙しい3人がそれぞれ勝手に来て作業ができる。眠くなっちゃったし、明日も早いから、今日は泊まってくわ… とかもできるし。ホーボーキング・バンドのツアーリハーサルと丸かぶりの時期があったなぁ。その時は芝浦のスタジオでリハが終わると、新宿に行ってホテルで作業して、そのまま泊まって、翌日は山手線に乗って芝浦へ… みたいな生活をしていたこともあります」
佐橋がセッションギタリストを始めた1980年代には、デモテープを1曲録るにもスタジオを丸1日押さえて楽器をセッティングして… と本番レコーディングと変わらない手間暇をかけることも少なくなかった。それを考えると、わずか10年あまりで音楽業界の制作システム自体が大きく変わりつつあった。
「豪華なようだけど、実はレコーディングスタジオをずーっと貸し切るよりは安上がりなんだよ。電気代もタダだし、徹底的に集中して仕事ができるし、いつ始めていつ終わってもいいしね。おなか空いたらルームサービスも頼める(笑)。そこにコンピューター3台と、打ち込み用のキーボードと、俺のギターとかをセットアップして。3人が同時にヘッドフォンをして作ってた。スイートルームの壁には、ゲームに登場するキャラクターをプリントアウトした紙をばーっと貼ってね。それぞれ自分が担当するキャラクターと、その場面の絵コンテを見ながら “この子はどういう曲がいいかなぁ” とか考えながら次から次へと作っていくの」
なんだか刑事ドラマに出てくる捜査本部… みたいな?
「まさに(笑)。ほんと、いったいどれだけ作ったのかわからないくらい膨大な曲数を作ったっけ。作業中の写真とか撮っておけばよかったな。今だったらありえないよね。ホテルのスイートルームで男3人がヘッドフォンをして黙々と… 。どう考えても、あやしい組織だよ(笑)。時々、長さんとかゲーム制作の担当者が様子を見にくるわけ。それで “この曲、いいねー” とか “これはもうちょっとテンポ速くできる?” とか。ゲームの制作と同時進行で、ゲームと音楽、両方が同じくらいのタイミングで完成する。ゲームってこうやってできていくんだって勉強にもなった。しかも、その業界でもヒットメイカーとして知られるすごい人たちと仕事できたわけだからね。面白かったよ」
日本を代表する若手ジャズマンのひとり、大林武司から届いた一通のLINE
話はちょっと横道に逸れるが、ここでちょっといい話をひとつ。今年2月、佐橋はMISIAのコンサートツアーに2公演だけゲスト参加した。現在、MISHAのツアーでバンマスをつとめているのは世界的に活躍するキーボード奏者、大林武司。名門バークリー音楽院を卒業後、ニューヨークを拠点に本格的活動を開始し、黒田卓也やホセ・ジェイムズ、ネイト・スミスらのサポートも手がける日本を代表する若手ジャズマンのひとりだ。その大林と初共演した佐橋は、さっそく連絡先を交換。共演からしばらく経ったある日、大林から一通のLINEが届いたという。
「僕が出演した後ももちろんMISHAのツアーは続いていたわけだけど。どっかの公演先から “『ポポロクロイス』の音楽やってたの、佐橋さんだったんですね!?” っていうLINEが来たの。“そうかぁ、大林くんもあのゲームをやってた世代だもんねぇ” って返事したら、その後すぐに動画が送られてきてね。なんと僕が書いたポポロクロイスの曲を、大林くんがピアノで弾いている映像なの(笑)。子供の頃に大好きで、もう完全に覚えているから譜面も何も見ずに弾けるんだって。大林くんといえば、今、海外でも大活躍している本当にすごいプレイヤーだよ? あれは嬉しかったなー(笑)」
佐橋が足かけ15年以上関わり続けたポポロクロイス・シリーズ
ポポロクロイス・シリーズでは作品ごとの主題歌も佐橋たちが手がけた。いわゆる “イメージソング” ではなく、映画やドラマと同じように作品中で流れる主題歌を制作するというのも、高音質が特徴のゲーム機、プレステならではの新たな試みだった。
「ソニーのネットワークを生かして、当時は無名の新人だったけど後に活躍するようになった人たちが歌ってくれているの。シリーズ中、ほぼ全作が僕の作曲。編曲も僕だったり、僕と飯尾さんと石やんとの連名だったり。第1作『ポポロクロイス物語』の「ピエトロの旅立ち」という曲を歌っている “ジュリエッタ柴田” というのは実は奥山佳恵ちゃん。2作目の『ポポローグ』の「月の魔法 星の夢〜夢を彷徨う人へ〜」は、この年にメジャーデビューした大塚利恵ちゃん。どれもなかなかいい曲だったと思いますよ」
なかでも佐橋のお気に入りは、2002年に発売されたシリーズ第4作『ポポロクロイス はじまりの冒険』の主題歌「瞳の扉」。作・編曲を佐橋が手がけ、作詞は西尾佐栄子。歌っているのはmarhy(マリ)。
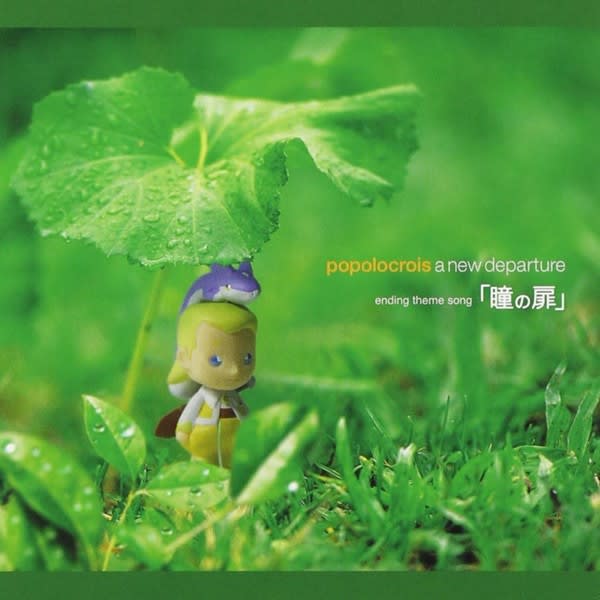
「これ、いい曲なんだよね。完全に山弦的な世界というか。自分で言うのもなんだけど。ゲーム中の音楽と違って、主題歌は唯一の歌モノだから、僕も毎回すごく作るのが楽しかったんですけど。特にこの曲の雰囲気とかは、当時、山弦とかSOYでやっていたことがけっこう上手に出てるんじゃないかなと思う。いわば、オグちゃん(小倉博和)と作っていた音楽の中の “サハシ部分” がよく出ている… というのかな」
「歌ってくれたmarhyさんは、今や “プリキュア” の作曲を手がけたりとか本当に大活躍しているけど。この曲を歌ってもらった時は、まだ活動を始めたばかりの頃。ソイツァー・ミュージックで作家とか、姉妹でコーラスの仕事とかをしていて。当時から自分で曲を書ける人だったけど、この時は僕が自分で曲を書きたかったので歌だけで参加してもらった。歌、めっちゃうまくてね。レコーディングもあっという間に終わった。その後、ソングライターとして、松たか子さんのアルバム『harvest songs』(2003年)で「Welcome back」という曲を書いてもらいました」
プレステ版が最初に登場して以降、ソーシャルゲーム、ダウンロード版など、形態を変えていったポポロクロイス・シリーズ。佐橋も足かけ15年以上関わり続けたことになる。
「他にゲームの仕事はほとんどしていない。その後も石やんはけっこうゲーム音楽をやっているので、そこにギターを弾きに行ったり、お手伝いはちょこちょこしているけど。自分が制作に関わったものはこれだけ。ま、“これだけ” と言ってもシリーズ化しているから曲数にしたら本当に膨大だよね。でも、この “ポポロ” で学んだ音楽の作り方は、その後の仕事にものすごく役に立っているんです。特にいろんなドラマとか映画のサントラを作る時とか。先週までまた映画の劇伴を作っていたんだけど。考えてみたら、それも “ポポロ” でのやり方で作ってるもんね。勉強になりました。はい」
カタリベ: 能地祐子

