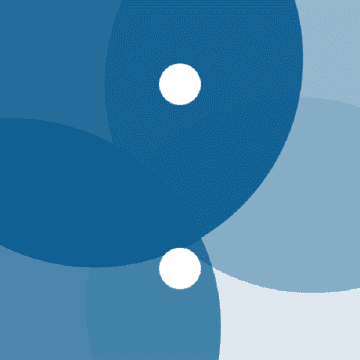江戸時代から続く歴史に幕
大分県竹田市の銘菓として知られる「荒城の月」などを手掛けてきた川口自由堂が5月、江戸末期から続いていた歴史に幕を下ろした。
後継者の不在や原材料の仕入れ価格の高騰など地域の和菓子店を取り巻く環境は厳しく、老舗の閉店が相次いでいる。
看板商品「荒城の月」全国菓子大博覧会で最高賞
和菓子店・川口自由堂は1866年に竹田市で創業しました。
滝廉太郎の名曲が由来の「荒城の月」を看板商品とする老舗の1つで、黄身と淡雪羹(かん)にこだわったしっとりした味わいが特徴だ。
全国菓子大博覧会で最高賞を受賞するなど竹田の銘菓として人気となり、最盛期には大分県内で4店舗を構えていた。しかし…
閉店の背景に…地域の労働者不足や設備の老朽化
――川口晃生さん「うちは後継ぎがいないから誰かに頼もうと思っていたけど、なかなか地域に人がいない。やっぱり働き手が少ない、どこも労働者不足」4代目の川口晃生さん(77歳)はこの度、158年続いてきた店を閉める決断をした。
理由の1つが従業員の高齢化と後継者の不在だった。
川口さんだけでなく、10人の従業員の多くも高齢となり、以前と同じように店を回していくのが難しくなってきたという。
また、建物や製造設備の老朽化も進み、更新する場合2000万円以上の資金がかかる見込みだ。
――川口晃生さん「製造する機械も古いからやり替えるとなると相当お金がかかる。それに見合う返りがあるかという、もうないかもしれない」
コロナ禍で手土産需要が落ち込む中でも、「客が来る限りは」と年中無休の営業を続けてきたが、砂糖や小麦粉といった原材料価格の高騰もあり、自らの代で老舗ののれんを下ろすという決断に至った。
30年以上働く従業員「やっていて良かった」
最後の菓子作りとなったこの日、工場にはいつものように製造や梱包に励む従業員の姿が。
――「いつもと変わらなくても、皆、実感はあると思う。今日は忙しさがいつもと違う。朝も早かった」こう話すのは川口自由堂で33年に渡って働いてきた木下あけみさん。
――木下あけみさん「コロナ禍からどんどん客も減っていったし社長の体力や従業員の年齢もある。そう長くないという覚悟はある程度あった。(店は)すごく居心地が良かった。寂しいけど、今までありがとうやご苦労様と言ってもらえてすごくやっていてよかった」
店には午前中から途切れることのない客の姿
この日は閉店を知った昔からのファンが次々と店を訪れ、従業員に感謝やねぎらいの言葉をかけた。
――客は「もう30年以上食べている。奥さんの実家に行くと茶の間にはいつも荒城の月があった」
――客は「食べ納めで買いに来た。皆にも配る」
――川口晃生さん「感謝しかない。県内のあちこちから来てくれてありがたい」
地域で受け継がれてきた和菓子店の閉店は川口自由堂だけではない。同じく竹田市の名物として知られる「はら太餅」を製造・販売している和菓子店・生長堂も後継者の不在と原材料高騰を理由に今月閉店することとなった。
「歴史ある店に足を運んで」老舗を盛り上げる動きも
老舗の閉店が相次ぐ中、伝統の和菓子を盛り上げようという動きもある。
老舗和菓子店でつくる全国銘産菓子工業協同組合が2023年にはじめたのが、御朱印ならぬ「御菓印」の取り組みでだ。歴史ある各地の和菓子店に足を運んでもらおうと企画したもので各地の本店で一定額以上の買い物などをすると、各店が趣向を凝らしたオリジナルの御菓印を手に入れることができる。
全国銘産菓子工業協同組合では「店に足を運んでもらうことで、改めて地域で受け継がれてきた伝統の味と歴史を知ってもらうきっかけの1つになれば」と話している。
手土産や家庭のおやつとして温もりを伝えてきた地域の和菓子店。惜しまれながらも消える老舗が増えることにどう向き合うのか。
地域の人口減少や原材料価格の高騰など難しい課題が重なっている。
(テレビ大分)