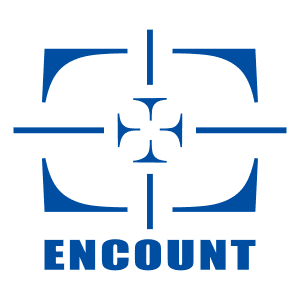EV特有のトラブルに対する救援が必要になっている
近年、ちまたで見かけることも多いEV(Electric Vehicle:電気自動車)。そのカテゴリーには幅広く普及したハイブリッド車に加えて、BEV(バッテリー式電気自動車)さらには燃料電池車などが含まれている。しかしここで素朴な疑問が。EVがトラブルを起こした際にはレスキューは受けられるのだろうか? 特に駆動用バッテリー切れによる走行不能時はどのような対策があるのか? 潜在的なEVユーザーを含めて実は気になるポイントなのではないだろうか。
特にEVの中でもバッテリーのみをエネルギー源にしているBEVの場合、バッテリー切れ=走行不能に陥ってしまう。そんな場合にはどうなってしまうのだろう。出先でバッテリー残量がゼロになってしまって立ち往生する事態に陥る可能性も予測できる。その時でも慌てず対処するためにはEV向けのレスキュー方法は知っておきたい。BEVをこれから導入しようと思っているユーザーにも気になるポイントになるEVのロードサービスについて注目した。

すでにEVロードサービスが始まっている
そこで、クルマのレスキューを手がけるJAF(日本自動車連盟)でEVの救援について話をうかがうことにした。取材に訪れたのは千葉支部。JAFではすでにEVロードサービスをスタートさせていて、2023年度には全国で年間8000件を超える救援を実施、直近の2024年4月も638件のEVロードサービスを実施している。とはいえ、従来のロードサービスが月間16万件(2024年4月)を超えていることを考えるとEVの救援事例はまだまだ少ないと言えるだろう。
そんな中でもBEVならではの救援内容として注目したのが“電欠”と呼ばれる“EVの駆動用電池切れ”に対する救援だ。2024年の救援データではEVロードサービス出動の8.5%をEVの駆動用電池切れが占めていることからも要注意の項目だと言うことが分かる。しかもガソリン車の“ガス欠”であればガソリンを補給すればすぐに走り出すことが可能なのだが、BEVの場合は当然充電しないと走行不能だ。そこで今回取材した千葉支部ではレッカー車にBEVへの給電システムを搭載(現在は一部の支部にのみ配備されている)、出先で駆動用電池切れになってしまったBEVに現場で充電することができるシステムを備えている。ただし、給電システムを搭載しないレッカー車の場合は、給電スポットまでのけん引で救援するスタイルが採られる。

レッカー車に搭載される給電システムとは?
JAFのレッカー車に搭載されているBEVへの給電システム、いったいどんなものなのかが気になったので、実際にBEVに対して充電を実施してもらうことにした。レッカー車には給電用のバッテリーと中継器、さらにBEVへの接続用のケーブル/コネクター(チャデモ規格)を搭載する。テスラへの給電の場合は変換コネクター(ユーザーが持っていることが前提)を用いて給電が可能だ。
BEVの駆動用バッテリー残量がゼロになってしまい、走行不能になった場合にこのレッカー車が現場に駆けつけ、その場で充電できる仕組みだ。約20分の充電(9.5kW)で0%だった残量が8~9%程度まで復活する。もちろん救援時に満充電にするわけではなく、あくまでも緊急時のレスキューなので、最寄りの給電スポットまで自走することができる範囲の充電が目的だ。
当日取材に対応してくれた千葉支部のスタッフによると、「救援後は給電スポットにたどり着くまでは電費を考慮してエアコンはかけないで走行してください。特にヒーターは電費を悪化させるのでオフで走行してもらうようにしています」。
全国どこのJAF支部でも給電システムを搭載したレッカー車が配備されているわけではないのだが、ガソリン車同様にBEVの電欠に対する救援態勢も整ってきているようだ。
今後、BEV車両の普及に合わせて増えることが予想される電欠によるロードサービス要請。出先での電欠による立ち往生に加えて、自宅マンションの駐車場で駆動用電池切れになったケースもすでに発生している。「自宅で車が動けなくなり、家から出られなくなったからご自宅で充電するという依頼もありました」。世界ではEV購入とともに、充電器も購入するのがスタンダード。しかし、日本では充電設備のないマンションなどでは、EVのみを購入するというのもポピュラーだ。レアケースではあるが、そんな時もJAFは駆け付けている。給電システムを備えたレッカー車による救援スタイルがあることは大きな安心感につながるだろう。土田康弘