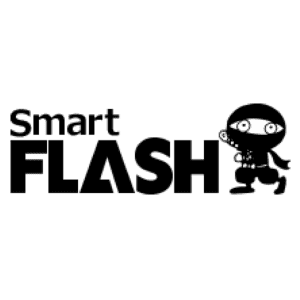木野 花
「36年前に引っ越してきたときに、最初に入ったのが珈琲館だったんです。温かい接客が心地よくて、それからほぼ毎日、通っています」
木野花は、コーヒーをひと口飲むと、ホッとした表情を浮かべる。「珈琲館 根津店」は、下町情緒が漂う “谷根千” に店を構える。
「芝居の稽古が午後からなら、お昼前にお邪魔します。こちらにはスポーツ新聞が置いてあるので、大好きな大谷翔平選手と藤井聡太さんの記事をチェック。天才的なのに努力を惜しまない姿を見て、毎朝、元気をもらっています」
お気に入りのメニューはナポリタンとホットケーキ。
「ナポリタンは昔ながらの喫茶店の味で美味しいんです。ホットケーキは、珈琲館といえばホットケーキという安定の味。台本を読んで1時間ほど過ごして稽古に行くのが私の日課。仕事の打ち合わせもこちらが多く、私の “出張オフィス” みたいです」
木野には珈琲館に来る前に、毎朝のルーティンがある。花に水をやり、部屋の掃除、ストレッチまでを2時間位。
「40歳まで掃除は週に一回の人間でした。母の『あなたに花は育てられない』というひと言で奮起して鉢植えの花を購入。毎朝、お水をあげていたら、どんどん咲くからかわいくなって。花にも表情があってシャキッと咲いていると私も元気になれる。ある日、生き生きと花が咲くベランダから散らかった部屋が見えて、ガッカリして、きれいにしたいと思ったんです。掃除も要はコツ。毎朝10分で終わるように部屋を整理整頓するようになりました。その後にストレッチ。ほこりのない部屋で体を動かすと、気持ちがいいし頭もスッキリします」
健康そのものに思えるが、50代後半から股関節の痛みに悩まされた。2015年に人工関節を入れる手術を決意。動くたびに襲われていた激痛から解放されると、まわりが驚くほど元気になった。
「だから、今は天下無敵」と笑う木野の女優人生も、じつは体調を崩したことがきっかけで始まった。
「大学卒業後は中学の美術教師をしていました。学校は男女平等と教えていながら、女の先生はお茶くみや補助的な仕事がまわってくる。これが現実かと思うと、この矛盾に職員室で叫びだしたいほどでした。生徒と向き合う時間は楽しかったんですが、職員室の時間がとにかく苦痛でした」
2学期の終わりぐらいから神経性胃炎と片頭痛に悩まされ、病院通いに。医師の診断は “ストレス” だった。
「当時はストレスという言葉が出始めたころ。どうすればいいかと聞くと、『環境を変えればいい』と。それを聞いた途端、病気になるくらいなら辞めようと決心しました」
そこで目に留まったのが雑誌「美術手帖」。表紙には「アングラ特集」と大きな文字が躍っていた。
「アングラって何? と思ったときに私の第六感が働いて。怖そうだけど、おもしろそうだし、ワクワクする。こういうところに身を投げだしたら、自分がどんなふうになるか試してみたいって思ったんです」
ここからは早かった。母親に「3年だけ時間をください」とお願いして東京へ。養成所である「東京演劇アンサンブル」の夜間部に入所すると、昼間はアルバイト、夜は演技の勉強に勤しんだ。バレエのレッスンで体を動かしたり、発声練習で大声を出しているうちに、気がつくと体調は回復していた。木野はさまざまな役を通して、ふだん口にすることのない台詞を大勢の客の前で話す演劇の魅力に目覚めていく。夜間から昼間に編入し、2年間、みっちり学ぶことに。
だが、演劇の世界も驚くほど男社会だった。二度とストレスで病気にはなりたくないと、1974年、養成所で知り合った木野を含む女性6人で劇団「青い鳥」を旗揚げする。
「男との軋轢(あつれき)がないから、女だけの考えを自由に好きなだけ出して『自分たちがおもしろいと思えるもの』にこだわりました。芝居作りは完全集団作業。全員が納得しないとアイデアが通らないので、自然とブラッシュアップされていく。そのために時間がかかって、上演は1年に1本でした。半年はバイトでお金を貯めて、半年で稽古を積む。大道具も衣装も全部自分たちで作って運び、チケットも手売りでしたが、口コミで徐々にお客さんも増えていって、劇団はずっと黒字でした」
演劇雑誌の編集長が観に来て「これはおもしろい」と話が広まると、旗揚げ公演で600枚だったチケットは3000枚ほど売れるようになっていた。
このころ、木野は初めて翻訳劇の演出を手がける。
「作品すべてに目を光らせて責任を取らなければいけない演出は、すごく怖かったけどワクワクしました。もっと演出をやりたいという欲が出て、12年在籍した『青い鳥』をやめ、単独で演出家の道を歩み始めました」
演出家をしながら、役者の依頼があれば受ける仕事のスタンスを決めた。
大学で美術しか学ばず、養成所で演劇を習っただけの木野は、ほとんど自己流で芝居作りをしてきた。
「役者としての演技も『青い鳥』時代から、絶対に主役はやらず、脇の狂言回しでおもしろいことをやり、お茶を濁してきました。自分は役者に向いてないんじゃないかと不安を抱えていた気がします」
そんな木野に大きな転機が訪れる。「劇団☆新感線」から高田聖子とのW主演で『花の紅天狗』(2003年公演)のオファーが届く。2年ほど断わり続けたが、熱心に口説かれ受けることに。
「やれないことだらけで、地獄のような日々でした。二十数年何をやってきたのだろうと、このまま終わらせるのが悔しくて、やるだけやってダメだったら、本当にやめようって。自分が演出しているときは、役者に『死ぬ気でやれ』と言ってきたのに、自分は何なんだと。この時ようやく役者として目が覚めました。
50歳過ぎてから本気で取り組んだらだんだん楽しくなって。それまで何をやっても自信が持てなかったんですが、精いっぱいやった結果はケセラセラ、なるようになるさと思えるようになって、演じることから解放された気がします」
演技が楽しい。そう話す木野が「青森のナイチンゲール」と呼ばれた花田ミキを演じる映画が『じょっぱり 看護の人 花田ミキ』だ。
「大流行したポリオの看護指導で町から村へと駆けずり回り、男尊女卑の壁にぶつかりながらも、看護師を増やさなければと看護学院創立に尽力した人です。彼女は結婚もせず、子供も産まず、晩年一人で病と戦いますが、王林さん演じるシングルマザーと心を通わせます。波瀾万丈の人生を終わろうとする老女と、今まさに海へ漕ぎ出そうとする若い母親との出会いが見どころです。ぜひ多くの女性に観ていただきたい映画です」
木野は「私はいま成長期」だと続けた。
「『もう70だからこんなもんだ』で止まってしまったら、そこで終わり。好奇心さえあれば新しい発見があって、何歳になっても成長していけるって気づいたんです。最近は『この役を木野さんにやってほしい』という依頼がくるんですが、私の予想の上をいく役ばかり(笑)。まだまだ止まっていられないんです」
喜寿を迎えても伸び盛り。女優・木野花の進撃は続く。
きのはな
1948年1月8日生まれ 青森県出身 1974年に劇団「青い鳥」を旗揚げし、小劇場ブームの立役者に。1986年に退団し、演出家、女優として活躍。連続テレビ小説『あまちゃん』(2013年、NHK)、『ブギウギ』(2024年)などに出演。映画『愛しのアイリーン』(2018年)では第92回キネマ旬報ベスト・テン助演女優賞を受賞。主演映画『じょっぱり 看護の人 花田ミキ』が7月2日より東京都写真美術館、7月5日よりイオンシネマ新青森、イオンシネマ弘前ほか、全国順次公開予定
【珈琲館 根津店】
住所/東京都文京区根津2-6-5 マインハイム根津1階
営業時間/月〜土曜 7:30〜20:00 日曜・祝日 7:30〜19:30※新聞の有無は店舗によって異なります
写真・野澤亘伸
ヘアメイク・片桐直樹