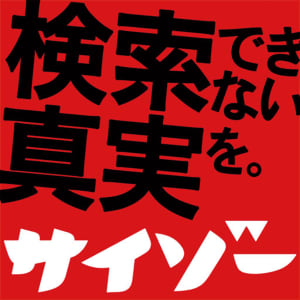──歴史エッセイスト・堀江宏樹が国民的番組・NHK「大河ドラマ」(など)に登場した人や事件をテーマに、ドラマと史実の交差点を探るべく自由勝手に考察していく! 前回はコチラ
前回の『光る君へ』第23回「雪の舞うころ」、いつもながらさまざまなトピックが含まれた回でした。今回は筆者の周囲から疑問が出ていた内容について、いくつかお話してみることにしましょう。
まずは、まひろ(吉高由里子さん)の父・藤原為時(岸谷五朗さん)が、越前国の国司として重要な采配を迫られていた部分についてです。中国からやってきた宋人商人たちが、「日本の朝廷と直接に商いがしたい」と熱望していましたが、なぜ朝廷は、中国との直接的なビジネスを避けていたのか……と疑問に感じる声がありました。
この歴史的背景について、はっきりと語った史料はありません。
しかし、日本が中国との国交を絶ったのは、寛平6年(894年)、約260年続いていた遣唐使の廃止がきっかけです。理由は遣唐使の船旅に事故がつきものであること、そして中国国内の戦乱だったといわれています。遣唐使の保護は名目で、激しくなる一方の中国の戦乱が飛び火してくることを日本は恐れたのでしょうか(遣唐使の廃止から十数年後に唐は滅亡してしまっています)。
またその後、宋王朝の成立後でも日本が中国との国交樹立に積極的ではなかった理由として、推測できるのは中国側の中華思想です。世界の中心に咲き誇る花=中華ですから、王朝が代わったところで、諸外国はへりくだって中国の皇帝に貢物を差し出し、返礼の品が与えられるだけという「朝貢貿易」が中国との公式な貿易になってしまうため、私貿易が盛んになるのは致し方ないことだったのでしょう。
それゆえ、ドラマにあったように、宋の宮廷の「宰相さま」が商人を日本に派遣し、公式貿易開始を目指して云々……という描写に史実性はないと思われますが、宋や元の時代、民間の商人による私貿易はかなり盛んで、宋側も民間業者が私貿易をやる分にはむしろ積極的に支援するという立場を取っていました。それゆえ、紫式部や藤原道長(ドラマでは柄本佑さん)の時代以降、平安時代後期になればなるほど、多くの商人が日本にやってくることになりました。越前国の敦賀でも九州の博多に並ぶ交易が行われ、宋人たちが多く滞在するようになったとか。
それほど日本の有力貴族たちは私貿易を多く行っていたのです。人気の輸入品のひとつは「宋銭」――つまり質のよい貨幣です。平清盛の一門は宋銭の輸入を通じて財を築いたのは有名な話ですね。こうして中国から輸入された銭貨は、室町時代くらいまで流通していました。室町時代以降、つまり宋王朝の滅亡後は、明王朝が発行したお金が「明銭」として輸入され、日本国内でも信頼性の高い貨幣として流通しました。
近代的な意味での「金本位制度」とは少し異なるかもしれませんが、貨幣の価値が含有される金や銀などの量で決定され、どこの国で発行されたかどうかは関係がなかった時代特有の現象といえるでしょう。
さて、ドラマでは越前にたどり着いたまひろに、当地で新たなロマンスの芽生えがあるかと思いきや、周明(松下洸平さん)はどうやら欲得ずくで彼女に近づいてきただけのようですね。一方で、親戚のおじさんのような立ち位置だった藤原宣孝(佐々木蔵之介さん)が、越前を訪れ、為時がいない間にまひろと親交を深め、最後には求婚までして京都に戻っていったのには驚きました。周明とまひろの仲睦まじい姿を見ていて、危機感に駆られたのかもしれませんね。
史実では、紫式部と宣孝の間に文のやりとりがあったことはわかっているのですが、彼女が京都を発つ前に宣孝からプロポーズされ、越前と京都の間で文のやり取りをしていたのであろうと考えられます。まぁ、ドラマのように宣孝が越前を訪れた可能性も否定はできないでしょうが……。
『紫式部集』という彼女の歌だけを集めた和歌集によると、越前にいる紫式部に宣孝が手紙で「春になれば雪も溶けるように、私に対して閉ざしているあなたの心も溶けるのでは」と書いてきたので、紫式部は「春なれど 白嶺(しらね)の深雪(みゆき) いや積もり 溶くべき程の いつとなきかな」――春になりましたが、越前の山には雪がいっそう高く積もってしまって、溶けることなどありませんよ(私はあなたには心を開いたりしません)という歌を送りつけたことなどが書かれています。
このように現在から見れば「塩対応」そのものに見えるやり取りですが、当時の貴族の間では、これでも充分に「脈あり」の対応だったのです。藤原兼家(ドラマでは段田安則さん)の「妾」であった藤原道綱母(同・財前直見さん演じる寧子)も『蜻蛉日記』の中に、最初は紫式部同様の「塩対応」で、「兼家さまを断ってやった」と書いていますから……。本当に「脈なし」なのはお断りの返事すら(ほとんど)ないという状態で、現在のLINEでいう「未読スルー」に相当します。
ドラマの話に戻りますが、まひろ自身は周明との関係を「恋愛ではない」と明言しているものの、周明は彼女がまだ自分では気づいていない好意を利用しようと必死のようですから、近い将来に周明から傷つけられたまひろは、父親を置いて越前を去らざるを得なくなりそうです。史実の紫式部も2年にも満たぬうちに、父親を越前に残したまま、なぜか帰京して宣孝と結婚したのですが、その謎の部分の説明として、ドラマではオリジナルキャラクターの周明の「裏切り」を描くつもりなのかもしれません。
さて今回、この連載の読者の多くが疑問に思ったのは、安倍晴明(ユースケ・サンタマリアさん)が「一条天皇(塩野瑛久さん)と定子中宮(高畑充希さん)の間に皇子が生まれる」と予言した部分でしょう。長保元年(999年)1月、一条天皇たっての願いで定子は規則を曲げて、後宮に呼び戻され、その直後に第二子を懐妊しました。一条天皇と定子の関係の再燃に「批判が出た」と書物にはよく書かれていますが、公家の日記などには具体的には残されていない(もしくは削除された?)ようですね。
興味深いのは道長の対応です。当時、12歳になった長女の彰子(見上愛さん)を一条天皇に入内させる計画を進めていた道長は、定子が第二子・敦康親王を出産するため、彼女が当時の実家に相当する「竹三条宮」と呼ばれる別邸に宮中から移動するという当日、通例であれば道長もその行列に加わらねばならなかったにもかかわらず、不参加でした。しかも道長は「その日、宇治にある私の別荘で宴を催す」と言い出し、多くの公卿たちを招待したそうです。しかし一条天皇と道長の板挟みとなった大半の公卿たちは屋敷に閉じこもってしまい、実際に宴に参加したのは、道長の異母兄弟の藤原道綱(上地雄輔さん)と、かつては中関白家の派閥にいたものの、道長が彼らを追い落とすのに貢献したと考えられる藤原斉信(金田哲さん)だけだったとのこと。
道長は、定子が2度目の出産を迎えた日の日記(『御堂関白記』)においては、彼女が一条天皇の第二子にして、第一皇子の敦康親王を出産した事実については触れようとせず、まさにその日に「一条天皇から彰子に女御宣旨が下った」と記し、藤原実資(秋山竜次さん)など多くの公卿たちと祝賀の盃を交わし合ったと書いているだけでした。結局、一条天皇も実質的な朝廷の「最高権力者」である道長に、自分が定子との関係を続けていくことを大目に見てもらうため、道長の娘を妃の一人として後宮にいれることを許可せざるを得なくなった背景が感じ取れます。
ちなみに父を早くに亡くし、伊周・隆家(三浦翔平さん・竜星涼さん)という二人の兄も没落した後の定子の後見役になっていたのは、道長の姉の詮子(吉田羊さん)でした。当時の詮子は体調不良がぶり返して困っていたので、定子たち、中関白家の関係者からの怨恨を少しでも解消することで神仏からの加護を得ようとしており、弟・道長の中関白家徹底迫害の方針に逆らったようですね。
道長を「光る君」としてヨイショしている今年の大河ドラマにとっては、史実どおりには絶対に描けないエピソードが今後は続いていくわけなのですが、どのように演出するのでしょうか。ある意味、非常に楽しみでもありますね。
<過去記事はコチラ>