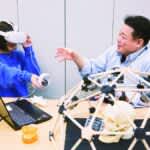
理系・文系のさまざまな科目を、偏りなく横断的に学ぶ文理融合型の学びで、「総合知」の創出をめざしている、同志社大学の“文化情報学部”。今回は、その中で「時空間情報科学」「文化・社会人類学」「地理学総論」の授業を担当されている時空間情報科学・行動計量解析学研究室の津村 宏臣准教授に、詳しくお話をうかがった。

タイムトラベル?パラレルワールド?
「時空間情報科学」とは
「タイムトラベル?やっていることは実はそれに近いんですよ。タイムトラベルとは、量子論的・量子力学的な世界ですが、いわゆる量子論というのは確率論。だから、私達はパラレルワールドがあるのかどうかについて、コンピューター上で試してみるわけです。同じシチュエーションが与えられたとき、同じ行動のルールを持った人間が、同じ行動結果になるのか、コンピューターを使ってシミュレートしていきます。」と語る津村准教授の本来の専門は「先史人類学」という分野。
「いわゆる人類としてのホモサピエンスの歴史そのものを、単に歴史学として研究するのではなく、行動や生態的なことを前提とした研究が私の本来の専門分野です。
例えば、私達の直接の先祖といわれるサピエンスが、お墓のようなものを作り始めるのは随分現在に近くなってからのことでした。しかし、ネアンデルタール人は、その随分前からお墓を作って花を供えるという文化を持っていたのです。そういう文化を持っていた彼らが滅び、文化的に遅れていた我々が生き延びた原因とは一体何なのかについての疑問が私の研究のスタートとなりました。
こうした行動や生態的なことを“文化情報”として見ようとすると、時間と空間の中で行動するので、その痕跡が必ず残ります。痕跡は情報化できるので、その情報から行動や生態的なことを再構築し、その再構築された行動が今の私達とどう異なっているのか比較することができるのです。それを行動メインで考えるときは「行動計量解析学」になり、行動を復元して科学する部分は「時空間情報科学」という学問になるのです。」
学ぶ上での大切な物の見方
「赤い色を見ると興奮したり、危険を感じたりすると聞いたことはありませんか?でも、世界中の人類を見ればわかるように、そんなことは絶対にないわけです。例えばアフリカの一部の遊牧民族には赤という色の概念がありません。あるのは、湿り気。私達は色を見るとき、湿り気を判断基準にはしませんが、アフリカの遊牧民にとってはそちらの方が重要。私達が当たり前だと思っている赤・白・黄色も、実は赤・白・黄色じゃない世界というのがこの地球上にはたくさんあるわけです。
また、私達は“家族”といいますが、中東地域の“家族”という概念は異なります。彼らは時にはクランという言い方もしますが、一般的には氏族(うじぞく)の概念で生きています。だから、季節ごとに遊牧先を変えて、その地域ごとに奥さんのいる一夫多妻制という世界は、人口減少を起こさないための仕組みなのです。
このように、世界は多様な仕組みで成り立っており、実はその多様な仕組みを持っている人達の方が先進国の人口よりはるかに多いのです。だからこそ、いわゆる先進国の非常に限られた世界しか知らない目線で世の中を見るのではなく、世界にある多様な文化にどう科学的にアプローチしていくのかを知って、社会に出てほしいと思っています。」
文系・理系を超えた専門分野の異なる先生がコラボすることで生まれる、新しい学びの授業「ジョイント・リサーチ」
文系・理系の多岐にわたる分野を専門とする先生たちが数多く所属されている文化情報学部。この学部ならではの授業が、2~3領域の専門の異なる先生方がタッグを組んで一緒に授業を行う「ジョイントリサーチ」。グループで探究型演習を行いながら、新たな問題を発見・解決する能力を身につける。
「以前は人間の行動を数理モデルで書かれる先生と組んで、コンピューターの中に作ったパラレルワールドの中に、1000人なら1000人別々の気質をプログラムした人を入れて、空間の条件を変えたときにその1000人がどのような行動をするかを観察し、科学的にモデル化するジョイント・リサーチを行っていました。
今は、国際関係の先生と組んで、地球温暖化や貧困問題といったSDGs一つひとつのテーマについて、実際の世界はどうなっているのかを学生たちがデータを集めて考えるジョイント・リサーチを行っています。理系・文系を超えた全く異なる領域の先生とのコラボで、以前から挑戦してみたかったことに学生たちと一緒に取り組むことができました。」

知らないことを結果として導き出せる可能性の広がる、
文理融合型の学び
数理モデルや確率論などの理系の学びを取り込むことで、知識を超えた知らない結果を導き出すことが可能になる、文理融合型の学びとは?
「何かを知るために膨大な数の本を読んで知識をつけたとしても、読んでいない本のことは語れない。つまり、知識の欠落している部分のことは予測ができないのです。でも、統計学やデータ科学は、ある一定のルールのもとでは、知らないことも結果として導き出す可能性があります。だからこそ、従来型の人類学・歴史学・地理学ではなくて、その中に文理を融合する数理モデル・確率論などを取り込んでいくことで、本を読んでも分からなかった部分が見えてくるという経験を学生達に経験してもらい、学生達の進みたい進路に向けてそこで得た知識を活かしていくことができると考えています。」
「なぜ?」「それは本当?」本やネットから得る知識ではなく、
現地へ行ったり自分で調べる力の大切さ
日々の生活の中で触れる本や映像・ネットは全て既に情報化されたもの。単なる情報ではなく、文化情報学を学ぶ学生にとって身につけてほしい大切な力について、お話を伺った。
「本を読んでもネットで調べても、結局は間接的な知識ですよね。学生たちが、実際に現地に行って体感してみるということをせずに、教科書に書いてあることやネットに書いてあることを鵜呑みにして自己形成をしていくのは、すごく怖いことだと感じます。だから、学生達には普段から自分の目でしっかり世界を見てくるように話していて、私のゼミでは興味を持ったことを調べるために、世界各国へ自分で赴いて現地で調査してくる学生たちが多くいます。
例えば、とにかく走る「タラウマラ族」という民族がなぜ走るのかについて調査するためメキシコに行ってみたり、国際連合開発計画が出版している各国の開発進捗状況の調査結果をまとめた『人間開発報告書(Human Development Report)』の内容と現地の状況の違いに疑問を持ち現地調査のためにガーナへ行ってみたり。海外には興味がないということであれば、今流行りのVRのR(リアリティ)の部分について、例えば1つの同じ空間であってもそれぞれの人にとってリアリティは違うということについて、VR実験を通して解明する卒論を書く学生もいます。情報化されてないところから情報化する能力と、本や映像・ネットのように既に情報化されたものをストックする能力では、使う脳が異なります。
今の学生たちは後者の情報化されたものをストックする能力は長けているけれど、全く知らない場所に一人ポツンと置かれたときに何もないところから情報化することは苦手です。文化情報学を学ぶ学生たちには、アナログな能力を身につけることと、情報科学の使い方をしっかり考えることの大切さを考えてほしいと思っています。」
「文化情報学」を社会化するために
「『文化情報学』が一体何をする学問なのかということは、まだ少なくとも社会化はされていないと思うんですね。それを社会の中で一般化するために、一昨年、文化情報学を社会化するための会社を大学発ベンチャーとして立ち上げました。
大学と高校の高大連携や、大学が中学校へ行って文化情報学の出張講義をして、学問自体の楽しさを伝えるだけでは一方通行。社会に一般化するためには、文化情報学的な『物』が世の中に売っていることが必要なんです。そのために、例えば小学校の修学旅行事前学習用のVRコンテンツを作成し、修学旅行前にVRグラスを使って現地に行った気分を味わいながら、目的地のお寺の仏像を観察して記録してみる、といった事前学習に役立ててもらっています。あと5~6年で、こうした文化情報学が生み出した社会のコマが、小学校の何かの教科・教材になるレベルに達するまで、文化情報学を社会化するための活動も行っていきたいと思っています。」
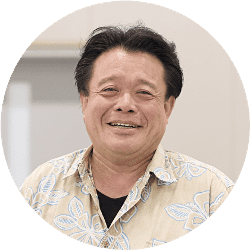
同志社大学文化情報学部 時空間情報科学・行動計量解析学研究室
津村 宏臣准教授
広島県出身。総合研究大学院大学文化科学研究科博士課程修了。国立歴史民俗博物館情報資料研究部講師、東京藝術大学大学院美術研究科助手などを経て、現職。同志社大学文化遺産情報科学研究センターセンター長、真庭市政策アドバイザー(文化政策)などを兼務。同志社大学発ベンチャー株式会社SOCRAH代表取締役。共著に『考古学のためのGIS入門』(古今書院)、『生きる場の人類学』(京都大学出版会)、『シークワーサーの知恵』(京都大学出版会)などがある。
同志社大学 文化情報学部 連載コラム
第1回 言語コミュニケーションのメカニズムを探り、人と自然に話せるコンピュータを研究開発
https://univ-journal.jp/column/2023232766/
第2回 デジタル・ヒストリー、歴史への新たな視座に向けて 〜同志社大学「総合知」の創出〜
https://univ-journal.jp/column/2023219941/
第3回 “男に生まれ変わりたい”と答える女性の割合が、調査では70年前の7割から現在の3割に逆転。性別、居住地域、職業など数字化できないものを含め、社会を知るためのデータを分析するのが『計量社会学』

