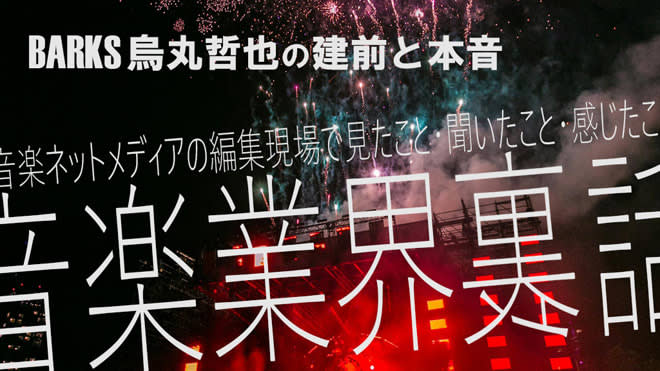
音楽というものは、そもそもが時間とともに流れ消えていく「瞬間芸術」として太古の昔から生活と密接に関わってきたものだけれど、19世紀に録音技術が発明されたことを機に、レコード産業が新たに生まれ急速な発展を遂げてきた。「瞬間芸術」ではなく「録音芸術」というこれまでなかったアートが、現代社会に欠かせぬ一大エンターテイメントとして急速に成長を遂げることとなったわけだ。
優れた「録音芸術」が生み出されていくことを目的に、必要な機能は分業化し最適化され再配置され続けてきた。作品を創る人、パフォーマンスをする人、それを支える人、音楽を宣伝する人、音楽を流通させる人、音楽制作ツールをつくる人、音楽機材を作る人、録音機材を作る人、音楽再生機器を作る人、発表の場を作る人…。そしてもちろんそこに、音楽を聴いて楽しむリスナーの我々の存在だ。
中世にも優れた作曲家が多く存在していたものの、そもそも音楽で食っていけるような環境にはなかったという。音楽という「瞬間芸術」をビジネスにする仕組みが確立していなかったわけで、当時のヒット曲…オペラなど興行が盛んなヒット作品でももっていない限り、楽曲で食っていくことは極めて困難だったとか。パトロンを得たり、ピアノを教えたり、音楽学校で教鞭をとったり、宮廷音楽家として教会や貴族から収入を得たり…と、音楽家の道は険しかったらしい。
そして近代、音楽家は「録音芸術=音源」を売ることで利益を得る仕組みを得た。アナログ盤からカセット、CD、MD…とパッケージは変わっても音楽が世の中を回る仕組みは変わらなかったが、インターネットの登場がそんな音楽業界を根幹から覆した。
今現在、パッケージを買わずとも、音楽は事実上いつでもどこでも自由に聴ける。パッケージが売れれば潤うというミュージシャンの収入構造はもはや日本においても崩壊寸前だ。サブスクでの再生回数や動画サイトでの広告収入が頼みの綱だけど、多くのミュージシャンの生活がこれで支えられるかと問われれば、現実はまだまだ厳しい。
もちろんライブやフェスなどの興行で食っていくという道筋は確立されつつあるけれど、ここでの収益の多くは知的財産を使用したIPビジネスによるものであって、音楽そのものが収益を得ているものではない。パフォーマーは儲かるが、音楽作家は未だ儲からないのだ。
音楽作家はどうすれば食っていけるのだろうか。なにかいい仕組みはないだろうか。

アスリートが企業に就職しながら競技に打ち込む「アスリート社員」のかたちは、ミュージシャンにも転嫁できないものか。スポーツは勝ち負けや記録など結果がはっきりと出るものだけに、売れることだけが正義じゃない「ミュージシャン社員」の業績評価が難しいのはわかる。けど、なんとかならないか。社会への貢献度は、アスリートに負けない力を持っているはずなんだけどな。アーティストは企業に所属し、専門性の高いマネージメント業務は専門会社に委託すれば、今すぐにでも稼働できるのではないか。
さらに突き詰めちゃえば、音楽なんて人類の共通財産なんだから、ミュージシャンは国が生活を保証すればいいじゃんとも思ったりする。要するにミュージシャン国家公務員化計画だ。そもそも国家公務員として認定する仕組みの難しさもわかるし非現実的とも思うけど、音楽産業を全て国営にしちゃう。日本が生み出す音楽エンターテイメントは国策。音楽収益は国が管理する。国がミュージシャンを保護する。国民が税金で音楽を育む。変な中間搾取もなし。ダメかな。小中高の国公立学校の音楽の先生だって、ミュージシャン国家公務員化計画に基づけば、もっともっと多様性に適合する文化育成を可能にするかもしれないし。
ミュージシャンは無形文化財なんだもの。もちろん荒唐無稽なことぐらいわかっているけど、子どもたちの未来を担う話なんだから妄想ぐらいいいじゃないか。ほら、言霊っていうしさ。
文◎BARKS 烏丸哲也
