
3日間で基調講演が1本、セミナーが22本というラインナップは、その殆どが満席となり、立ち見なるという盛況ぶりだった。やはりこういった議論の場が11月のInterBEEだけでは足りておらず、スピード感を持って考えていくべきなのだ。

注目を集めたAdRM
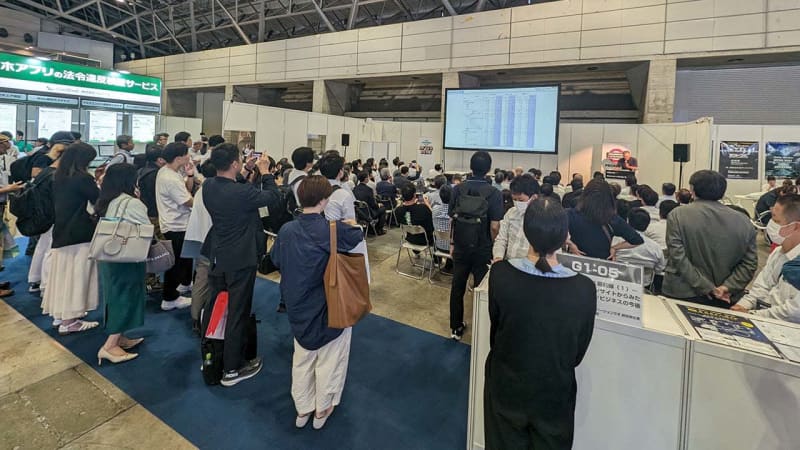
最も注目を集めたセミナーは、地上波テレビ広告の取引が変わる、日本テレビが提唱するAdRM(アドリーチマックス)関連の3本のセッションだ。正確には広告取引が変わるのではなくて、新たな運用型広告が加わるが正しい。
これはテレビの70年の歴史において、はじめてビジネスモデルが変わるという、本当のパラダイムシフトである。電波かネットかといった伝送路議論とは桁違いのビジネスインパクトがある。
もちろん現時点でこれが決まったわけではなく、どれだけの局の支持を得られるかは未知数だ。こうした民放局が系列やエリアを超えて一致団結して動いた例というのは決して多くはない。場合によってはテレビ局以外からの協力も必要になるかもしれない。
広告の世界では既に主導権はネット側にあるのは明確である。ここでテレビはネットに迎合するという意識ではなく、これをきっかけにコンテンツそのものを変化させていくチャンスと捉えるべきだろう。
TVerの現在地と未来
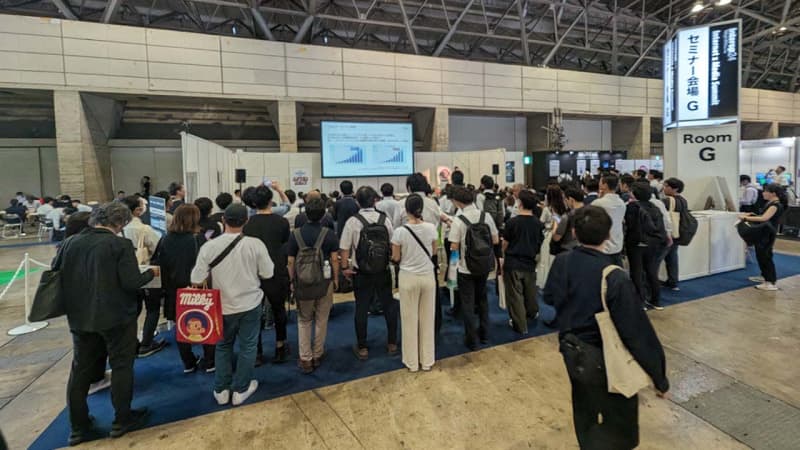
最も多くの参加があったセッションはTVerの現在とこれからについてのセッションだ。
TVerが着実に広がりを見せていることが分かる内容だ。TVerがここまで成長したことについて関係者の努力に敬意を表すと同時に、TVerを軸にこれからの地上波テレビの議論を進めることが必須だろうと感じた。
ローカル局問題やTverオリジナル番組など、果敢に挑戦を続けているTVerだ。こうした映像プラットフォームがオリジナルコンテンツに参入するというのは、過去の例を見ても必ずしも成功の方程式とは言えないと思う。
しかし、前述のAdRMのような動きとも関連して、オリジナル番組と超えて、映像コンテンツの新しい形の模索という視点で挑戦をしてもらいたい。
セカンドキャリア問題は前向きに考える必要がある

もう1本、どれだけ集客できるか、どんな層の参加があるのか読めなかったのが、「人生後半戦をどうやって生きる?放送・映像業界人のセカンドキャリア・サバイバル~あなたがまだ知らない、あなたの本当の労働市場価値~」という、ずいぶん長いタイトルのセッションである。
これは参加するだけで「あの人転職を考えてるらしいよ」という噂話が駆け巡りそうなので、オープンな場で行わない方がいいのかもしれないという危惧もあった。
ところが、これも実際には立ち見になってしまった。テレビ映像業界出身者が他の業界で活躍できる素養が大きいことと、それによって業界へのフィードバックも得られるという、一石二鳥な話と捉えて欲しい。
そして本セッションで気になったは、終了後にその場でパネリストに相談しに来たのが、若いテレビ局員が多かったということだ。
人材の流動性というのは放送業界は元々多くはなかったが、彼らの話を聞くと流動ではなく人材の流出になりかねないこともうっすら見えてきた。こうした放送・映像業界人ののセカンドライフというテーマはそのニーズは予想以上に深刻なで重要な問題のようである。
見えてきたテレビの未来
こうしてInternet x Media Summitでは、3日間で様々な意見をパブリック、プライベート両方で聴くことができた。今回はInteropという枠組みでの開催であるので、放送業界以外の参加者、いわゆるネット業界からの参加が非常に多い。
その中で聞こえてきたというか、現地で耳に入ってきた言葉は、「放送業界はまだこんなことを議論してるのか?」という嘲笑である。それは放送通信融合とか、放送のIP化とか、未だにそれが実現していない、あるいは議論が続いている事に関してのネット側からの評価と見ていい。
そして総論として思うことは、放送及びその周辺に関して、テクノロジーとコンテンツとビジネス両面に基づいたビジョンはどこにあるのか、どこからなら出てくるのかが見えてこない点だ。
例えば放送の未来を語る時に、表示装置やコンテンツのスタイルが、全部横長の四角いディスプレイに完パケコンテンツが出てくるという前提になっている。果たしてそうなのか。
これに対する答えは、XRやAI関連のセッションを通して見えたのではないだろうか。

