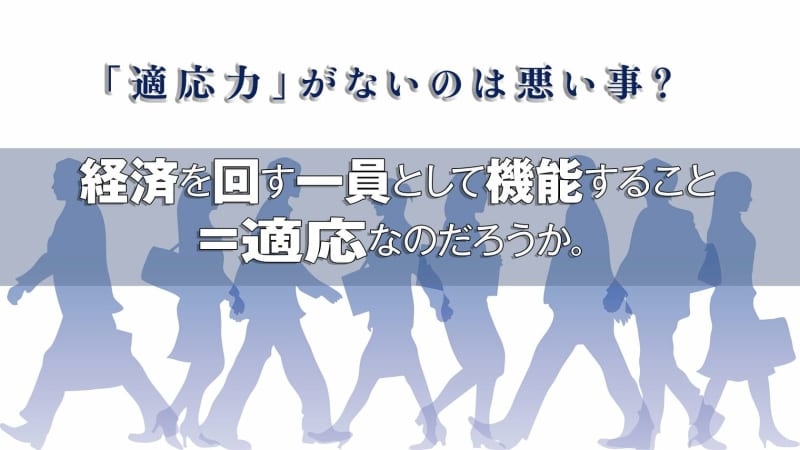
第4章 適応障害についての疑問・1
広がりを
エピソードにあげたような若者の状態は、精神障害の基準に照らすとピタッと合わない、基準に示された適応障害ではない可能性があります。
しかし普段何気なく使っている適応という語感は、仕事のみならず家事や学業などやるべきことがうまくできている状態と理解されますので、うまく行っていなければ、適応力が低い、適応がうまく行っていない、適応が障害されていると言っても違和感はないかもしれません。あの人はうまくやっているのにこの人はうまくやれていないという程度のことでしょう。
しかしこの一般的な適応に関しても、適応力がないなどと言われると短所にようになってしまいます。就活でも、適応力がない、協調性がないというのはマイナスポイントと受け止められます。
しかし他の生き物を考えると、適応できる生き物もできない生き物もいて当然です。海の生き物を陸にあげると死んでしまうし、春になると多くの人を苦しめるスギ花粉の杉も日本では北海道の名寄あたりが北限と言われています。それ以北は生えないのです。
これは仕方のないことです。人間だって得手不得手があり、その人その人のできることできないことがあっても仕方がないと思うのですが、適応力がないが悪のように取り扱われてしまうのは何とも傲慢というかきびしい感じがします。
人間が人間社会に適応するのは当然だと思われているかもしれませんが、人間社会はさまざまな側面を持ちかつ流動的に変化し続けています。それぞれの時代、地域、社会は、価値や慣習、意識も異なります。また人間の成長に伴い求められるものも変わってきますし、移動などによってもうまく適応できないことが当然起こります。
現在、うまくやれないことが適応できていないと理解されるのは、適応障害という言葉ができたからだと思いますが、病名(障害名)としての適応障害とは違いがあります。病名(障害名)としての適応障害には、診断基準があります。しかしその違いを飲み込みつつ、言葉としての適応障害は広がりを持って来ているように思います。
適応障害という呼称は、ICD、DSM以降であり、それまでわが国では精神疾患の病名としては使われていませんでした。診断基準に示されている適応障害と、一般的な感覚でとらえられる適応障害には違いがありますが、言葉としての広がりによって、ストレス因を日常生活上のことにも広げ、仕事や家事や学業などやらなければならないことがうまくできないと適応障害と表現され、認知され、治療対象になっているように思います。
何かブーメランのように戻ってきて理解が拡大された印象ですが、わが国においては仕事や家事や学業は動かし難い運命であり、それに適応することが絶対であるという前提があるのかもしれません。
確かに、一般的に仕事は適応しなければならないという大きな前提があるのでしょう。現代は働くこと=社会生活を送ることだと思われているので、働けないと社会生活上の能力に疑問符を打たれます。
うまく働けないことがひとえに適応力がない、適応障害と読み替えられてしまうのかもしれません。あたかも現代の資本主義経済を回す一員として機能することが当然のことであり、それが適応することだと考えられているかのようです。
〈ちょいたし3〉適応って、何?
辞書には大体、うまく当てはめること、生物が環境に合わせて変化することなどと書いてあります。これらは適合や順応に近く英語のAdaptationに近いのだと思います。生物や動物が環境に沿って生きることであり、変化する環境に適応できなければ死んでしまいますが、適応できれば生物学的地位(ニッチ)を獲得することになります。
精神障害の診断基準では、適応障害はAdjustment Disordersと書かれています。
屁理屈のようですが、このadjustは整える、調整するあるいは和解するなどの意味合いがあります。出来事や問題に対し自分の調整がうまく行かないことによる症状や状態が適応障害ということになります。
ここで適応とは何かという難しい問題にぶつかってしまいますが、確かにadaptationはより生物的で環境に順応し環境との相互作用で変わっていくという印象がありますが、adjustmentはより社会的で人間社会の避けがたい出来事にどう対応するかという印象があります。
※本記事は、2022年9月刊行の書籍『仕事で悩む若者は適応障害なのか』(幻冬舎メディアコンサルティング)より一部を抜粋し、再編集したものです。
