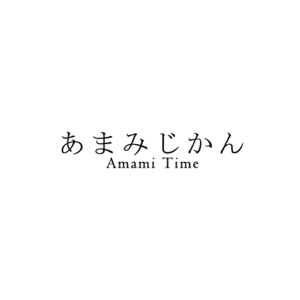奄美海洋生物研究会(興克樹会長)主催のウミガメミーティングが9日夜、鹿児島県奄美市名瀬の奄美海洋展示館であった。親子連れなど17人が参加。奄美大島で主に見られるアカウミガメ、アオウミガメの生態や、上陸、産卵状況などを興会長が説明した。近くの大浜海岸で光に向かって進むウミガメの習性を学ぶための実験も行った。
同協会は2012年に発足。ウミガメの産卵環境の保全を目的に、地元自治体や地域住民らと連携して奄美大島全域で上陸、産卵状況の調査を行っている。ミーティングは島内の産卵地などで毎年数回実施しており、観察会なども取り入れて保全への意識向上を図っている。
調査報告によると、23年の奄美大島へのウミガメの上陸は360回、産卵は260回。産卵の内訳はアカウミガメ46回、アオウミガメ157回、種不明57回で、アカウミガメの産卵回数は協会発足以来最少となった。
興会長は「ウミガメの産卵には周期があり、アオウミガメは同水準で増減を繰り返しているものの、アカウミガメは減少傾向が続いている」と説明。北太平洋では日本が唯一の産卵地であるアカウミガメの減少に危機感を示した。
ふ化したばかりの子ガメは光に寄ってくる習性があり、産卵地の街灯によって道に迷う子ガメが出ることも報告された。興さんは夜間の観察の際は影響の少ない赤色ライトを使うことや、上陸したウミガメを見つけた場合は刺激せず静かに見守ることなどを呼び掛けた。
報告の後は近くの大浜海岸へ移動。昨年8月に同海岸でふ化し海洋展示館が保護・飼育している重さ3キロ弱のアカウミガメを砂浜へ下ろし、白色ライトと赤色ライトに対する反応の違いを確認した。
龍郷町赤尾木から家族で参加した女児は「ウミガメがかわいかった」と笑顔。女児の母親は「ウミガメの生態を知り、より興味が深まった。娘にも地元で見られるウミガメに愛着を持ってもらいたい」と話していた。

実験を通して強い光に向かっていくウミガメの習性も学んだウミガメミーティング=9日、奄美市名瀬の大浜海岸