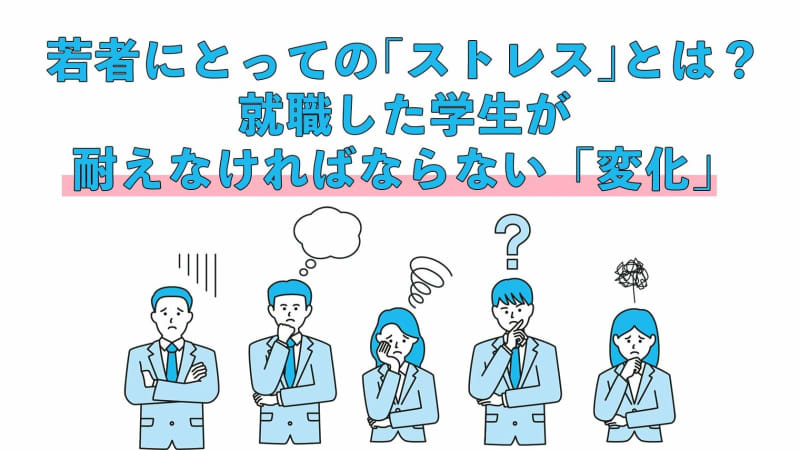
第5章 適応障害についての疑問・2
適応障害の基準と実際の状態が合っていないのではないかという疑問について考えましたが、もうひとつ単純にどうしてこうなったのかという疑問は払拭されません。多くはブラックやパワハラではなく、仕事をすることで? 何で? どこでこうなったの? という疑問です。特に年長者には疑問でしょうし、若者自身もわからないかもしれません。
適応障害はストレス因関連障害の中の一つとされており、まずはどんなことがストレスになっているかを考えます。そしてこの疑問、なぜ? に関し推察をまとめてみました。
就職という変化
まず働き始めた時、目に見える変化は生活の変化です。単身での生活は問題となりやすいです。大学進学から単身生活を始める人もいますし、就職を機に始める人もいます。どちらにおいても、数は多くないかもしれませんが、単身生活が難しいというケースが出てきます。
朝起きられない、片づけられない、ご飯を食べられない、友人を作れず孤立してしまう。親が行ってみると生活が破綻していて、連れて帰って来ることもまれにあります。自己の生活構成能力、管理能力が培われていないのです。ちゃんと食べる、ちゃんと寝て朝起きる、掃除洗濯を適宜行う、ゴミは決められたように出す、家賃や光熱費などの経費の管理を行う、単調なことの繰り返しです。
これらを通常のこととして行える忍耐力と精神力が必要です。まずこの生活の変化に耐えなければなりません。
一人暮らしの生活の変化がストレスとなる、生活自体が破綻してしまう場合や一人暮らしを継続する中で重荷になり徐々にうつ的になる場合など程度の差はありますが、他の人は乗り越えられることでも乗り越えられず支障をきたす場合はストレスとなります。
そして次に、日常の意識や構えを変えなければなりません。
朝自分で起き、多くは夕方までずっと働く。与えられた仕事を理解して行う。わからないことは聞き臨機応変に対応する。正社員であれば、与えられた仕事と他の業務との関係も理解し調整できるようにし、質問し応答しなければならず、部分的にも責任を負っていくことが期待されます。要するに仕事をするということですが、仕事は自分が意識的にしなければならないという身構えのようなものです。
自分を律して、仕事すなわち労働を行うことですが、これに対し違和感を抱く場合もあります。言ってしまえば資本主義経済の被雇用賃金労働者ですから、労働の対価として賃金をもらいます。資本主義は高校、大学でも学んだと思いますが、今ひとつ実感がない。言われたことをやる・やらないではなく、やる=できることが前提でお給料をもらうことになります。
最初からできることを期待されているとか、間違ってはいけないということではないのですが、ひとつの製品を作るにしても責任を負って作るようになることを求められます。
ですから、誰でもない自分がする、自分が働くという意識や構えが重要になります。これらの変化が求められるのだと思います。アルバイトで賃金をもらうことに多少慣れていればそのショックも少ないかもしれませんが、学生でいることと社会に出ることの構えの差が大きいのだと思います。
就職後少なくとも、これらの生活という外部的な変化と働くことの構えとしての内面的な変化に耐えないといけないのでしょう。多くの若者は就職後大急ぎでこれらの認識を変化させ、働くことに飲み込まれて行くことになります。
若者のこのような特徴がひとりでに生まれたわけではないので、育てられ方、育て方ということになりますが、これまた親だけの問題でもありません。社会全体の問題と考えたほうがよさそうです。
ひとつには、今や子どもは希少な存在で、衣食住のすべてにおいて親がしてくれて当たり前になっているでしょう。もちろんヤングケアラーのような問題もありますが、勉強することを熱心に子どもに迫る家庭では、日常生活の自立よりも勉強し1点でもテストの点数を上げることが重要課題となるでしょう。
自分のことは自分でするように練習しなければ、できるようにはなりません。勉強さえできれば、それらもできるようになるというのは間違いです。一人暮らしになった子どもの部屋を訪れ、その破綻ぶりを見て「どうしてこんなこと(生活すること)も、できないのかしら」と愕然とする親御さんもいますが、日常生活の自立はテスト勉強よりも難しいかもしれません。
自分を律して、仕事すなわち労働を行うことですが、これに対し違和感を抱く場合もあります。言ってしまえば資本主義経済の被雇用賃金労働者ですから、労働の対価として賃金をもらいます。資本主義は高校、大学でも学んだと思いますが、今ひとつ実感がない。言われたことをやる・やらないではなく、やる=できることが前提でお給料をもらうことになります。
最初からできることを期待されているとか、間違ってはいけないということではないのですが、ひとつの製品を作るにしても責任を負って作るようになることを求められます。
ですから、誰でもない自分がする、自分が働くという意識や構えが重要になります。これらの変化が求められるのだと思います。アルバイトで賃金をもらうことに多少慣れていればそのショックも少ないかもしれませんが、学生でいることと社会に出ることの構えの差が大きいのだと思います。
就職後少なくとも、これらの生活という外部的な変化と働くことの構えとしての内面的な変化に耐えないといけないのでしょう。多くの若者は就職後大急ぎでこれらの認識を変化させ、働くことに飲み込まれて行くことになります。
若者のこのような特徴がひとりでに生まれたわけではないので、育てられ方、育て方ということになりますが、これまた親だけの問題でもありません。社会全体の問題と考えたほうがよさそうです。
ひとつには、今や子どもは希少な存在で、衣食住のすべてにおいて親がしてくれて当たり前になっているでしょう。もちろんヤングケアラーのような問題もありますが、勉強することを熱心に子どもに迫る家庭では、日常生活の自立よりも勉強し1点でもテストの点数を上げることが重要課題となるでしょう。
自分のことは自分でするように練習しなければ、できるようにはなりません。勉強さえできれば、それらもできるようになるというのは間違いです。一人暮らしになった子どもの部屋を訪れ、その破綻ぶりを見て「どうしてこんなこと(生活すること)も、できないのかしら」と愕然とする親御さんもいますが、日常生活の自立はテスト勉強よりも難しいかもしれません。
※本記事は、2023年1月刊行の書籍『ラガーマン ジャッカル翔』(幻冬舎メディアコンサルティング)より一部を抜粋し、再編集したものです。
