
医師免許を持つ芸人・しゅんしゅんクリニックP。芸人として活動する傍ら、内科医・美容皮膚科医として病院に勤務する、吉本興業に所属する芸人のなかでも異色の存在だ。
体の異変を感じやすくなると言われているのが「40歳」だ。しゅんP自身も40代となったこともあり、ニュースクランチのメイン読者である40代に向けて、健康のことなどを彼の経験も踏まえて話してもらった。
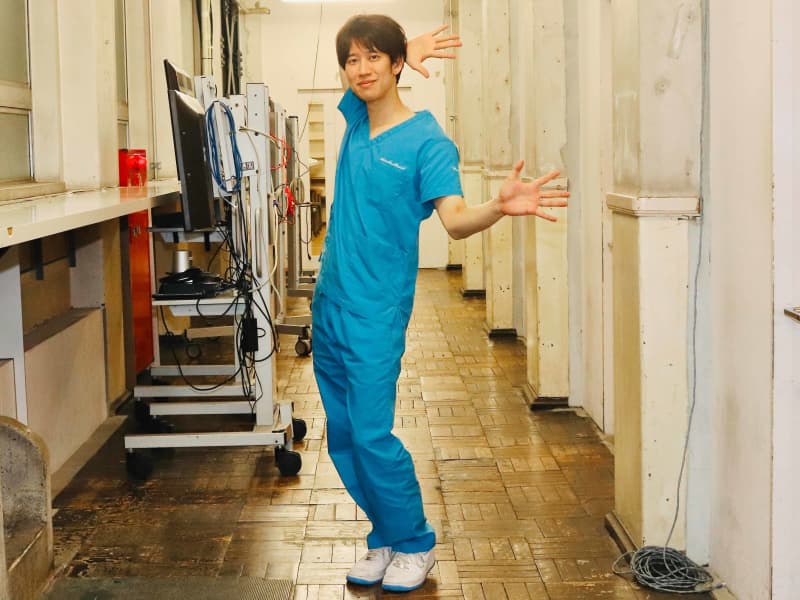
▲しゅんしゅんクリニックP【WANI BOOKS-“NewsCrunch”-Interview】
医師と芸人の自分だからこそ伝えられる
「四十不惑」という言葉があるものの、40代は健康面において怯えてくる年齢である。若いときとは違って体調の変化を実感することも多くなるだろう。
「40歳を超えると、単純に血圧が高くなりやすかったり、大腸がんのリスクが高くなったり、なんとなく“調子がマックスじゃないな”と感じる日が多くなる人もいます。
以前だったら、4~5時間の睡眠でもいけたし、“その状況でも頑張っている自分が好き”みたいなことがありましたけど、ちゃんと睡眠をとらないと、良いパフォーマンスも発揮できません。〈4~5時間“しか”寝ていない〉というマイナスのマインドにもなっちゃいますね」
では、40代に突入した人は特に何に気をつけて生活すればよいのだろうか? もちろん、生活習慣が乱れているなら改善すべきなのだが……。
「総論にはなってしまうのですが、プラスマイナスの精神で生活してほしいです。僕はケーキが好きでよく食べるんですけど、ケーキを食べたあとは体を動かしてプラスを作る。いわゆる健康的にマイナスなことをしたら、プラスになることをするよう心がけています。
とはいえ、健康を意識しすぎて好きなものを極端に控えるのはよくない。逆にストレスが溜まってしまうので、“過剰になりすぎ”にも注意が必要です。結局、(何に気をつけても)行きつくところってストレスなんですよね」
「心の不調」に年齢差は関係ない。アラフォーはもちろん、10代でも20代でも、しゅんPの助言は参考になりそうだ。メンタルが保てていないと影響が出る代表例として、仕事が挙げられる。しゅんPが勤務する病院にも、心の不調で来院する人がいるそう。
「診察をしていると、うつや適応障害の方って多くいらっしゃるんです。本当にツラくて、耐えながら仕事をやるぐらいだったら、別に辞めちゃってもいい。“我慢して仕事を続ける”という古い価値観をとっぱらって、令和的価値観も広められたらいいなと思っています」
確かに心と体が連動していないと、良いパフォーマンスは発揮できない。取り返しのつかない状況に陥る前に、どうにか対処をしておきたいものだ。
「わかりやすいところで言うと、不眠や気分の落ち込み。あと、会社に行く前や夜寝る前に涙が出てくるようであれば、絶対に受診をしたほうがいいと思います。几帳面、神経質、周りに気を遣いすぎる、自分が会社を休んだら迷惑をかけてしまう……など深く考えやすい人は、うつや適応障害になりやすい傾向にあるので、気をつけてください」
もちろん、メンタル面だけではなく、体にも目を向けなければならない。健康診断や人間ドックで自分の体のことを知る手もあるが、その際にも気をつけるべきことがある。
「40代になったら年に1回、胃カメラ・大腸カメラ・CT検査・脳のMRIなど、広くやっておいたほうがいいと思います。ただ、難しいのは、“どこまでやるか”という問題ですね。例えば、若いうちに検査をして、気にしなくてもいいものが発見されたり、ちょっとした数値の上下が逆に気になったりするので、難しいところではあります」
1983年生まれのしゅんPは、昨年40歳になった。2020年にタレントの三秋里歩と結婚し、2022年には長女も誕生。彼自身、結婚や子どもの誕生は健康に目を向けるきっかけのひとつにもなったという。
「まず見た目的なところで、娘に対して“カッコいいお父さんでありたい”と思っています。38歳で娘が生まれたこともあって、周りの若いお父さんに比べて“老けてるな”と思われたくないので頑張ろうって。それから、最近、父親が心筋梗塞になったのですが、こんなにも悲しくなるんだ……と思って、さらに健康を意識するようになりました。
もちろん、いろいろやりたいことがあるなか、病気で断念するのはツラい。運の要素が絡んではくるのですが、できる限りリスクを下げて、それでも病気なったらしょうがない、という考えです」

▲自身も40歳を迎えて心境に変化があったと語るしゅんP
『さんまのお笑い向上委員会』出演が転機に
近年、同世代の芸人からの相談も増えてきた。彼ら彼女らにとって、自分の体のことや健康診断の結果など、気軽に相談できるしゅんPは心強い存在だろう。今年の4月に発売された彼の新刊『40歳を過ぎるとなぜ健康の話ばかりしてしまうのか?』(ヨシモトブックス)のタイトルがまさにそうだ。
「お医者さんの友達って、なかなかいないでしょうし、わざわざ病院に行って気軽に相談もできない。そういうときに、この本をご覧いただきたいです。医者の友達がアドバイスをしてくれている、と思って読んでいただければ!」
医学や健康に関する本は、どこか難しいイメージがあるが、しゅんPの本は読みやすい印象があった。彼自身も明快な文章を心がけて書き上げたという。
「昔、コンビを組んでいたときに医者ネタをやったんですけど、お客さんに伝わらないことがあったんですよ。そこで噛み砕くことを意識してネタを作るようになりました。根底として“認知度を上げたい”という気持ちがあるので、みんながわかることを書かないと意味がないと思ってます」
芸人活動が執筆業にも役立ったというわけか。現在、しゅんPは曜日固定で2つの病院に勤務。空いている日にライブやメディア出演など、芸人活動をしている状況だ。そもそも、なぜ芸人になったのか。当初は医者を目指していたというが……。
「僕の父が医者で、自然と自分も医者になりたいと思っていました。父の仕事場にも行ったことがあって身近でしたし、高校の模試で志望校に早稲田や慶應を書くなか、医学部も書いていて。“なんとなく”目指した感じです」
大学時代、医者を目指すしゅんPに大きな転機があった。その出会いが彼の人生を変えることになる。
「もともと、有名人になりたい願望はありました。お笑いも好きだったんですけど、医学部に入った大学時代、当時付き合っていた彼女の影響で『爆笑オンエアバトル』とか『M-1グランプリ』を見るようになって、そこでメディアに出る前の“若手芸人”という存在を知ったんです。その姿を見て“カッコいいな”“あの世界に入りたいな”と思いました」
その後、吉本の養成所NSCに入り、ほどなくして芸人デビュー。当初はコンビを組んでいたが解散し、ピン芸人として劇場に立っていた。
そして、医者あるあるをメロディーに乗せて歌い踊る「ヘイヘイドクター」で爆笑をかっさらい、『さんまのお笑い向上委員会』(フジテレビ系列)のモニター横芸人としてブレイク。彼自身も、同番組への出演は大きかったと振り返る。
「芸人として、完全にターニングポイントになった番組です。ただ、自分としてもウケたなとは思いつつも、手応えを感じたかと言われると、なんとも言えない状態。そんなときに、他の芸人のチーフマネージャーさんから“(今後に向けてネタを)用意しとけよ”と声をかけられて……“あるかもな”と思いました」

▲『さんまのお笑い向上委員会』が芸人としてのターニングポイント
番組出演をきっかけに、しゅんPの知名度は飛躍的に上がった……が、こんな悩みも。「医者芸人」として注目をしてもらったものの、自身としては“医者と名乗っていいのか……”という葛藤があったという。
しゅんPは、大学を卒業後に2年間研修医として働き、NSCに入学した。初期臨床研修でさまざまな科を回った経験はあるものの、いわゆる専門医として働く普通の医師とは違う道を歩んできた。
そうした後ろめたさがあるなか、現在働いている病院『埼玉みらいクリニック』の岡本宗史先生から誘いがあり、医師として働くことになる。
「最初は、医者芸人と名乗ることに躊躇していたんですけど、病院で働くようになったことで、“医者芸人と言っていいのかな”と思えるようになりました。岡本先生にはすごく感謝しています」
医師×おばあちゃんの相性抜群ユニット
近年は新たな挑戦も。現在77歳の“若手芸人”おばあちゃんと一緒に、ユニット「医者とおばあちゃん」を組んで賞レースに挑んでいるのだ。おばあちゃんは、高齢ながら若手芸人がしのぎを削る劇場『神保町よしもと漫才劇場』で、レギュラーメンバー入りした異色のピン芸人。
「本の編集者さんに、おばあちゃんと接する際は、大きな声を出す・段差に気をつける・遅い時間にネタ合わせをしない・なるべく向こうの家に行く、などを気をつけていることを話したら、“すごく面白いですよ”と言われて、“これって面白いことなんだ”と気づきました。僕としても、おばあちゃんと話していると“医者って傲慢だったな”とか“患者さんってそんなこと思ってたんだ”とか気づけて、勉強になるんですよ」
おばあちゃんと今後どんな活動をしていきたいのか。
「M-1はもちろん、テレビでも漫才をしたいです。おばあちゃんとの漫才は、高齢者の方が見ても面白いあるあるが詰まっているので、老人ホームや病院でネタをして、笑っていただきたいという夢があります。おばあちゃんの話をみんなに聞いてほしいですし、それを見て元気になってほしい。僕らの漫才を見て元気になってくれたら、日本を活気づけられるんじゃないかなと思います」
(取材:浜瀬 将樹)

