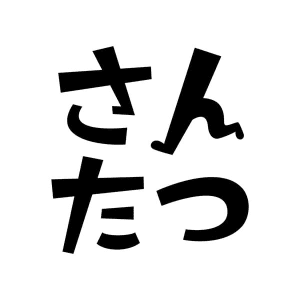前回に引き続き、2024年5月に大阪を空撮した際、市内中心部で出合った廃なるものを紹介します。後半の今回はレンガ建築の建物です。場所は大阪城の北西、お堀と寝屋川が接近するあたりです。そのような場所に、廃墟となって草むしている建物がひっそりと残っています。
大阪中心部のビル街にどどんと構える大阪城。伊丹空港へ着陸する旅客機の左窓からでも、その勇姿はしっかりと見えます。「ナニナニ何個分」の広さというのはピンとこないですが、野球場やサッカー場が、余裕で10以上並べられるほどの広さがありますね。
このエリアを空撮するときは、旅客機の着陸の合間に行います。
空港管制圏内の申請や、管制官との調整はパイロットを通じて行い、念入りに事前の準備をするのですが、それでも実際に飛行して旅客機が近づいてきたら離れなければなりません。すんなり時間通りに撮影できない、空撮にとってはシビアな場所です。
広大な公園は巨大な兵器工場だった

私のように空撮を生業としている人にとっては、「ああ、このエリアか……」と渋い顔をしてしまう場所。今回の空撮でも渋い顔をしながら、タイミングよく飛行できますようにと願うばかりでした。

当日は飛行の調整と進入の許可が滞りなくでき、すんなりと大阪城の上空へ。ちょっと珍しいくらいのタイミングの良さでした。
眼下に広がる広大な森とオフィス街は、80年ほど前まで兵器工場だったなんて、にわかに信じられません。上空からその遺構を捉える前に、少し歴史を紐解きましょう。
大阪城は、明治時代になると広大な敷地が政府に活用されました。1870年(明治3)に三の丸だった場所に「造兵司」が設置。造兵司は1879年(明治12)に大阪砲兵工廠となり、組織改変により陸軍造兵廠大阪工廠、大阪陸軍造兵廠となりました。
造兵廠は現在の大阪城ホールの場所を中心にして敷地があり、徐々に拡大されていきました。主に陸軍の砲弾を研究製造し、大阪の兵器製造拠点となっていたため、終戦前日の8月14日空襲によって隣の京橋駅とともに壊滅的な被害を受け、多数の死傷者が出てしまいました。

造兵廠の敷地跡は、戦後約80年の月日のなかで、公園化、大阪城ホール建設、オフィス街へと変貌し、広大な兵器工場であった面影はほぼありません。とくに大阪城ホールの場所には、1873年(明治6)建築の造兵司本館があって戦後も残されてきましたが、1981年(昭和56)に大阪城ホール建設のために解体されました。
天守閣を望む緑茂る公園は、終戦まで砲弾を作っていた。そんなことはもう忘れかけているようにも思えます。私も、約30年前の大学時代は大阪に住んでいたのに、造兵廠の存在は知識として知るくらい。大阪城公園には部活動で訪れたこともあるのに、戦跡を調べることはありませんでした。
唯一残っている建物は旧化学分析場
造兵廠の痕跡(遺構)はほとんどが消えてしまいましたが、一部は残されています。一つは大阪城ホールと少年野球場の北側。第二寝屋川の川縁に水門が口を開けています。水門は工廠への水路出入り口となっていました。水路は埋め立てられましたが、石造りのアーチが残されています。

もう一つ残されているのは、今回のメインとなるレンガ建物で、旧化学分析場と呼ばれるものです。寝屋川とお堀(北外濠)に挟まれた細長い敷地に、その建物は存在します。
ネオ・ルネッサンス様式、地下1階と地上2階建てのレンガ造りで、1919年(大正8)に建設されました。
随所に意匠が散りばめられたデザインは、分析場というより学校のような雰囲気です。中心部から左右対称の構造で重厚。兵器の開発や実験に使われていた建物で、戦後は国の施設として活用され、最終的には自衛隊の庁舎となっていました。本館が解体されたいま、造兵廠最大の遺構となります。
京橋口交差点から大阪城公園の道へ入ると、造兵廠表門のレンガ積みが目に入り、前方右手にはレンガ建造物の小さな建屋が。
この建屋は便所だったようです。旧化学分析場は低い柵で覆われて近づけないですが、全体像を拝むことはできます。

再び、上空から見てみましょう。旧化学分析場のある場所は、寝屋川と北外濠に挟まれていて、「なぜこんな猫の額のような場所に建てたのだろう?」と疑問が湧きました。この場所になった理由は定かではありませんが、造兵廠自体が外濠と寝屋川に挟まれた土地に、ところ狭しと工場が並んでいたので、他に場所がなかったのかもしれません。

異空間のように緑で覆われる遺構
空港の管制官から許可をもらったとはいえ、ずっと大阪城の上空に滞空することはできません。短時間で撮影してこのエリアから離脱します。
旧化学分析場の建物はネオ・ルネッサンス様式とのことですが、上空からだと、正直その優雅な意匠のレンガづくりの魅力がよく分かりません。「なんだ、せっかく高いお金出して飛行したのにもったいない、ネオ・ルネッサンスの魅力が撮れないのか?」と思われるかもしれませんが、その美しさは半分以上が緑で覆われてしまっていたためよく見えないのです。
建物はどこだろう?と一瞬分からなくなってしまうほど、蔦、低木、木々にのまれています。寝屋川の壁面などは、成長した木が建物を覆いつくしていました。

辛うじて公園道路側の正面の壁面は、蔦と低木に同化しつつありながらレンガ色の壁面と意匠が見え、かつての威厳が残っています。とはいえ正面入り口は完全に低木で遮られ、瀟洒なアーチが見えません。



周りはすっかりとオフィス街へと開発しつくされ、すぐ隣には立派な高層ホテルも建つ環境で、手付かずのまま自然へとのまれつつある……。実際にこの目で見ると、旧化学分析場は現実の姿なのか、これは異空間なのではないかと疑ってしまうほど、そこだけ不思議な空気が流れているようでした。
上空からでもそう感じるのだから、地上で公園道路から眺めるとなおさら引き込まれると思います。昭和末期や平成初期までは、このような廃墟は都心部にも点在していましたが、いつの間にか消えていきました。



造兵廠は終戦前日の空襲で甚大なる被害と犠牲者が出てしまいましたが、旧化学分析場が将来に渡って、この姿のままで歴史を語っていくことを願ってやみません。
取材・文・撮影=吉永陽一
吉永陽一
写真家・フォトグラファー
鉄道の空撮「空鉄(そらてつ)」を日々発表しているが、実は学生時代から廃墟や廃線跡などの「廃もの」を愛し、廃墟が最大級の人生の癒やしである。廃鉱の大判写真を寝床の傍らに飾り、廃墟で寝起きする疑似体験を20数年間行なっている。部屋に荷物が多すぎ、だんだんと部屋が廃墟になりつつあり、居心地が良い。