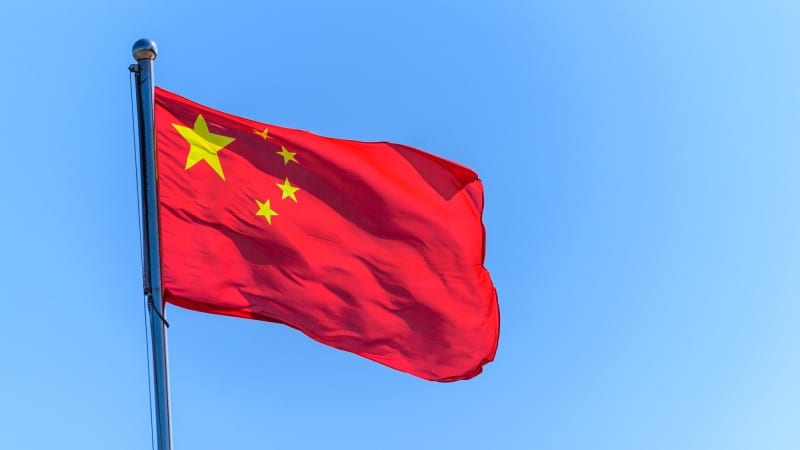
ロシアによるウクライナ侵攻、中東ではイスラエルによるガザ地区への攻撃など、国際情勢が物流に影響を与え、各国のインフレ率を直撃している。
私たちが“投資”を考えるときに、こうした地政学的な知見も、今後の経済情勢を予想するために重要になる。
経済評論家・上念司さんの著書『経済学で読み解く 正しい投資、アブない投資』(扶桑社)から、「なぜ中国共産党は不良債権処理に及び腰なのか」について一部抜粋・再編集して紹介する。
中国の経済の自由化は期待できない
現在、中国共産党は政治的にも経済的にも巨大な権力を握っていますが、経済の自由とはその巨大権力を民衆に明け渡すことを意味します。
そんなこと認めるわけがないですよね?
中国は共産党が永久に統治する。そう思っているに違いない。だとすると、中国における経済の自由化は全く期待できません。
中国経済は中所得国の罠にハマって今後、長期停滞に陥る可能性が高いです。それはつまり、ハル・ブランズが指摘する「チャイナピーク論」にピタリと一致しています。
だからこそ、非常に危ない。まさに「デンジャー・ゾーン」。
とはいえ、これはあくまでも政治的な理由です。
経済的な面からも中国の不良債権処理が進まず、経済の自由化が難しい理由について考察してみたいと思います。
将来に不安を抱くと人は何をする?
不良債権を積極的に処理せず、住宅価格も大して調整しないということは、表面上は緊急事態が起こっていないという設定です。
そのため、家を買った人は住宅ローンを払い続けなければなりません。
しかし、よく考えてください。
そのローンの残高は住宅バブルのピークでつけた価格に対するローン残高です。トンデモない高値摑みの金額ですよね。
まして、住宅バブルは崩壊しているので物件を転売してもローンは返せません。下手すると借金だけが残ります。
当然、人々は将来の見通しに不安を抱きます。そういうとき、人はなにをするでしょう?日本でもそうでしたよね?
そういう状況に陥ったら、多くの人は消費を切り詰めて、借金返済を優先します。
しかし、みんながこれをやってしまうと、当然消費は低迷します。結果として景気が悪くなる。
景気が悪いと将来に対する不安もさらに膨らんで、人々はますます消費を切り詰めて借金の返済や貯蓄に走る。まさに悪循環!
日本で起こっていたことが中国でも
実はこれが1990年代の日本で起こったことです。いわゆる「バランスシート不況」と呼ばれる現象です。
中国の庶民は貯金の代わりに住宅を買って、バブル期はその含み益で遊んでいました。ところが、含み益が含み損に転じると経済が逆回転し始めます。
含み損が消えない限り、消費の切り詰めは終わらず、景気は低迷したまま。
とはいえ、不良債権処理をすることは、借金の担保になっている不動産の価値がないことを認めることでもあります。
それは、銀行にとって貸した金が返ってこないリスクを公認することでもあります。
不良債権処理とは、こういったリスクを正しく査定し、破綻先、破綻懸念先、健全先といった分類をすることから始まります。
こうすることで銀行はお金を貸してみたけど返ってこない金額を推計できるわけです。
その推計が完了したら、もう返ってくる見込みがない債権は債権回収業者に売り飛ばし、特別損失を計上してバランスシート(貸借対照表)から除外します。
その結果、バランスシートに大穴が開いたら、最後は政府に救ってもらう。いわゆる公的資金注入というやつです。
日本はバブル崩壊から12年かけてこれをやり遂げました。中国にそれができますか?大きなリスクですよね?
なぜなら、不良債権を処理して競売にかけたら、モノによっては二束三文になってしまうわけです。たとえば、額面金額の100分の1とかはザラです。
それでも銀行は政府に補塡してもらえるからいいとして、一般庶民はどうでしょう?
貯金のつもりで買った不動産が二束三文だったら怒りの矛先はどこに向くのか。もう答えはおわかりですよね?
突然、不動産に価値がなくなったら…
ここで私の経験をお話しします。
1998年、29歳にしてマイホームを買った私は4000万円もの住宅ローンを組みました。買ったお家の値段は土地代込みで5000万円。
ところが、サラリーマンをやめて起業することに伴いこの家を売ることになりました。
2002年に無事売れましたけど、売れた値段は3750万円。差し引き1250万円の「減損」を食らいました。怒りのやり場に困りましたよ。選挙では民主党に入れたかもしれませんね(笑)。
私の場合は家を売ったのでこの損失が現実化しましたけど、売らなかった人だって同じ目に遭っていたわけです。
バブルの崩壊過程で、高値摑みしたマイホームの住宅ローンを支払うために生活を切り詰めて返済していたわけですから結局同じです。
不良債権処理は全員の借金を帳消しにする徳政令とは違います。厳格な査定に基づいて、法的に整理するわけです。絶対に巻き込み事故が発生します。そして、被害者は国民全員です。
なぜなら、借金の肩代わりをするのは一義的には政府ですが、その政府は国民の税金によって支えられているからです。要は国民全員で負担しているのと同じ。しかも、ポイントは借金をして家を買った人ほど負担が重いという点です。
私は若い頃に期せずしてその重みを実感するイベントを経験してしまいました。
中国共産党が不良債権処理に及び腰な理由はまさにこれです。ある日突然、貯金の代わりだと思っていた不動産の価値がなくなったら中国人民はどう思うでしょう?
日本のように民主主義の国なら政権交代というかたちで与党におきゅうを据えてストレス解消することができます。
ところが、中国には選挙がない。共産党は常に正しいことをやっているという「設定」になっています。こうなると人々は暴力によってしかそのストレスを解消することができません。
上念司
1969年、東京都生まれ。中央大学法学部法律学科卒業。在学中は創立1901年の日本最古の弁論部・辞達学会に所属。日本長期信用銀行、臨海セミナーを経て独立。2007年、経済評論家・勝間和代氏と株式会社「監査と分析」を設立。取締役・共同事業パートナーに就任(現在は代表取締役)。2010年、米国イェール大学経済学部の浜田宏一教授に師事し、薫陶を受ける。金融、財政、外交、防衛問題に精通し、積極的な評論、著述活動を展開している。

