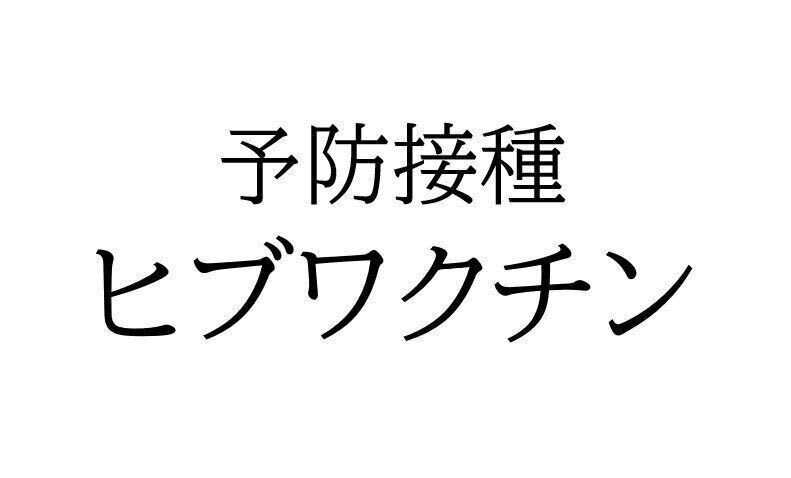
ヒブワクチンは1回目の接種月齢により接種回数や間隔が異なるため、受け方を迷うママやパパも少なくないでしょう。小児科医で神奈川県衛生研究所 所長多屋馨子先生に、ヒブワクチンの受け方や副反応などについてと、ヒブによって発病する細菌性髄膜炎について解説してもらいました。
なお、2024年4月からヒブ、百日せき、ジフテリア、破傷風、ポリオのワクチンを混合した五種混合ワクチンが定期接種で使われています。このワクチンで受ける場合は、1回目の接種月齢に関係なく4回接種になります。
五種混合ワクチン/5種類を合わせた混合ワクチン。5つの病気の免疫をつけることができます
ヒブワクチンは命を落とすこともある細菌性髄膜炎から赤ちゃんを守る
・定期接種
・不活化ワクチン
・皮下注射
ヒブが原因の細菌性髄膜炎は、0才代後半に発病することが多い病気。細菌性髄膜炎は高熱、けいれん、意識障害など重症になりやすく、後遺症が残ったり、最悪は命を落とすこともあります。そのため、WHO(世界保健機関)は最重要ワクチンの一つとしており、すべての国で定期接種にすべきだと勧告しています。
ヒブワクチンは2ヶ月から接種できるので、感染リスクが高くなる6ヶ月までに3回の接種を済ませ、免疫をつけるようにしましょう。
【予防接種の受け方と時期は?】4回接種することで発症リスクの高い時期をカバーします
ヒブワクチンは2ヶ月から接種でき、4回の接種で発病しやすい時期をカバーします。6~11ヶ月が最も発症しやすいため、早めに接種を始めましょう。
なお、ヒブワクチン単独で受ける場合は、1回目に接種した月齢により接種回数や間隔が変わるので注意が必要です。五種混合ワクチンで受ける場合は、1回目の接種月齢に関わらず4回接種です。
1回目の接種月齢・年齢とその後のスケジュール(ヒブワクチン単独で受ける場合)
[2ヶ月~6ヶ月]…4回接種
1回目から4(医師が必要と認めた場合、3)~8週空けて2回目
2回目から4(医師が必要と認めた場合、3)~8週空けて3回目
3回目から7~13ヶ月空けておおむね1年後の1才代早期に4回目
[7ヶ月~11ヶ月]…3回接種
1回目から4(医師が必要と認めた場合、3)~8週間空けて2回目
2回目から7~13カ月空けておおむね1年後に3回目
[1~4才]…1回接種
※ヒブワクチンを単独で受ける場合は、5才以上の場合は定期接種としては接種できません(なお、長期にわたり療養を必要とする病気にかかった子の場合、10才に達するまでは接種可能)。五種混合ワクチンで受ける場合は、生後90ヶ月未満であれば、定期接種として受けることができます。
【おすすめの受け方は?】ほかのワクチンとの同時接種を検討しましょう
ヒブワクチン単独で受ける場合は、ロタウイルス、B型肝炎、肺炎球菌、四種混合ワクチンとの同時接種もできます。五種混合ワクチンで受ける場合は、ロタウイルス、B型肝炎、肺炎球菌ワクチンとの同時接種が可能です。
【効果の持続期間は?】4回の接種でしっかり免疫がつきます
4回の接種で発病しやすい時期をカバーします。発症リスクが高い6~11ヶ月に免疫を得られるように、早めに接種を開始することが大切です。5才以降になると、ヒブによる重症感染症は少なくなります。
【副反応は?】接種部分が腫れたり、熱が出たりすることがありますが、通常1~2日で治まります
接種した部位が赤くなる、腫れて痛む、発熱する、機嫌が悪くなるなど、軽度の副反応がまれに見られることがあります。しかし、いずれも多くは1~2日で自然に治まります。
重度の副反応は報告されておらず、安全性が確立していますが、高熱が出るなど気になることがあれば、予防接種を受けた病院を受診してください。
ヒブ感染症はどんな病気?
・かかりやすい季節は?…とくになし
・かかりやすい年齢・月齢は?…0~5才
・主な症状は?…発熱、嘔吐、けいれん
・感染力は?…病気が周りの人に感染することはありませんが、飛沫感染で保菌者になります
・ママからの移行免疫は?…3ヶ月ごろまで有効
ヒブ(インフルエンザ菌b型)が原因の感染症。ヒブは健康な人の鼻やのどに常在していますが、菌が血液中に入り込むと、体中のいろいろなところに炎症を起こします。脳を包む髄膜に菌が入り込んで炎症を起こすのが髄膜炎で、ヒブワクチンの接種が始まる前は、赤ちゃんの細菌性髄膜炎の約60%はヒブによって引き起こされていました。
3ヶ月ごろから発症する子が出てきて、ピークは6~11ヶ月。2才ごろまでに多く発症しますが、5才ごろまではかかることもあります。
なお、今は、ワクチンの効果でヒブ感染症は激減しています。
【症状・経過は?】初期症状は風邪の症状と似ているので、悪化するまで診断がつかないことも
細菌性髄膜炎は発熱、嘔吐などの症状が風邪の症状と似ていて、初期は血液検査に変化が出ないなどの理由で、早期発見が難しいのが特徴。症状が進んでけいれんや意識障害が出てきて、初めて診断がつくことも珍しくありません。
診断がついたらすぐに入院して抗菌薬などで治療しますが、適切な治療を行っても死亡したり、後遺症が出たりすることがあります。抗菌薬が効きにくい耐性菌の増加も問題になっています。
【合併症・後遺症は?】脳に重い後遺症が出る割合は15~20%
●合併症
けいれんや意識障害が出たり、髄膜だけでなく脳の中にも膿がたまる脳膿瘍、脳室が拡大する水頭症、くも膜と硬膜との間に髄液・血液・浸出液などが貯まる硬膜下水腫、てんかんを引き起こしたりすることがあります。敗血症(細菌による炎症が全身に広がり、臓器障害が起きて重篤になった状態)になることもあります。
●後遺症
治っても脳に重い後遺症が出ることがあります。主に発達や知能、運動の障害や難聴が残ります。後遺症が出る割合は15~20%です。
【患者数・罹患率は?】ヒブによる髄膜炎の発生は激減しています
ヒブワクチン導入前の日本では、年間約600人がヒブによる重い細菌性髄膜炎になっていました。しかし、2011年からヒブワクチンの費用助成が始まるとともに細菌性髄膜炎の発生率は減少。13年度から定期接種となり、14年度以降、ヒブによる細菌性髄膜炎は激減しています。これは、ワクチンによる予防効果だと考えられます。ヒブは莢膜(きょうまく)※がb型のインフルエンザ菌で、ワクチンが開発される前は、最も多かったのですが、最近はワクチンの効果でb型は激減し、b型以外のインフルエンザ菌や無莢膜型のインフルエンザ菌による感染症の報告が多くなっています。
※莢膜:細菌の外側にある多糖類の厚い層
ヒブによる細菌性髄膜炎は早期の診断が難しく、重い後遺症が出る確率も高い非常に怖い病気です。6ヶ月になるとヒブによる細菌性髄膜炎が増えるため、それまでに十分な免疫をつけることが重要。2ヶ月から接種を始め、6ヶ月までに3回の接種を終わらせるようにしましょう。
情報提供/多屋馨子先生
取材・文/東裕美、ひよこクラブ編集部
●記事の内容は掲載当時の情報で、現在と異なる場合があります。
※記事の内容を一部修正しました(2023年3月)
