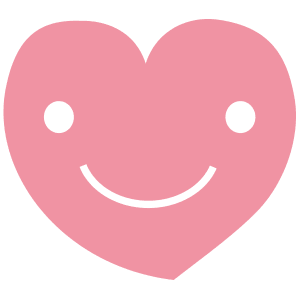厚生労働省が令和6年6月14日に発表した令和6年第23週(6/3-9)の「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況について」によると、全国の定点当たり報告数は3.99。数値としてはまだ低いものの、5週連続で増加しています。都道府県別では、36の都道府県で増加しています。定点当たり報告数では沖縄は19.58、5週連続で10を超えています。そのほか鹿児島8.73、北海道6.67、千葉5.56、宮崎5.38、埼玉4.91、佐賀4.90、愛知4.72で多くなっています。また、気がかりなのは、KP.3と呼ばれる新たな変異株の検出が増加していることです。現状について、感染症に詳しい医師を取材しました。
【2024年】6月に注意してほしい感染症!溶連菌感染症高水準維持 手足口病・咽頭結膜熱と言った夏の感染症に注意 医師「マイコプラズマ肺炎徐々に増加」
感染症に詳しい医師は…
感染症に詳しい大阪府済生会中津病院院長補佐感染管理室室長の安井良則医師は、
「新型コロナウイルス感染症の患者は徐々に増えていますが、今は梅雨時で湿気が高く、あまり流行に適している気候とは言えないので、すぐに急増することはないと思っています。ただ、去年もそうでしたが梅雨が明ける7月から8月には患者数が増加するのでないかと予測しています。流行の規模については、まだなんとも言えない状況です」と語っています。
新型コロナウイルス感染症とは?
新型コロナウイルスは感染者の口や鼻から、咳・くしゃみ・会話のときに排出されるウイルスを含む飛沫またはエアロゾルと呼ばれるさらに小さな水分を含んだ状態の粒子を吸入するか、感染者の目や鼻、口に直接に接触することにより感染します。一般的には1メートル以内に近接した環境において感染しますが、エアロゾルは1メートルを超えて空気中にとどまりうることから、長時間滞在しがちな、換気が不十分で混雑した室内では、感染が拡大するリスクがあることが知られています。感染すると2〜7日の潜伏期間のあと、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、咳といった上気道症状に加え、倦怠感・発熱・筋肉痛・頭痛といった全身症状が生じることが多く、その症状はインフルエンザとよく似ています。オミクロン株が主流となった現在は、嗅覚・味覚障害の症状は減少しています。軽症の場合は1週間以内に症状が軽快することが多い一方、発症から3か月を経過した時点で何らかの症状が2か月以上持続し、他の疾患による症状として説明がつかない場合には、罹患後症状(後遺症)の可能性を考える必要があります。
新たな変異株KP.3が急増
国立感染症研究所感染症疫学センターでは、新型コロナウイルスに関するデータを発表しています。第18~21週にかけての調査では、その期間に検出した新型コロナウイルスはBA.2系統が75.37%。特にKP.3という株が54.48%と最も多くなりました。KP.3は今年の3月頃から急増しています。世界的に見てもKP.2、KP.3は増加傾向にあるということですが、既存の亜系統と比較して公衆衛生的なリスクに変化はないとされています。
安井医師は「KP.3はオミクロン株の一種で、以前に流行したBA2.86から派生した株です。ワクチンや感染による中和抗体による免疫からの逃避の可能性が高く、感染しやすいというBA2.86の特徴はそのまま引き継いでいるものと思われます。また、発症しても症状には大きな違いはないと思います。とはいえ、新型コロナウイルス感染症による入院患者は高齢者が多く、特に感染した場合のリスクが高い方やその周りの方たちは、予防に十分留意していただければと思います」としています。
入院患者のおよそ半数が80歳以上の高齢者
厚生労働省のデータによると、今年の新型コロナウイルス感染症による入院患者の届け出数は49,623人。そのうちおよそ半数の24,282人が80歳以上の高齢者、70代の方は11,921人となっています。「3密」の回避、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒、部屋の換気など、予防対策を引き続き行ってください。
引用
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況について令和6年第23週(6/3-9)、新型コロナワクチンQ&A、新型コロナワクチンについて
国立感染症研究所感染症疫学センター:新型コロナウイルス感染症サーベイランス月報発生動向の状況把握2024年5月
取材
大阪府済生会中津病院院長補佐感染管理室室長 安井良則氏