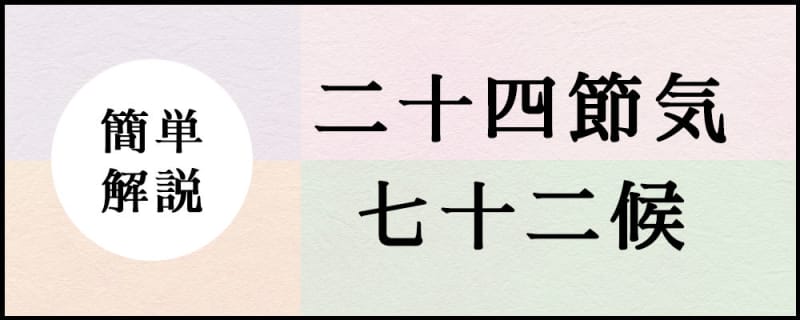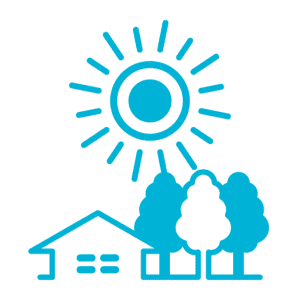二十四節気「夏至」の意味
夏至(げし)とは、日本を含む北半球で、一年の中で最も昼の時間が長く、夜の時間が短くなる日です。本格的な夏の始まりを意味し、この日を境にだんだんと日が短くなっていきます。
かぼちゃを食べたり柚子湯に入ったりする“冬至(とうじ)”のような風習はあまりありませんが、関西ではタコがよく食べられます。
夏至の七十二候
・ 初候:乃東枯(なつかれくさかるる) 6月21日~6月25日頃

乃東(なつかれくさ)は、夏枯草(かこそう)ともいい、ウツボグサのことです。シソ科ウツボグサ属に分類され、初夏の頃から紫色の花が咲き始めます。花が終わる頃になると褐色に変化し、褐色になり始めた花は、うがい薬などの薬に使われます。
・ 次候:菖蒲華(あやめはなさく) 6月26日〜7月1日頃

菖蒲(あやめ)は、しょうぶとも読みますが、あやめはアヤメ科、しょうぶはショウブ科ですので、漢字で書くと同じでも、実際は異なる植物です。あやめは花びらに網目模様があるのが特徴で、“文目”や“綾目”と書くこともあります。乾燥した場所を好んで咲きます。
・ 末候:半夏生(はんげしょうず) 7月2日~7月6日頃

半夏とは、烏柄杓(からすびしゃく)というサトイモ科の薬草のことです。日本では北海道から沖縄まで広く分布し、6~8月にかけて花が咲きます。
雑節の“半夏生(はんげしょう)”もこの七十二候がもとになっていて、こちらは夏至から数えて11日目の7月2日頃から七夕までの5日間です。
この時期に使える時候の挨拶
時候の挨拶とは、手紙などの最初に書く季節を表す言葉や挨拶文です。
さまざまな表現がありますが、6月下旬~7月上旬にかけて、よく使われるものをいくつかご紹介します。
① 夏至(げし)の候
夏至の頃となりましたね~という意味です。
二十四節気の夏至から次の節気の小暑(しょうしょ)の前日まで使うことができます。
② 短夜(みじかよ)の候
夏至を迎え、昼が長く、夜が短くなりましたね~という意味です。
6月の中旬から下旬の夏至の頃によく使われる挨拶です。
③ 長雨(ながあめ)の候
雨の続く季節になりましたね~という意味です。
6月中旬から7月上旬の梅雨の時期に用いられ、梅雨明け前まで使うことができます。
④ 小夏(こなつ)の候
小夏は夏の半ばを表し、夏本番を前に汗ばむようになってきましたね~という意味です。
6月中旬頃から7月上旬にかけて使われる挨拶です。
⑤ 桜桃(おうとう)の候
桜桃とはさくらんぼのことで、さくらんぼのおいしい時期となりましたね~という意味です。
桜桃は、旧暦5月の仲夏(6月5日頃~7月4日頃)の季語で、その時期に使える挨拶です。
二十四節気や七十二候については、こちらのページでも解説しています。