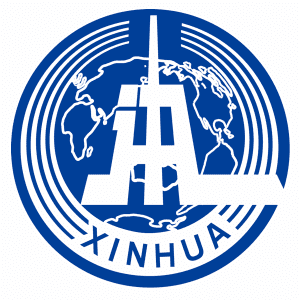【新華社淮南6月20日】中国でこのほど、2千年以上前の打楽器、青銅編鐘(へんしょう)で演奏された民謡「茉莉花」が公開され、多くの人が澄んだ調べに聴き入った。編鐘は安徽省淮南市で現在も発掘が進む戦国時代・楚国の武王墩(ぶおうとん)墓で出土。考古研究者の測定で音階が揃っているのが分かった。
春秋戦国時代に楚国は中原の「八音」(楽器の主要部の素材により分類した8種類の楽器)を継承しただけでなく、自らの想像力とロマンを伝統楽器に込めた。大まかな統計によると、武王墩墓からは3種類100点以上の音楽関連遺物が見つかっている。
武王墩墓でかつて出土した「漆木虎座鳥架懸鼓」は台座に虎、枠に鳥をかたどった楚地特有の楽器で、湖北省や河南省などの楚国貴族墓でも見つかっている。武王墩墓のものは残存部分だけで高さが1.92メートルあり、これまでで最大の大きさを持つ。
湖北省荊州市の荊州文物保護センターの漆木器保護室では、武王墩発掘プロジェクト実験室の温婧琦(おん・せいき)さんが、墓で見つかった琴や瑟(しつ、大型の琴)などの弦楽器、笙(しょう)や竽(う)など管楽器の破片を整理していた。瑟は最も長いもので本体の長さが約2.1メートルあり、ほぞに絹弦の跡が残っていた。笙や竽などは吹嘴(マウスピース)や笙斗(気室)、苗管(竹管)、簧(リード)が見つかっている。
漆木虎座鳥架懸鼓はかつて盗掘で持ち出され、後に回収されたが、同時に回収された「内楽虎座」は虎の背中部分に長方形の穴がある編鐘の台座で、虎の腹と胸に「内楽」の銘文が刻まれている。専門家によると、秦から漢初の時代には社(やしろ)や宗廟の祭祀(さいし)の音楽を司る人を「外楽」、宮殿や宴会の音楽を担当する人を「内楽」と呼んでいた。
武王墩では、墨書の中に「楽府」の2文字があり、椁室(かくしつ、棺をおさめた部屋)内に対応する楽器が置かれていた。この発見は、音楽を司る役所「楽府」の設置時期を秦代から戦国時代にさかのぼらせた。
武王墩墓出土の楽器は、当時の中国人の風雅な趣、中華文明の足跡、文化の脈動を今に伝えている。(記者/陳諾、劉美子、屈彦、白斌)