
気候変動に取り組む民間団体「気候変動イニシアティブ(JCI)」は、企業や自治体、NGO・NPOなどさまざまな団体が参加し、1.5度目標の達成に向けて連携して取り組んでいる。積極的に行政に働きかけ、グローバル市場での日本企業の「競争力」を高めることが目標の一つだ。共同代表を務める加藤茂夫氏は、リコーの執行役員サステナビリティ推進本部長として、当時の経営層と共に、日本企業の中でいち早くサステナビリティを推進してきた経歴を持つ。「化石燃料からの脱却を加速させなくては、日本は取り残される」と語る加藤氏に、JCIの活動や日本社会が目指すべき脱炭素の取り組みについて話を聞いた。(松島香織)
――加藤さんはリコーの執行役員として長らくサステナビリティに従事され、日本企業の中でも先進的な取り組みをされてきました。JCIで活動されるきっかけについて教えてください。
加藤:私はリコーで、2015年のパリ協定以降、環境経営やESG経営統合に邁進していました。当時、国連気候変動枠組条約締約国会議(COP)などに参加する中で、社会システムの変革を求められてきていることを肌で感じ、同時に、一社ではできないことがたくさんあると考えていました。
UN環境計画特別顧問の末吉竹二郎先生も同じように考えられていて、企業だけではなく自治体、NGO・NPOなども含めた団体と、民間レベルで気候変動に取り組む組織が必要だという機運が高まり、同じ思いを持つ仲間たちが集って、切磋琢磨しつつ脱炭素社会の実現を目指したJCIを2018年7月に立ち上げました。
参画には、1.5度目標に沿った脱炭素の取り組みをコミットしているとか、RE100/SBTなどへの参画という条件がありますが、当初は105団体だったのが、現在約800団体になりました。東京都、横浜市、京都市などの自治体や、企業ではソニーグループなどの大企業から中小企業、教育機関やシンクタンクなど、いろんな方々に集まっていただいています。
――JCIは、2023年12月にカーボンプライシングの導入を提言されていますね。カーボンプライシングは、企業にとってコストアップになるなど、不利な点があるのではないかと思いましたが、提言の背景には何があったのでしょうか。
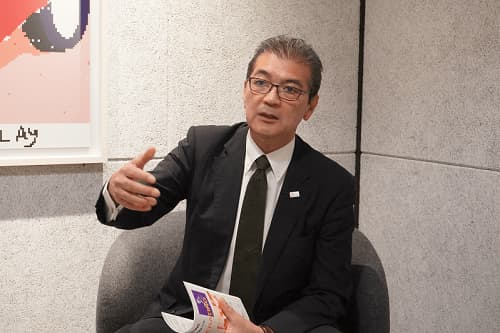
加藤:日本の課題は、化石燃料に頼った電源構成だったり、再生可能エネルギーの開発拡大がいろんな理由で進んでないことです。JCIのメンバーはほぼ需要家です。熱電源を電化したり再エネを利用したり努力するわけですが、いろんな課題があって進まない。
今の日本の政策は国際的に見て、どちらかというと保守的です。「ベース電源として化石燃料をある程度維持しながら、再生可能エネルギーをちゃんと拡大しましょう。それから原子力も利用しましょう」とあまり“野心的”ではないし、グローバルスタンダードとのギャップがあります。
もっと政府が野心的な目標を掲げないと、特に需要側の企業は、脱炭素やカーボンニュートラルに対応できない。取り組みがそれなりのレベルに達しないと、世界中のパートナーやお客さまに認められないわけです。そういった国際競争力を失うという危機感と、あとはコストですね。
円安の影響はあるかもしれませんが、コストの面でやはり化石燃料や原子力は、実際はコストアップであって、再エネは毎年、コストダウンが図られている。それからエネルギー安全保障という問題。30兆円余りを原油国に支払う輸入に頼っている不安定さから脱却し、その原資を使って国内の再エネベースの地産地消のエネルギーシステムを構築し自給率を高めることが賢明な政策と考えます。
日本の取り組みを加速させるためには、世界中が今政策として進めているカーボンプライシングを導入していかないと、自然エネルギーの転換やカーボンニュートラルの移行がスピードアップしません。この数年間、需要側が期待しているのはそのスピードアップです。
――提言にあたって、JCI内でどのような議論をされたのですか。
加藤:カーボンプライシングという言葉が出始めた時、一時的にコストアップ、増税のような感覚を持たれる方が多かったと思います。ですが、真面目にやっている人たちにはメリットがあるし、CO2排出を減らすことが大前提になっているので、排出しているものに対して課税することは当然の理であり、提言するべきだと多くの意見が出ました。
カーボンプライシングによって、CO2を排出しないようにみんなが工夫していけば、脱炭素の取り組みを加速させることができます。排出がなくなればコストはゼロになるわけですし、長期的に見れば非常にメリットがあります。
提言書は、メンバー企業と分科会を設けて、何回も議論を重ねて作り上げました。この具体的かつ詳細な提言に、JCIに参加する210ものメンバーが賛同しました。この提言をはじめ、JCIが出す提言は、賛同する個々のメンバーの声として、各団体名を添えて発表しています。
――需要側からの提言は、インパクトがありますね。
加藤:経済産業省などにお持ちしたときには、「冗談でしょ」くらいのリアクションがありました。省庁で政策を固めるときには企業へのヒアリングがありますが、今までは重工業や電力、鉄鋼、自動車というような、経済界を支えてきた企業・学識者に偏っていたと思います。JCIのようなさまざまな企業・団体の需要側からの提言は、インパクトがあったのではないでしょか。経産省のGX推進部門から、継続的にヒアリングしたいと言っていただきました。GXは今後、カーボンニュートラルを進める大きなフレームワークになるので、GX推進戦略にもJCIとしての要望を織り込んでいきたいと考えています。

――昨年のCOP28では、現地でイベントを開催されていましたね。今回のCOPの成果や課題をどのようにお考えですか。
加藤:地球沸騰化で緊急性が高まる中、2030年までに再エネ3倍、エネルギー効率2倍、化石燃料からの脱却に向けたこの10年の行動加速が合意されました。エネルギー効率化に日本は貢献できるし、日本にとっては大きなビジネスチャンスです。課題は、2030年までにどう再エネを3倍にし、化石燃料からの脱却を加速するかということですね。
COPの画期的な成果が出たとき、「日本政府や社会全体が、それを真摯(しんし)に受け止めて本旨をしっかりと捉え、逃げることなく立ち向かわなくては」と思いました。これに取り組まないと、ますます日本が取り残されてしまいます。
今年4月のG7気候・エネルギー・環境大臣会合でも「2030年代の前半で石炭火力は使用しない」と共同宣言が出されましたが、あの本旨は「脱炭素を加速させるべきだ」という世界のコンセンサスであり、アンモニア混焼や水素混焼などで化石燃料系の電源を延命させることではありません。
世界中で、あるいは日本でも、ある程度実証された解決策があるので、つまりそれが再エネなのですが、それを思い切りやるべきです。そこはさらに声を上げていかなきゃいけないだろうと思います。
今年はエネルギー基本計画の見直しと、来年初頭に提出する2035年温室効果ガス削減目標(NDC)の策定がスタートしましたが、1.5度目標と整合した野心的な目標値を明確に定めて、それに向かっていろんなセクターが、もっとスピーディーに対応・移行していく必要があります。JCIは7月上旬にそのエネルギー基本計画やNDCに向けた提言を出す予定[^undefined]です。より多くのJCIメンバー賛同、更にはJCIメンバー以外の方々にも賛同を求めています。
※ JCI「2035年66%以上(2013年比)のGHG削減目標を日本に!」
https://japanclimate.org/news-topics/jci-message-2035ndc/

――企業や市民など立場を超えて、声を上げることは大事ですね。
加藤:国連の提言でもアドボカシーの重要性は言われています。やはり、自分たちが取り組んでいるだけでいいわけではなく、周りに影響を及ぼし社会全体を変革させなくてはいけないのです。JCIとして政府とのパイプを太くし、「声」を増幅させていくことが重要だと考えています。
――JCIのイベントを中継で拝見しましたが、COP会場には、多くの日本企業の姿が見られました。
加藤:いろんな日本企業の社長含め経営層の方々が来場されていて、課題に対する意識の高さを実感しました。
COP28では、ただ単に脱炭素に取り組めばいいというわけではなく、「ジャストトランジション(公正な移行)」で包括的に取り組むことが求められました。ネイチャーポジティブや人権など、包括的に考えてカーボンニュートラルを実現するのだと、自分にとっても改めて学びになりました。
それから、CO2を減らせば、逆に影響を被る人が当然います。「Hard to Abate」(CO2低減が困難な産業)をどうするのかといった、「真のトランジション」ということまで議論していかなくてはいけない。そう改めて考えさせられました。
――日本は、政策を推し進めるスピード感が課題ですね。そして、それを企業・団体が後押しすることも必要になってきます。
加藤:こちらから声を上げないと、それは当然、政策には反映されません。アドボカシーとはそういうことだと思います。次の第7次エネルギー基本計画とNDCに、エネルギーの需要側を含む多様なステークホルダーの意見がきちんと反映されているのかが肝になると思います。
――声を上げるには、個人の意識改革も必要になるのではないでしょうか。今まで法制だから対応してきたところがあり、受身の姿勢に慣れてしまっているので、まず意識改革をしないと、企業としても声を上げることが当たり前、とはなりづらいと思います。
加藤:そうですね。例えばロビー活動は良きにつけ悪しきにつけ、特に米国では、一企業でもベストな環境にするためにいろんな政策提言をして、政策決定プロセスに意見しています。ですが、日本はなかなかそれがない。それは今おっしゃったような、意識の違いや国民性の違いもあるでしょう。
ただ本当に社会全体を良くするためには、意見を出し合わず、政府が言ったことだけに追従するだけでは駄目ですし、多様性も求められているわけですから、狭い視野による政策もベストとは言えない。やはり、声を上げることが必要ですし、政府も政策決定プロセスの中により多様なアクターの声を織り込むことが重要だと思います。
また、同じような思いを持った人たちが集まった方が、声を上げやすいでしょう。
今回のカーボンプライシング提言も、おそらく一社だけでなら出す機会はないし、パワーも出ない。そこにJCIの存在意義があります。あとはJCIだけでは声の強さは限られているので、もっといろんな方々と連携をしながら、より良い社会、脱炭素社会の実現に向けて協働していきたいですね。
加藤 茂夫(かとう・しげお)
株式会社リコーで欧州事業、本社統括に従事したのち、2015年からサステナビリティ担当役員として、脱炭素宣言、日本企業として初のRE100参画を実現。事業活動とSDGsを同軸化するESG経営への変革をリード。その後、日本気候リーダーズ・パートナーシップ(JCLP)の共同代表、 World Environment Center(WEC、本部米国)やグローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン(GCNJ)の理事として、気候変動問題を中心に企業・産業界の社会課題解決への貢献をけん引。外務省の「気候変動に関する有識者会合」のメンバーに加わる。2018年7月に気候変動イニシアティブ(JCI)設立に参画し、2023年共同代表に就任。
