
株式会社ガイアックスは、「フリー・フラット・オープン」な社風づくり、そしてアントレプレナーシップ(起業家精神)を重視した人材育成に注力している。
これは、社員のキャリア自律を促進しつつ、組織としてのイノベーション力向上につなげるとともに、同社が掲げる企業理念である「人と人をつなげる」こと――「人と人とのコミュニケーションの促進や、コミュニケーションを行うサービスや事業の創造に力を注ぎ、世の中全体を思いやる社会の実現に取り組む」――の実現を支えるものとみられる。
人材育成支援を手掛ける、株式会社FeelWorks代表の前川孝雄さんが、ガイアックスの上田社長にオンラインの対談形式でインタビューを実施した。
20代起業家を続々と輩出する同社の企業理念・ミッションへの取り組み、経営人材を育てる自律分散型組織づくり、今後の展望などについて、深く話を聞いた。
《お話し》上田 祐司さん(株式会社ガイアックス 代表執行役社長) 《聴き手》前川 孝雄(株式会社FeelWorks代表取締役/青山学院大学兼任講師)
仕事で失敗するしか学びはない
<リーダーはメンバーの夢を変えよ!「アップサイド」引き出すガイアックスの人材育成の流儀とは【インタビュー】>の続きです。
前川 孝雄 御社は、人材育成にはそこまで力を入れていないともうかがいました。しっかりとしたwillがあれば、個々が主体的に能力開発に向かうということでしょうか。
上田 祐司さん 「育てる」という観点よりも、本人が存分に学べる環境を用意することが大事だと考えています。
自分が決めた難しい夢に向かうことに、総じて周囲の理解があり、自分のやりたいようにどんどんと攻め込んで行く。
その中で、一緒に働いてくれるメンバーや、お客様や、出資者に対する義務の重さに押しつぶされそうになるというのが、学ぶ環境だと考えています。
前川 なるほど。先ほどのお話と同様で、環境は用意するので、自ら進んでシビアな市場の中で存分に学べということですね。
上田さん 仕事で失敗するしか、学びはないと思っています。
前川 それは至言ですね。世間的には、失敗をさせないがために早め早めに教育やアドバイスをしようとしがちです。そうではなく、失敗から自ら学ぶことが一番だということですね。
上田さんや事業リーダーたちも、メンバーに対して失敗しないようアドバイスすることは控えるわけですか。
上田さん いえ。お互いに、いろいろと好き勝手に口は出します(笑)。でも、的外れなこともあるし、聞くか聞かないかは本人の自由なんです。
前川 どうやら、一般的な組織における上司と部下の関係とは少し違っていて、ステークホルダーという感覚なのかもしれませんね。
それにしても、御社は上場もしていて、傘下企業もあり、株主の目もあって、企業全体としての経営は難しくないですか。持ち株会社に対しても、議決権行使はしないとのお話も聞きましたが...。
上田さん もちろん難しさはあります。傘下企業の運営にも、いくつかルールは設けています。社長の給与は1000万円までで、それ以上必要なら株の配当で取ることなどです。第三者割当増資なども悩ましいですね。
しかし、各経営者が自社株を持ち、その価値を自ら何とか高めようと努力している中で、こちらが議決権をちらつかせてもあまり意味はないでしょう。
前川 各経営陣とも、自分たちで必死に何とかしようとしていて、自ずと結果が出る。だから、任せて見守るのみというわけですね。ここも「倒し切っている」発想ですね(笑)。
定款、規程、マニュアルだけで動く理想の会社とは

前川 残念ながら、日本企業で働く人たちは、世界と比してエンゲージメントがとても低く、最下位ラインの現状です。これまでのお話とも重なる部分が多いとは思いますが、これからの働きがいのある会社とはどのようなものだとお考えですか。
上田さん 事業構造の透明化が重要だと思っています。
お客さんからの期待や喜びをダイレクトに体感できることが大切なのですが、それが組織の中をきちんと流れて通っているのかということです。最前線の営業だけは感じていても、その一歩後ろのメンバーに通じていないというのはありがちです。それを、構造上分かるようにしておくべきなのです。
前川 全従業員が内向きにならず、顧客や社会に向くためにも、とても大事なことですね。
私が営む会社でも、売上という言葉は使わず「お役立ち」という言葉を使っています。最前線の営業のみならず、全従業員が世のため人のために自分はお役に立っているのかを感じながら働いてほしいからです。御社では、どのように進めているのですか。
上田さん 実は、私たちが進めているDAO(自律分散型組織づくり)は、そこをとてもよく分かる仕組みにしています。
ブロックチェーン上だけに存在するDAOでなく、ごく普通に世の中に存在する組織づくりを目指しています。それはすなわち、「定款と規程とマニュアルで動く組織」です。
前川 それだけを聞くと、ごく普通のことに思えますが。定款、社内規程、業務マニュアルのない会社はありませんよね。
上田さん 私が理想とするのは、本当にその3つだけで動く組織です。
そうなれば、上司は果たして必要かと問いたいのです。いまの取締役会は、定款類には書かれていない例外事項を話し合い意思決定します。管理職である上司も、それらに書かれていないことをマネジメントしているわけです。
であるならば、株主総会の決議項目に定款、規程、マニュアルを上げてしまい、詳細な内容まで随時更新されていけば、取締役会も管理職も不要です。当面、会社法上の代表取締役は必要ですが、それも定款類の操り人形です。上司からの指示命令も必要なくなります。
働くメンバーは定款類に書いてある組織のパーパスや運営ルールと、お客様のニーズを満たす仕事と直接向き合えばよいのです。
出資者に対しては、その定款類の内容がエレガントだと感じたら出資してくださいと頼みます。定款類に必要な改善点があって、株主総会の議案に上がればどんどん更新する。定款類はすべてオープンなので他社も真似できますが、弊社は更新の速さで勝負しますと説明するのです。
そうした構造をすべてオープンにすれば、その組織が自身のパーパスやミッションにどれだけ向き合って動いているのかも、すべて可視化されるわけです。そういう会社を、世の中に量産していきたいと考えています。
▼ガイアックスの取り組み事例:「日本初、『株式会社型 DAO』による歴史的建造物への小口投資プロジェクト」(2024年6月3日)
前川 倒し切っていますね(笑)。その組織像は、今、優秀な若手の早期離職が激増している伝統的な組織の改革に向けた一つの答えでもありますね。
今の若者たちは、SDGsやESGなどもよく学び、各企業の経営理念やビジョンに共感して会社を選ぶ傾向も強くなっています。
経営トップの言葉や人事の説明に期待して入社してみると、言っていることと現場でやっていることが全く違うと感じてしまう。日々の仕事やマネジメントに幻滅して、辞めてしまうケースが多いのです。
だから、真っ当な定款や、規程、マニュアルがあれば、徹頭徹尾その通りに組織運営せよということですよね。しかし、そうなると、そこでの経営リーダーやマネジャーの役割とは一体どうなるのでしょうか。
上田さん 現在の私たちは、そうしたビジネスを生み出す会社の経営者として、当面役割を果たしていますが、仕上がった各ビジネスにおいては、経営陣の相対的存在意義は減っていくでしょう。
私自身、経営者は組織の大小にかかわらず3人から5人で十分だと感じています。私たちのDAOへの取り組みは始めてまだ日が浅いので、今後いろいろな事例を作っていきたいと考えています。
前川 つまり、取締役や管理職は、しっかりとした定款、規程、マニュアルの仕組み作り上げるために必要な役割であって、それらが完成すれば不要になり、自律分散型で組織は回るだろうということですね。いゃあ、本当に倒し切った発想ですね。
DAO(自律分散型組織づくり)がめざすもの

前川 DAOの取り組みの中で、現時点で、手応えを感じている事例がありますか。
上田さん シェアハウスをDAO化した例があります。住んでいるお客さん自身が株主で、ハウスルールもサービス提供者が決めるのではなく、いわゆる株主総会で決めるのです。必要な設備についても、100万円を渡すので、自分たちで相談して好きなものを買ってもらいます。
サービス提供者にとっては、設備について適切なものを選ぶのも買い付けるのも手間ですし、買ってきたものが不評で入居者から苦情を言われても困ります。皆で投票して意思決定できる仕組みで対応してもらえれば、助かります。
新規入居者の決定や受け入れ対応も、入居者がやってくれます。この仕事には報酬のトークン(デジタルマネー)がもらえるのですが、新規入居者が入れば、その分自分たちのトークンも増える仕組みです。
ハウスの人口密度が増えるのはマイナスもあるけれど、人数が増えれば自分たちにも利益があるという、オーナー感覚なわけです。
それまで、管理会社がシェアハウスを月に何回か見に行っていたのに、今は年に数回です。というのは、ハウスでの情報交換や意思決定がすべてネット上のやりとりで閲覧でき完結しますから、他の物件以上に現場に行かなくても手に取るように様子がわかるのです。
▼ガイアックスの取り組み事例:「日本初の DAO 型シェアハウス『Roopt DAO』、 開業から 1 年で売上 1.7 倍&利益率の大幅改善を達成~DAO で稼働率 UP&運営・集客コスト減を実現~」(2023年10月11日)
前川 いままで、わざわざ管理会社をつくって一生懸命に物件管理をしていたのが、自律分散型組織にすることで、不要になったということですね。
上田さん このように、ICTが進化しているので、日本の行政の仕組みにも同じことが応用できるはずなのです。これまでは地方や国の代議士を選んで、行政を動かしていました。
でも、イシューごとの国民投票がテレビの赤青緑のボタンでもサクッとできてしまう。我々の会社組織も株主総会で取締役を選んで、取締役が毎週会議をして物事を決めています。
でも、今時の株主総会など、ICTを駆使すれば一瞬で行えますし、何週間も前に招集通知を出す必要もない。定款変更の定足数を10%などに設定しておけば、サクサク更新も進みます。
前川 その考え方と仕組みを実際に広げていくことができれば、会社も社会もガラリと変わりますね。
ルールに縛られず、社会を展望できる視野の広い人が増えること
前川 最後の質問です。行き過ぎた資金主義による社会問題が噴出して不安定になっているのが現代です。第三次世界大戦勃発の危機感も高まっています。
この中で特に優秀な若手ほど社会問題への感度が高く、自身の成長を強く望んでいます。政治への信頼も失われ、旧来型の大組織も敬遠されつつある中、企業のあり方も問い直されています。
これまでうかがったお話と重複する部分もあるかとは思いますが、今後の人を活かす経営をどう考え見据えていけばよいか、ご意見や展望などお聞かせください。
上田さん ことさら資本主義と闘おうとは思いませんが、資本主義は本当に間違っていて駄目だと思います。とにかくひどく非効率です。現在の資本主義や民主主義の形は、僕らが作った一つのハウスルールにすぎません。
にもかかわらず、ルールは絶対で、その下に生まれたからにはルールを守って生きていかなければならないと勘違いしているのではないでしょうか。金持ちになるのも別に悪くはないですが、ルールの中だけで自分の夢を設定する必要もない。
だから、視野の広い人がもっと増えていくことが大事なのです。私たちがすべきことも、私たちが関わる一人ひとりのメンバーに、ただ与えられたゲームの中で最高点を叩き出させることじゃない。そもそもこの社会はどうあるべきなのか、そのために自分は何を成すべきかなど、幅広に考えられる場を提供したいと思います。
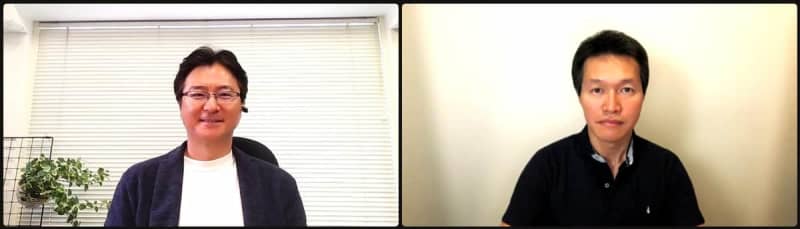
前川 自分たちの祖先が、たかだか数百年前につくったルールが絶対だと誤解していないか。もっと視野を大きく持つべきだし、そうしたスケールの大きな人がたくさん育つ環境をつくろうということですね。
現代社会は不安定で生き辛いといわれ、政治への信頼もがた落ちするなか、経済的に存在感を失っていくことに悲観論も多い日本。でも、実は私たち一人ひとりが、自ら無意識の固定観念や既成概念の呪縛に陥っている部分も大きいのかもしれませんね。
本日は、常識を揺さぶられる深いお話を存分にうかがうことができました。御社の構想と取り組みがさらに大きなソーシャルインパクトとなり、世の中全体を思いやる社会が実現していくことをおおいに期待します。ありがとうございました。
